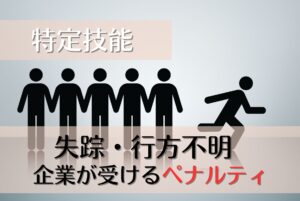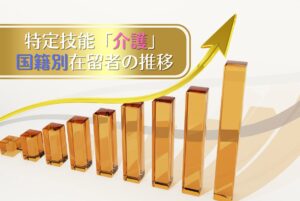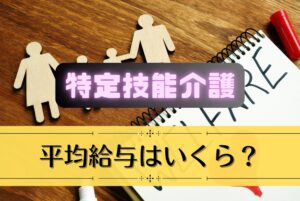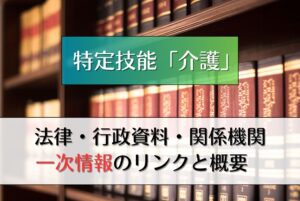介護現場の人手不足が深刻化する中、外国人材の活用を検討する企業や施設が増えています。
その中でも注目されているのが、在留資格の一つである特定技能「介護」です。
しかし、制度の概要や従事できる業務範囲、受け入れに必要な条件については、まだ十分に理解されていないことも多く、正しい知識がないまま採用を進めてしまうと、思わぬトラブルや人材のミスマッチにつながるおそれがあります。
この記事では、特定技能「介護」の制度の仕組みや取得要件、任せられる業務内容、さらに受け入れ機関が満たすべき基準までを整理して解説します。
制度を活用する上での注意点や、採用パートナーとして適した人材会社を選ぶ際の視点についても触れ、初めて外国人介護人材を採用する方でも安心して判断できる情報を提供します。
特定技能とは

特定技能は、国内での人材確保や業務効率化を進めてもなお慢性的な人手不足が解消されない分野において、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格制度です。
制度は2019年に創設され、2025年9月現在において、受け入れ対象分野は人手不足が特に深刻な16の産業分野に限定されています。
この制度には、相当程度の技能を有することを条件とする「特定技能1号」と、より高度で熟練した技能を求められる「特定技能2号」の2種類があります。
産業分野により詳細な基準は異なりますが、特定技能1号の許可を取得するには、日本語能力や技能水準の確認が必須であり、一定の基準を満たした人材のみが在留許可の対象となります。
介護分野については特定技能1号のみが認められており、在留できる期間は通算で最長5年です。
在留期間は許可時に1年・6か月・4か月のいずれかで決定され、都度更新を行います。
5年を超えて継続して働く場合は、「介護福祉士」の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行する必要があります。
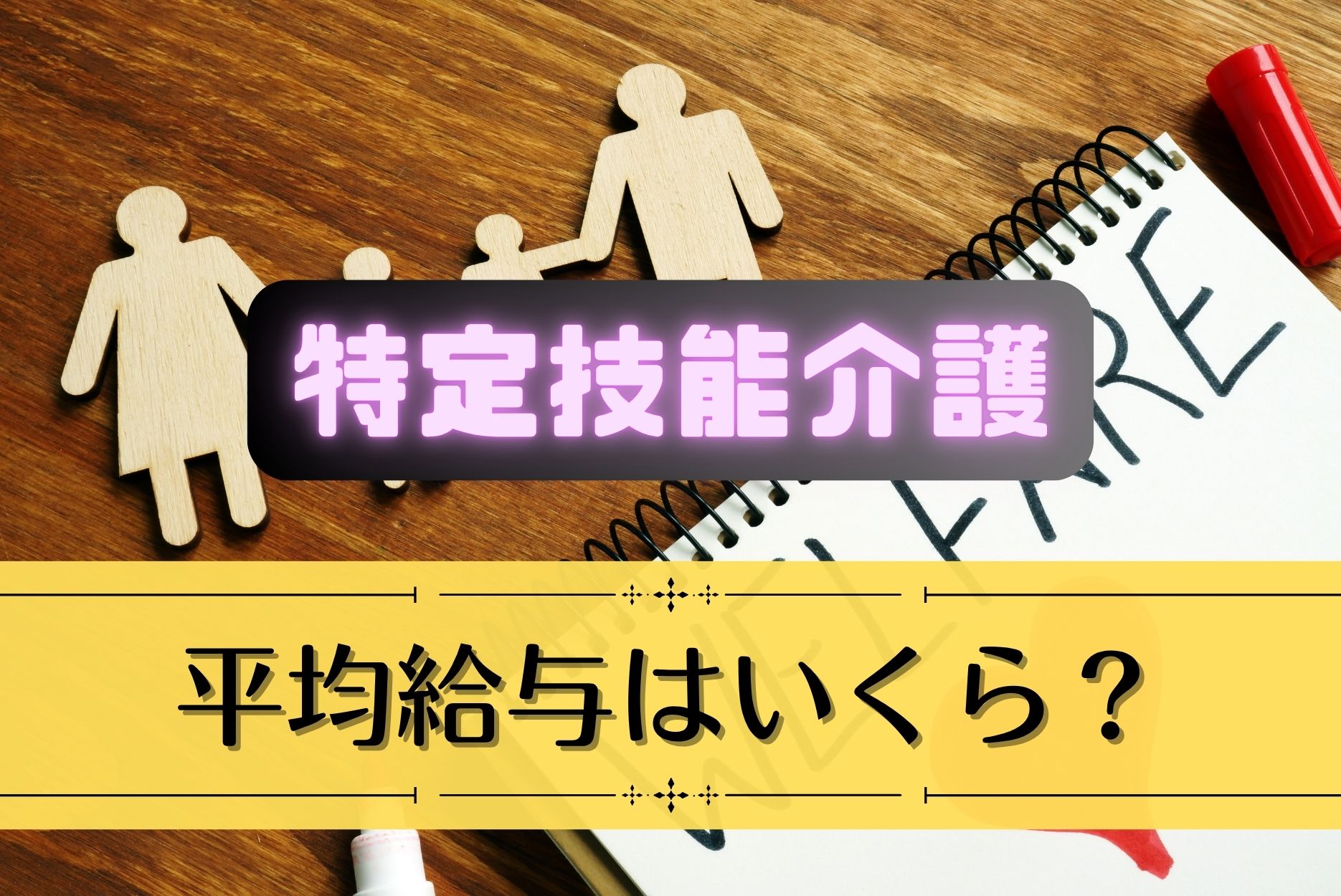

特定技能「介護」の業務内容

特定技能「介護」では、利用者の身体介護や生活支援を中心に、介護現場で幅広い業務を担当します。制度の拡充により、従来対象外だった訪問系サービスも条件を満たせば従事可能となり、活躍の場はさらに広がっています。
以下に、特定技能「介護」で従事可能な業務の詳細を解説します。
従事可能な業務
特定技能「介護」では、入浴や食事、排せつといった日常生活の身体介護を中心に、利用者の生活を直接支える業務に従事します。
これには移動や着替えの介助など、利用者の状態に合わせた生活上の支援も含まれます。
加えて、レクリエーションの企画や進行、機能訓練の補助など、心身の活力維持や回復を目的とした関連業務にも携わることができます。
こうした業務は介護サービスの質を高め、利用者の生活の質向上に直結します。
一方で、介護施設内であっても経営管理、医療行為、事務処理など介護業務に該当しない作業を行うことは認められていません。
従事範囲は「介護」に該当する業務のみに限られており、その枠組みの中で役割を果たすことが求められます。

訪問介護の追加要件
特定技能「介護」の在留資格で訪問介護に従事するには、介護保険サービスの指定事業所で1年以上の実務経験を有するか、日本語能力試験N2以上に合格していることが前提となります。
さらに、日本人介護職員と同様に介護職員初任者研修を修了している必要があります。
そのうえで、以下の追加要件を満たすことが求められます。
- 訪問介護の基本事項に関する研修を受講すること
- 一定期間、責任者などによる同行訪問を実施すること
- 本人の意向を確認しつつ、訪問介護業務に対応したキャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のため、相談窓口を設置すること
- 緊急時の対応が可能となるよう、情報通信機器など必要な設備を導入すること
これらの要件は、訪問介護における安全性とサービス品質を確保するために設けられており、受け入れ事業所には計画的な人材育成と継続的な運営体制の維持が求められます。
特定技能「介護」の雇用形態と受け入れ人数
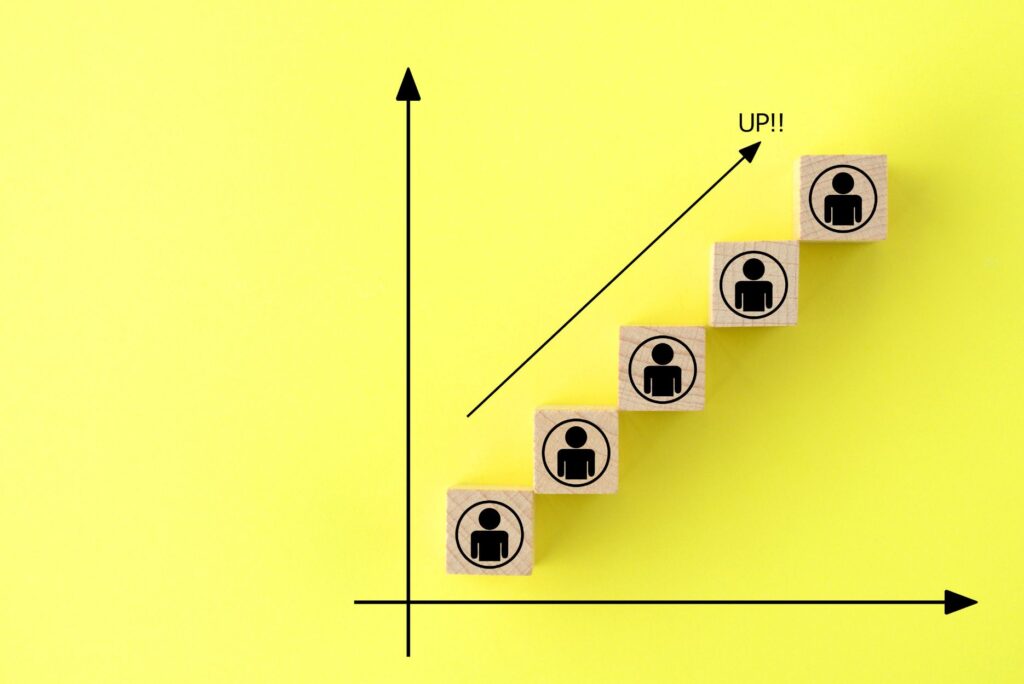
特定技能「介護」の制度を活用して外国人材を採用する際は、雇用契約や受け入れ可能な人数に明確な基準があります。
ここからは、人材受け入れのために事前に押さえておくべき受入れルールについて解説します。
フルタイムの直接雇用契約が必要
特定技能「介護」の在留資格で就労する場合、雇用契約は介護事業者との直接雇用に限られます。
派遣契約や短時間勤務といった形態は認められておらず、原則としてフルタイム勤務が前提となります。
また、雇用契約の内容は、日本人職員と同等以上の待遇を確保することが求められます。
これは報酬額や勤務時間だけでなく、社会保険や有給休暇などの福利厚生面も含まれ、差別的な取り扱いは許されません。
この基準は、外国人介護人材の安定した生活基盤を守るとともに、日本人職員との公平性を確保するために設けられています。
適正な契約形態と条件整備は、長期的な人材定着にも直結します。
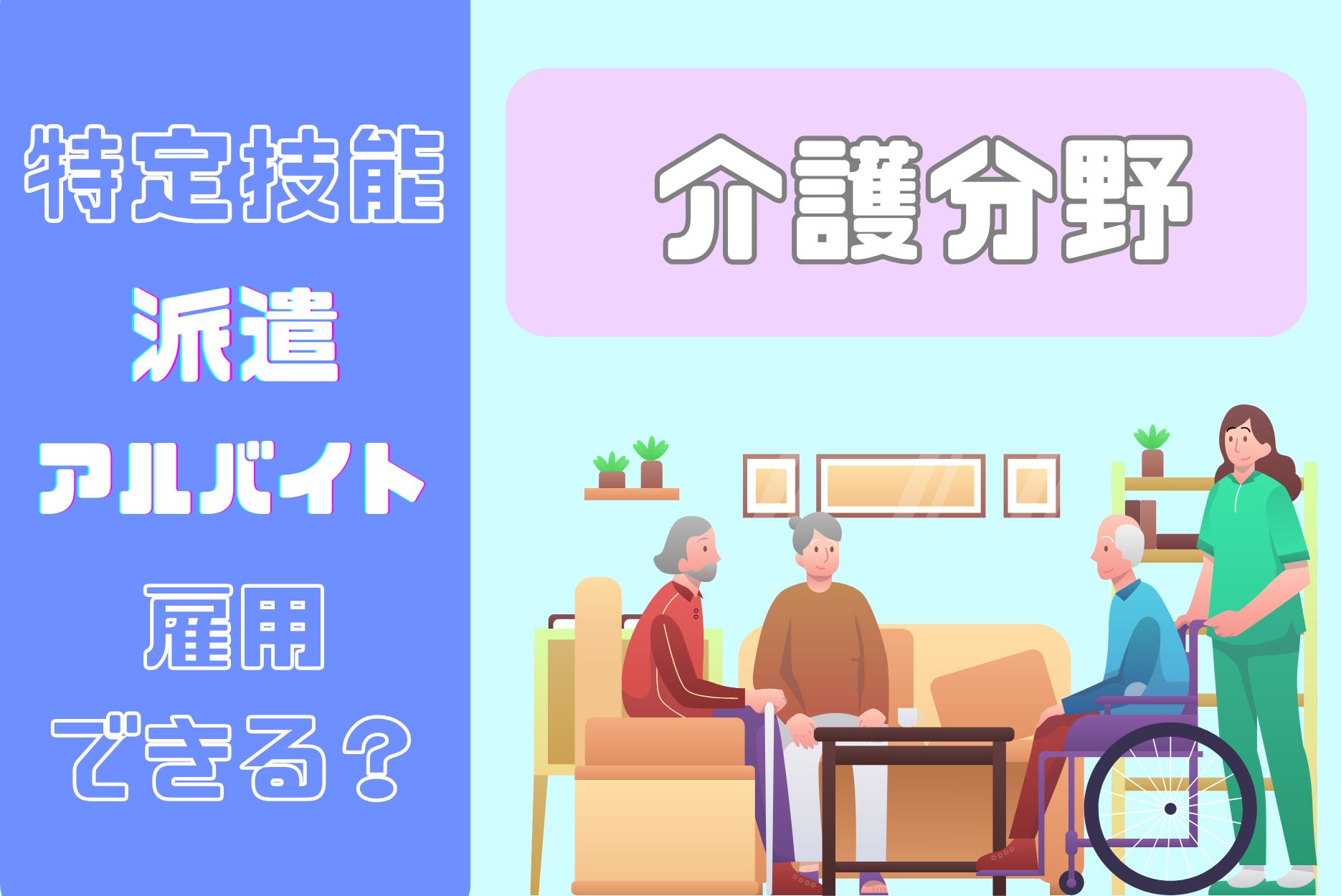
受け入れ人数の上限
特定技能「介護」の受け入れ人数の上限は、「事業所ごとの常勤介護職員の総数」を超えない範囲です。
ここでいう常勤介護職員とは、介護を主たる業務として従事している職員を指し、事務職や就労支援担当者、看護師などは含まれません。
ただし、医療機関などで身体介護と同様の業務を中心に行う看護補助者や、その指導を行う看護師は例外として常勤介護職員数に算入されます。
また、この常勤介護職員には、永住者や定住者、在留資格「介護」などの外国人介護職員は含まれますが、特定技能1号や技能実習、留学生の介護職員はカウントされません。
実際の受け入れ可能数を把握する際には、職務内容や職員一人ひとりの状況を正確に確認する必要があります。

外国人本人側の許可基準

特定技能「介護」で働くには、日本語能力や介護技能の試験合格など、外国人本人が満たすべき許可基準があります。
ここでは、外国人本人に課せられる在留許可の要件を解説します。
特定技能全分野の共通要件
特定技能の全分野に共通する許可基準は、外国人材の適正な受け入れと外国人本人の権利保護を目的として定められています。
主な要件は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 健康状態が就労に支障のない水準であること
- 有効な旅券を所持していること
- 特定技能1号の在留期間が通算5年に達していないこと
- 保証金の徴収や不当な金銭管理など、権利を侵害する行為を受けていないこと
- 外国側で支払う手数料などの内容を理解し、外国人本人が同意していること
- 外国の送り出し機関を通じ、正規の手続きを経て入国すること
- 食費や住居費など本人が負担する費用が適正な水準であり、外国人本人がその内容を理解し合意していること
介護分野の固有要件
介護分野の特定技能1号を取得するには、介護業務に必要な知識と技術、さらに現場での円滑な意思疎通能力を証明する試験に合格することが条件となります。
合格が必要な試験は以下の通りです。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
上記3つの試験に合格することで、介護分野の特定技能1号で求められる技能水準と日本能力水準を満たしていると判断されます。
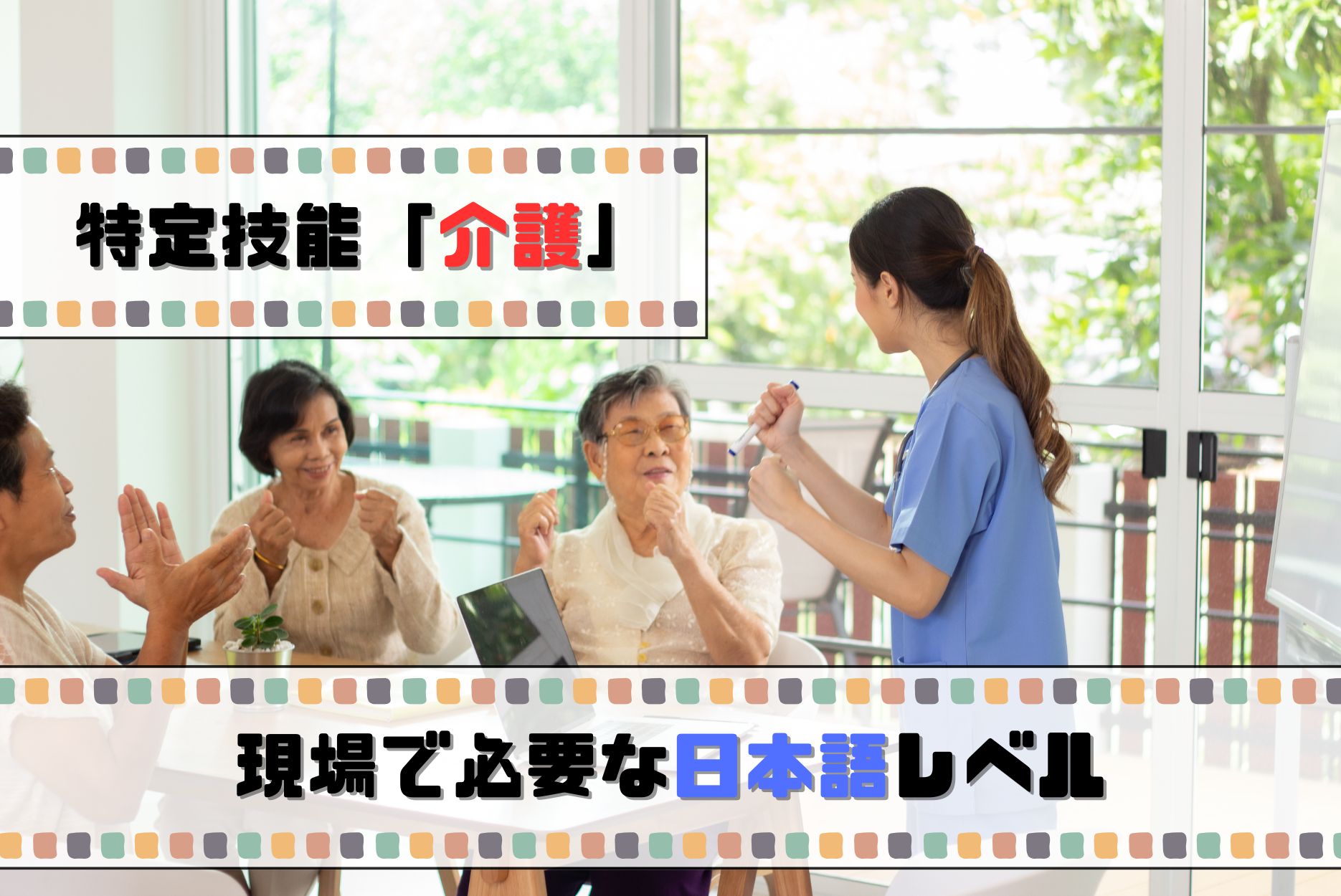
技能実習修了者は試験免除制度がある
「介護職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能「介護」への移行時に試験免除の措置があります。
この場合、介護技能評価試験、日本語試験(日本語能力試験N4以上またはJFT-Basic合格)、さらに介護日本語評価試験のすべてが免除されます。
一方、介護分野以外の技能実習2号を良好に修了した者については、日本語試験(JLPT N4相当またはJFT-Basic)のみ免除され、介護技能評価試験および介護日本語評価試験は受験が必要です。

受け入れ事業者側の許可基準

特定技能「介護」の人材を採用するためには、受け入れ事業者側も法令で定められた許可基準を満たす必要があります。
ここからは、受け入れ企業が満たさなければならない各種要件について解説します。
特定技能協議会への加入義務
特定技能で介護人材を採用する場合、受入れ企業は、一人目の雇用の在留資格申請を行う前に、介護分野の特定技能協議会へ加入しなければなりません。
さらに、採用した外国人が就労を開始してから4カ月以内に、その外国人に関する情報を協議会のシステムへ登録する手続きを完了させる必要があります。
登録済みの情報に変更が生じた際は、その都度速やかに変更登録を行うことが求められます。
これらの手続きを怠ると、受入れ資格の維持や更新に支障をきたすおそれがあります。
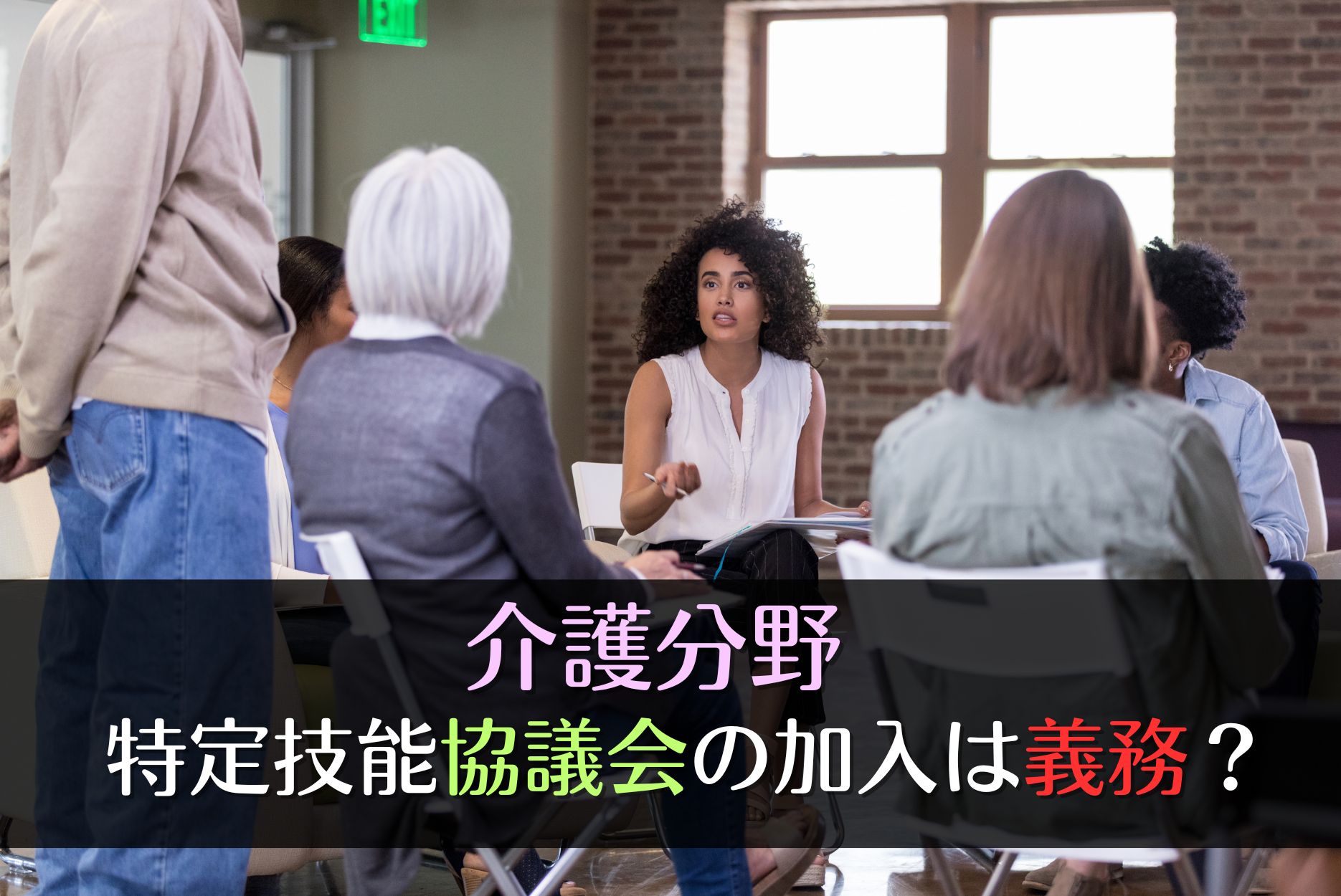
支援計画の策定
特定技能1号で外国人を雇用する事業者は、支援計画を作成し、その計画に基づいて支援業務を適切に実施しなければなりません。
また、作成した支援計画書は在留資格申請時に出入国在留管理庁へ提出することが義務付けられています。
支援計画に盛り込む内容には、法律で定められた「義務的支援」と、企業が自主的に実施できる「任意的支援」があります。
このうち、必ず計画に記載しなければならない義務的支援の内容は以下のとおりです。
- 入国前の事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎対応
- 住居確保や生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続に関する情報提供や行政機関への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談や苦情への対応窓口設置
- 地域住民や日本人との交流促進
- 人員整理などの場合の転職支援
- 定期的な面談と必要に応じた行政機関への通報
これらの支援は、外国人が安心して働き生活できる環境を整備し、職場定着を促進するうえで重要な役割を担います。
適正な雇用契約の締結
特定技能の在留資格を取得するためには、受け入れ企業と外国人労働者との間で結ばれる雇用契約が、法令や制度に沿った適正な内容であることが必須です。
適正な雇用契約の基準としては、以下の項目が定められています。
- 分野ごとに定められた業務に従事させること
- 労働時間が通常の所定労働時間と同等であること
- 同一業務に従事する日本人と同等以上の報酬水準であること
- 職業訓練や福利厚生、報酬面などで差別的な待遇を行わないこと
- 一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得できるようにすること
- 契約終了後、本人が帰国費用を負担できない場合は企業が負担すること
- 健康や生活状況の把握に必要な措置を講じること
これらの条件を満たすことで、外国人が安心して働ける環境が整うとともに、事業者側においても制度遵守の体制が確保されます。

欠格事由に該当しないこと
特定技能で外国人を受け入れる企業は、欠格事由に該当しないことが前提条件となります。
主な欠格事由としては、労働・社会保険および租税に関する法令を遵守していること、過去1年以内に日本人を含む同一業務で非自発的離職者を発生させていないこと、同期間に外国人の行方不明者を出していないことなどが挙げられます。
また、過去5年以内に拘禁刑以上の刑罰を受けていないこと、労働関連法令や技能実習法などで罰金刑以上の処分を受けていないこと、入管法や労働法に関して不正または著しく不当な行為を行っていないことも条件です。
不正・不当な行為には、旅券の取り上げや不当な外出制限、脅迫、人権侵害などが含まれ、刑罰の有無に関わらず受け入れ停止の理由となり得ます。
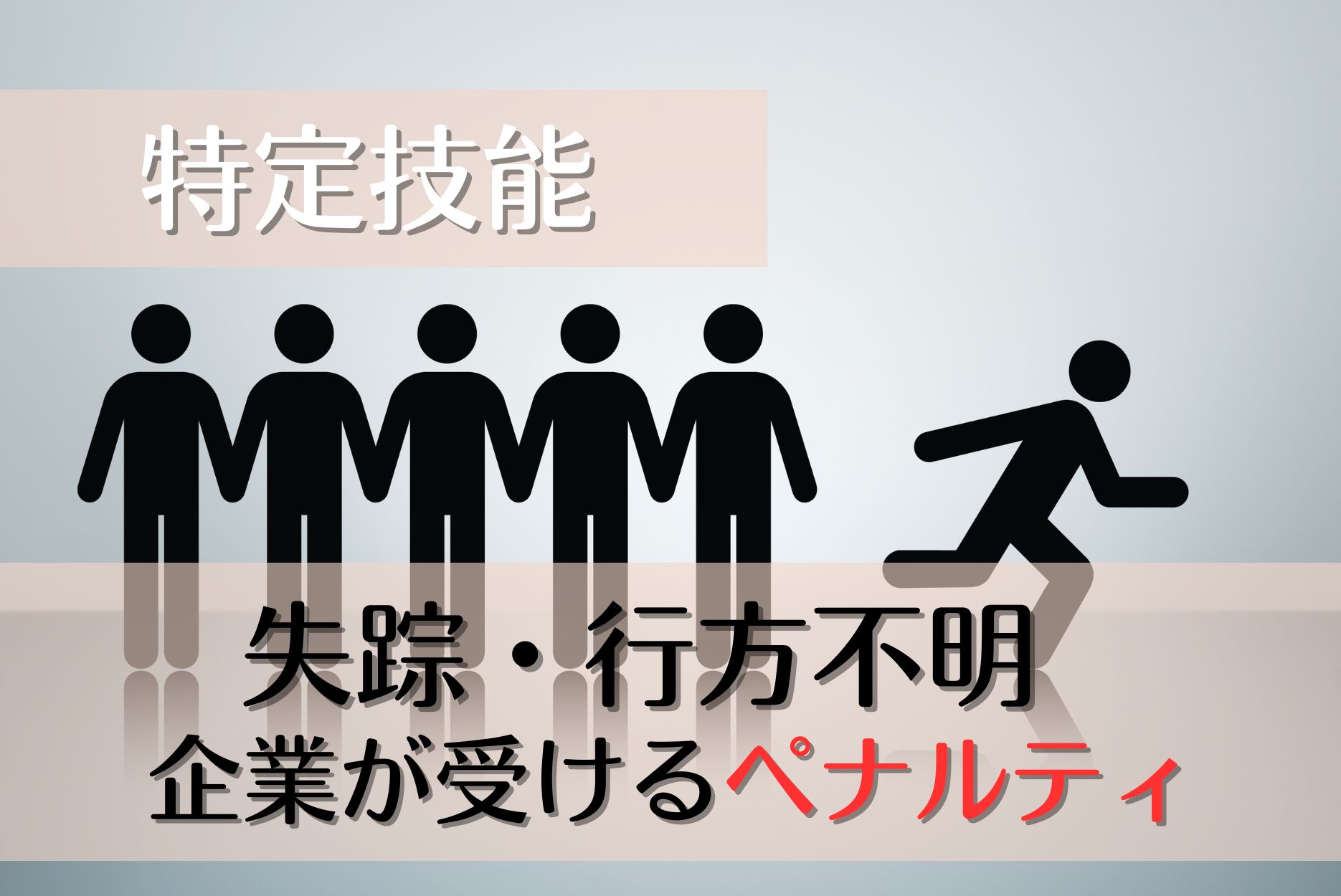
在留資格取得の流れ

在留資格の取得には、必要な準備や申請手続きを段階的に進めることが求められます。
ここでは、その全体像をつかむための流れを順を追って確認していきます。
海外から人材を採用する場合
海外から人材を採用する場合、企業と外国人双方が合意したら雇用契約を結び、企業が外国人の代理人として地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
認定証明書が交付された後は、それを外国人本人に送付し、本人が現地の日本大使館や総領事館で査証発給申請を行います。
査証の発給を受けた外国人は、日本へ渡航し空港等で入国審査を受け、許可が下りればその場で在留資格と在留期間が付与されます。
国内在留中の人材を採用する場合
国内に在留している留学生などを採用する場合は、雇用契約を結んだ後、外国人本人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
申請には、受入れ企業が作成する所属機関用の書類が含まれるため、企業は必要書類の準備や情報提供など申請手続きへの協力が求められます。

雇用開始後の受け入れ企業の義務

特定技能外国人を雇用する受け入れ企業には、就労開始後も法令で定められた複数の義務が課せられます。
ここでは、その具体的な内容を順に解説します。
定期届出と随時届出
特定技能外国人を雇用する企業は、定期届出と随時届出を行う義務があります。
定期届出は年1回実施され、4月1日から翌年3月末までの雇用・支援状況を、翌年度4月1日から5月末までの間に提出します。
随時届出は、行方不明者の発生、雇用契約内容や支援計画の変更など、特定技能外国人の雇用状況などに変化があった場合に行う手続きで、事由発生から14日以内に行う必要があります。
届出を怠る、または虚偽の内容を報告した場合、過料や特定技能外国人の受入れ停止といったペナルティを受ける可能性があるため、企業は適正な管理体制を維持することが重要です。
適正な在留管理
特定技能「介護」の在留資格申請で1度に認められる在留期間は最長1年であり、最長5年間の就労には複数回の更新手続きが必要となります。
更新申請は原則として外国人本人が行いますが、手続きを忘れたり不許可となった状態で就労を続けさせた場合、雇用主は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
そのため、受入れ企業は在留カードの有効期限を正確に把握し、更新時期には必要書類の準備や申請方法の案内など、従業員が適正に手続きを完了できるよう支援する体制を整えることが重要です。
支援義務の履行
特定技能外国人を採用した企業は、在留資格申請時に出入国在留管理庁へ提出した支援計画の内容を、継続的に実施する義務があります。
支援には生活面・職業面の双方が含まれており、特定技能1号外国人を雇用している限り、適切に履行しなければなりません。
この義務を怠った場合には、改善指導や勧告に加え、特定技能外国人の受入れ停止措置が取られる可能性があるため、支援義務は確実に実施する必要があります。
支援業務は登録支援機関に委託できる
特定技能外国人を採用する企業は、支援業務を外部の登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関とは、入管庁の名簿に登録された外国人支援の専門機関であり、月額2~3万円程度の費用がかかりますが、企業が本来の業務指導に専念したい場合には有効な選択肢となります。
ただし、委託できるのはあくまで支援業務に限られ、届出義務などの法律上の責任をすべて任せることはできません。
そのため、信頼できる支援機関を選び、委託範囲を双方で明確にしたうえで事業を運営することが、トラブル発生のリスクを抑えるうえで重要です。
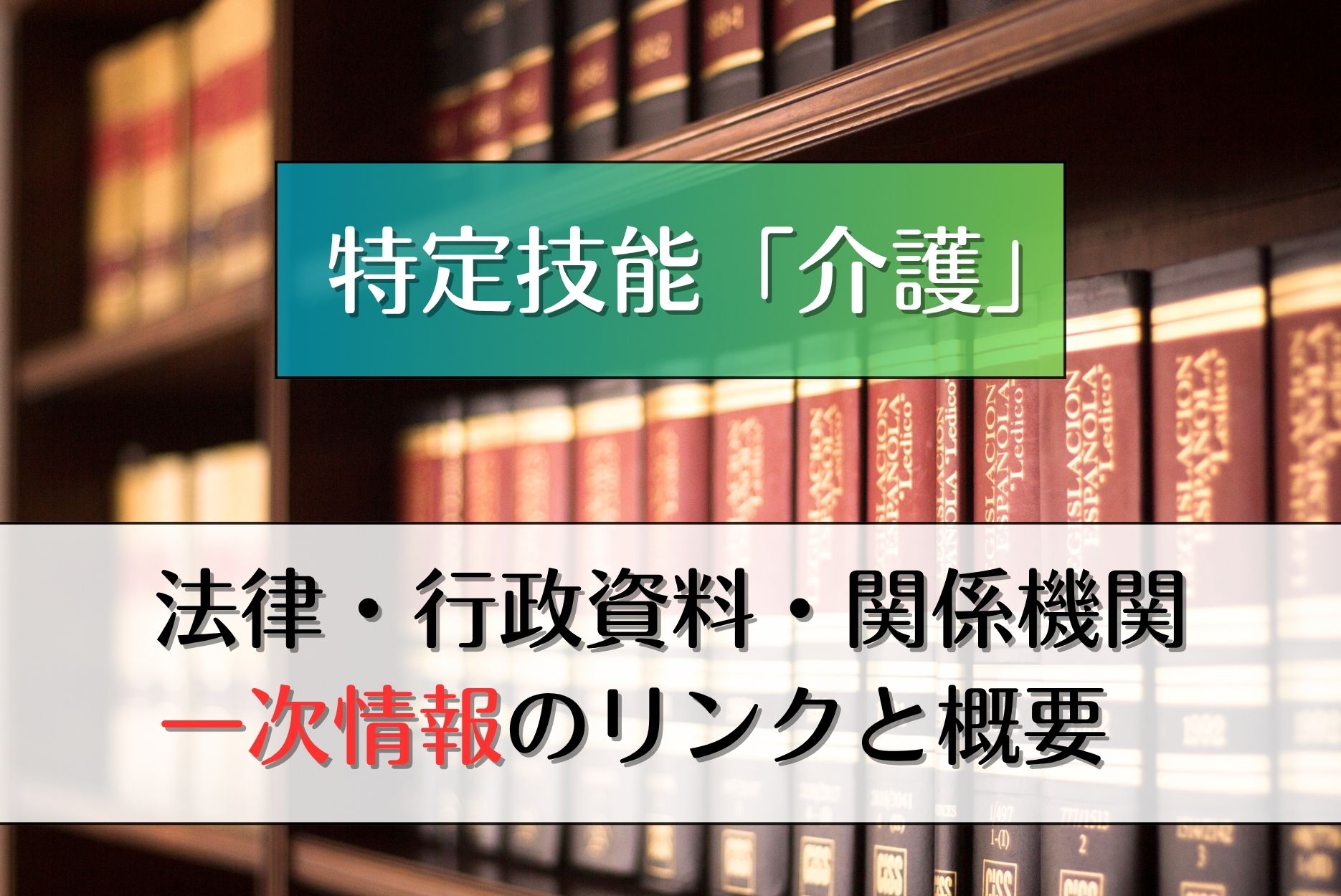
5年以上の就労を希望する場合は介護福祉士を目指しましょう
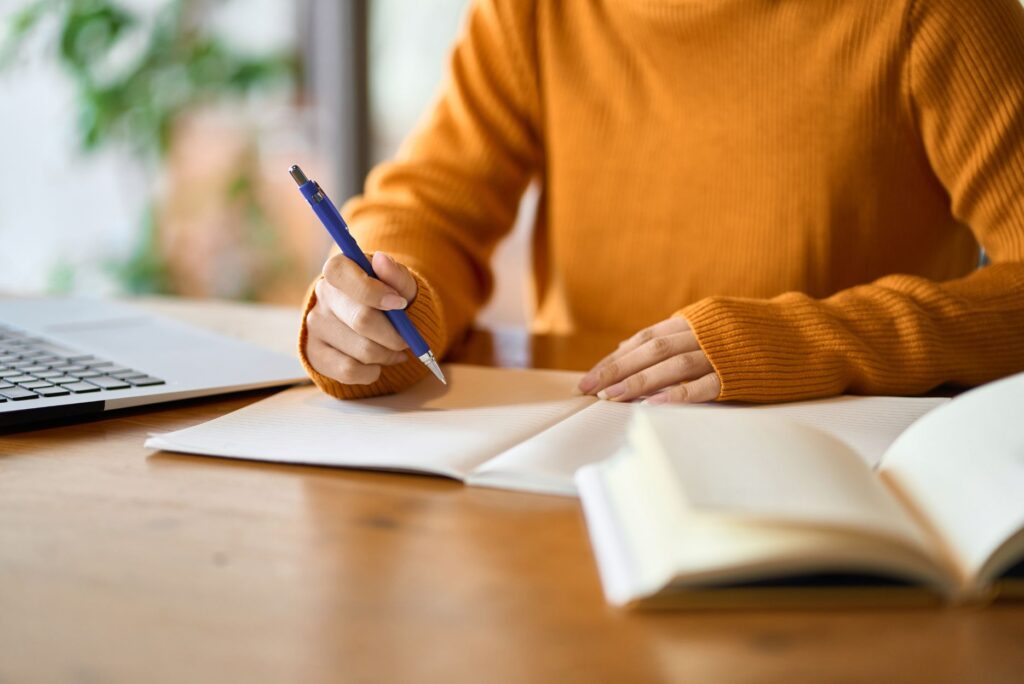
特定技能「介護」では在留期間が通算5年までに制限されており、その後の更新は認められません。
そこで、長期的な戦力として外国人材に働いてもらうためには、介護福祉士の国家資格取得を目指すことが有効です。
介護福祉士資格を取得すれば、在留期間の更新に上限がなくなり、継続して就労することが可能となります。
この資格を受験するには3年以上の実務経験と介護福祉士実務者研修の修了が必要となるため、1~2年目の早い段階から日本語力を高め、試験準備に取り組むことが合格への近道です。
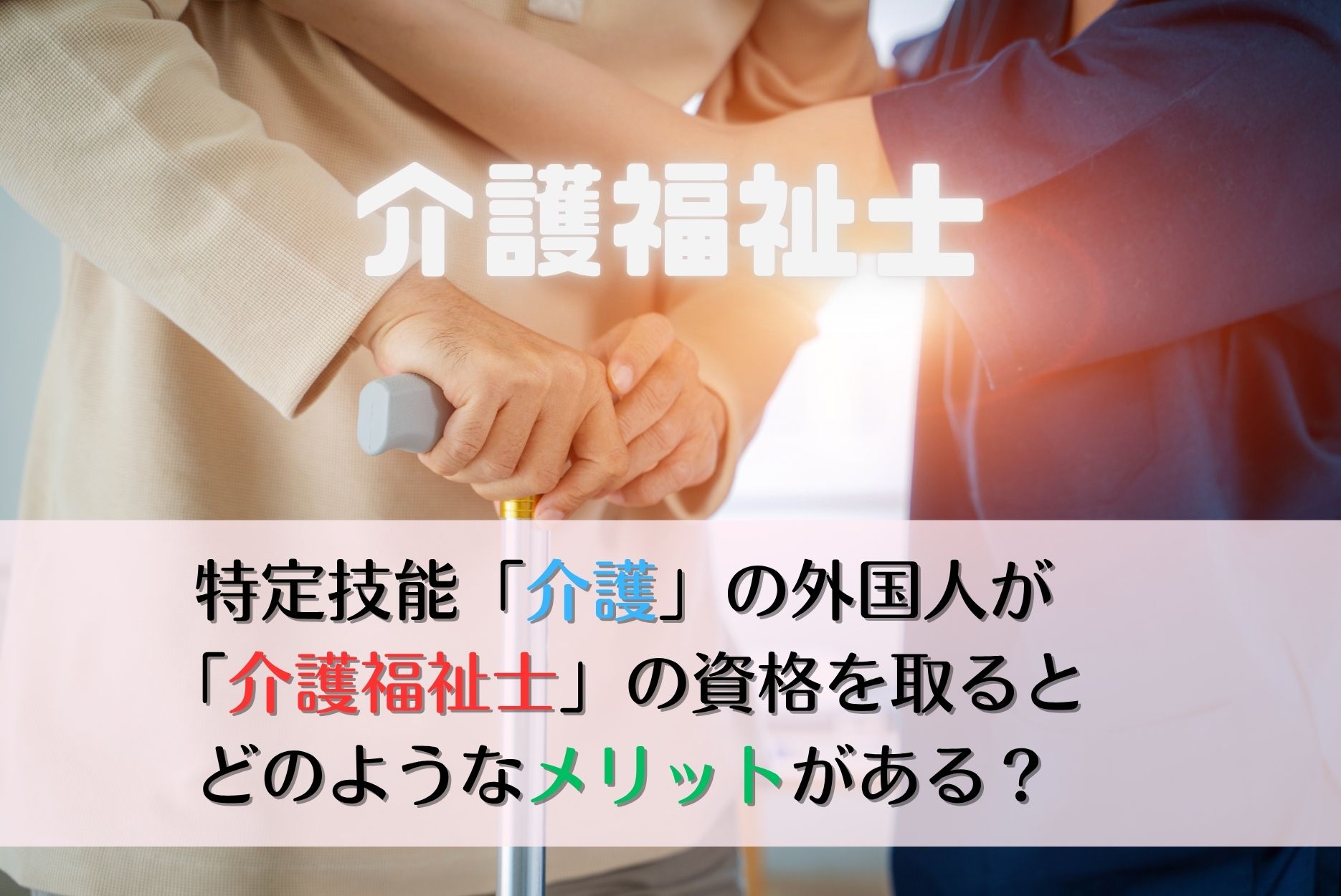
まとめ
本記事では、特定技能「介護」における雇用条件や受け入れ基準、在留資格取得の手順、雇用後の義務、さらに長期就労のための介護福祉士資格取得について解説しました。
制度の概要から実務上の注意点までを整理し、受け入れ企業と外国人双方が安心して就労できる環境づくりのポイントを示しました。
今後、外国人介護人材の採用や活用を検討している場合は、自社の受け入れ体制確保や協議会加入の準備を早めに行うことが重要です。
制度の要件や手続きは細かく定められているため、最新情報を確認しながら、信頼できる支援機関や専門家と連携し、計画的に採用プロセスを進めていきましょう。
監修者コメント
介護分野の特定技能1号外国人は、令和6年末時点で44,367人が日本で就労しています。
今後は介護福祉士の国家資格に合格し、在留資格「介護」へ移行する外国人の増加が見込まれ、全国で活躍する外国人介護職員のスキルが一層高度化していく流れが予想されます。
熟練した技能を持つ人材の受け入れは、日本社会にとって大きなメリットとなります。
長期就労を希望する外国人の方は、ぜひ介護福祉士の取得を目指して頑張ってください。
また、外国人材の介護福祉士取得は、受け入れ企業にとっても大きな利点となるため、資格取得を希望する外国人材には積極的な支援を行うことをおすすめします。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
出入国在留管理庁|特定技能運用要領
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html)
出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)
出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html)
出入国在留管理庁|特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html)
国際厚生事業団|介護分野における特定技能協議会
(URL:https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=81)
社会福祉振興・試験センター|介護福祉士国家試験
(URL:https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html)