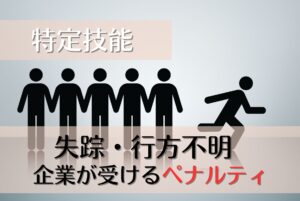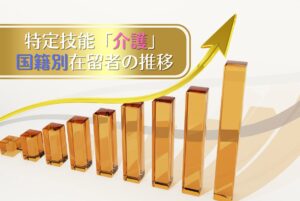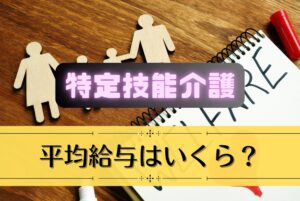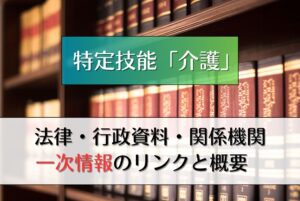監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹
介護現場では、特定技能「介護」の在留資格で働く外国人に対し、業務範囲や役割を正しく把握しないまま業務を割り当てている例が少なくありません。
制度改正や運用の見直しが繰り返される中で、「どの業務まで任せてよいのか」「知らないうちに不法就労に該当してしまわないか」と不安を抱える現場担当者も多いのが実情です。
本記事では、特定技能「介護」で従事できる主な業務や関連業務の範囲、不法就労と判断される具体的なケース、そして実務で注意すべき点を公的な資料をもとに分かりやすく整理します。
現場で必要な判断力や制度理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能「介護」の業務範囲

特定技能「介護」は、介護分野において即戦力となる外国人材を受け入れる制度として設けられています。
特定技能制度には、相当程度の知識や技能を持つ特定技能1号と、熟練技能を持つ特定技能2号が設けられていますが、介護分野においては特定技能1号のみ受け入れ対象とされています。
その理由として、介護福祉士の資格を取得した人には、より上位の在留資格「介護」がすでに用意されている点が挙げられます。
ここでは、特定技能「介護」で従事できる主な業務内容について解説していきます。

主な業務
特定技能「介護」で従事できる主な業務は、利用者の心身の状態に応じた入浴や食事、排せつ、整容、衣服の着替え、移動など、身体介護に関する一連のサービスです。
これらは、利用者の日常生活を支えるために身体へ直接関わる支援であり、介護の現場で中心的な役割を担います。
加えて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など、身体介護に付随する業務も主な業務の一部として認められています。
この身体介護は、利用者の生活の質向上や自立支援、重度化防止などを目的に、専門的な知識と技術を用いて提供されるものです。
関連業務
特定技能「介護」の関連業務としては、お知らせ等の掲示物の管理や物品の補充・在庫管理などが例示されています。
こうした業務は、同じ職場で働く日本人職員が通常行っている内容に付随して従事する形であれば認められています。
一方で、これらの関連業務だけを専任で担当することは制度上許容されていません。
したがって、関連業務はあくまで主な介護業務とあわせて行うことが必要です。
関連業務は全体の何割くらい認められるか
特定技能「介護」においては、関連業務だけに専念することは認められていないものの、どの程度まで従事できるかという具体的な割合は運用要領等で定められていません。
このため、業務の配分について明確な数字は存在しないことになりますが、技能実習「介護」の数字が参考になります。
技能実習では必須業務・関連業務・周辺業務の分類があり、関連業務の割合は全体の半分を超えないこと、周辺業務は3分の1以内とされています。
もし特定技能「介護」でも同じ感覚で現場運用を行うのであれば、主な業務に該当しない部分が全体の3分の1を超えない範囲を目安とするのが望ましいでしょう。
※特定技能の関連業務は、技能実習における周辺業務に近い概念であるため、全体の3分の1を目安として説明しています。
生活援助を行うことはできるか?
生活援助は利用者の身体に直接触れない支援で、掃除・洗濯・ゴミ出し・ベッドメイク・買い物・調理補助などが該当します。
特定技能「介護」の運用要領では、これらは身体介護に含まれず 「関連業務」 と位置づけられ、主な業務とはみなされません。
したがって生活援助を行う場合は、次のように身体介護を伴う訪問や入浴介助の流れの中で、付随的に実施する形が適切です。
- 利用者宅で食事介助を行った後に食器を洗う
- 入浴介助前後に衣類を準備・整頓する
一方で、生活援助だけを日常的に担当させる家事代行的配置になると、関連業務専従=業務範囲逸脱と判断され、不法就労となる可能性が生じます。
免許を取得すれば送迎業務に従事可能か?
特定技能「介護」の外国人が日本の運転免許を取得していたとしても、送迎スタッフとして専ら車両の運転に従事することは認められていません。
送迎は身体介護とは異なるため、メインの業務とすることはできず、あくまでも関連業務の一部と判断されます。
このため、送迎業務は主となる介護業務の合間に、他の日本人介護職員と同様の範囲で付随的に対応することができるに過ぎません。
外国人だけを送迎担当にすることや、ドライバー業務のみを行うことは制度の趣旨に反します。
現場では、日本人介護職員と同様に、必要な範囲で送迎に関わるよう運用されるべきでしょう。
特定技能「介護」で働ける場所

特定技能「介護」で就労できる現場は幅広く設定されており、たとえば障害児入所施設など児童福祉法の対象施設や、障害者支援施設など障害者総合支援法に基づく事業所が挙げられます。
加えて、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、訪問介護事業所など、老人福祉法や介護保険法に関連するサービス提供施設でも受け入れが可能です。
さらに、病院や診療所などの医療機関においても一定の条件下で勤務することが認められており、多様なニーズに応じた就労環境が整っています。
特定技能「介護」で従事できない業務

特定技能「介護」の在留資格で働く外国人であっても、施設内の業務内容によっては従事できないものがあり、これらの業務を行うと不法就労に該当する可能性があります。
ここでは、従事できない具体的な業務について解説します。
他の在留資格の業務に該当する行為
特定技能「介護」の資格で従事できる業務は介護業務に限られており、たとえ介護施設内の仕事であっても「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格の活動に該当する業務を行うことは認められていません。
具体的には、経営に関する管理職や役員の職務、事務職や営業担当などは対象外となり、これらの業務を担当すると不法就労と判断されるおそれがあります。
一方で、同じ介護分野の在留資格である「介護」や「技能実習(介護)」、あるいは「EPA介護福祉士(候補者)」については、従事可能な業務範囲が重複しており、多くの場合で業務内容が重なります。
医療行為
特定技能「介護」の外国人は、医療行為に携わることは法律で認められていません。
特に病院やクリニックでは、医師や看護師の管理下であっても実施できない作業が数多く存在するため、現場での役割分担に十分な注意が必要です。
もし医療行為を行った場合、医師法など医療関係の法令違反だけでなく、入管法にも抵触するリスクが生じます。
まとめ
本記事では、特定技能「介護」の業務範囲や関連業務、従事できる施設、従事できない業務の具体例について整理し、実務上注意すべきポイントを解説しました。身体介護や関連する支援業務は制度上認められていますが、業務範囲を逸脱すると不法就労のリスクがあるため、日々の業務分担や役割確認が重要となります。
受入れ機関や現場責任者の方は、業務内容や就労範囲を定期的に見直し、迷う場合は必ず専門家へ相談するようにしましょう。制度理解を深めることで、外国人スタッフが安心して働き続けられる環境づくりにつながります。
監修者コメント
不法就労を防ぐためには、在留資格ごとの業務範囲についての正しい理解が欠かせません。
ただし、実務上は明確な線引きがされていないケースも多く、制度の趣旨や公的資料の内容を踏まえて個別に判断する必要があります。
現場の裁量に委ねるのではなく、あらかじめ対応可能な業務を整理し、関係者間で共通認識を持つことが、適正な外国人雇用の第一歩となります。