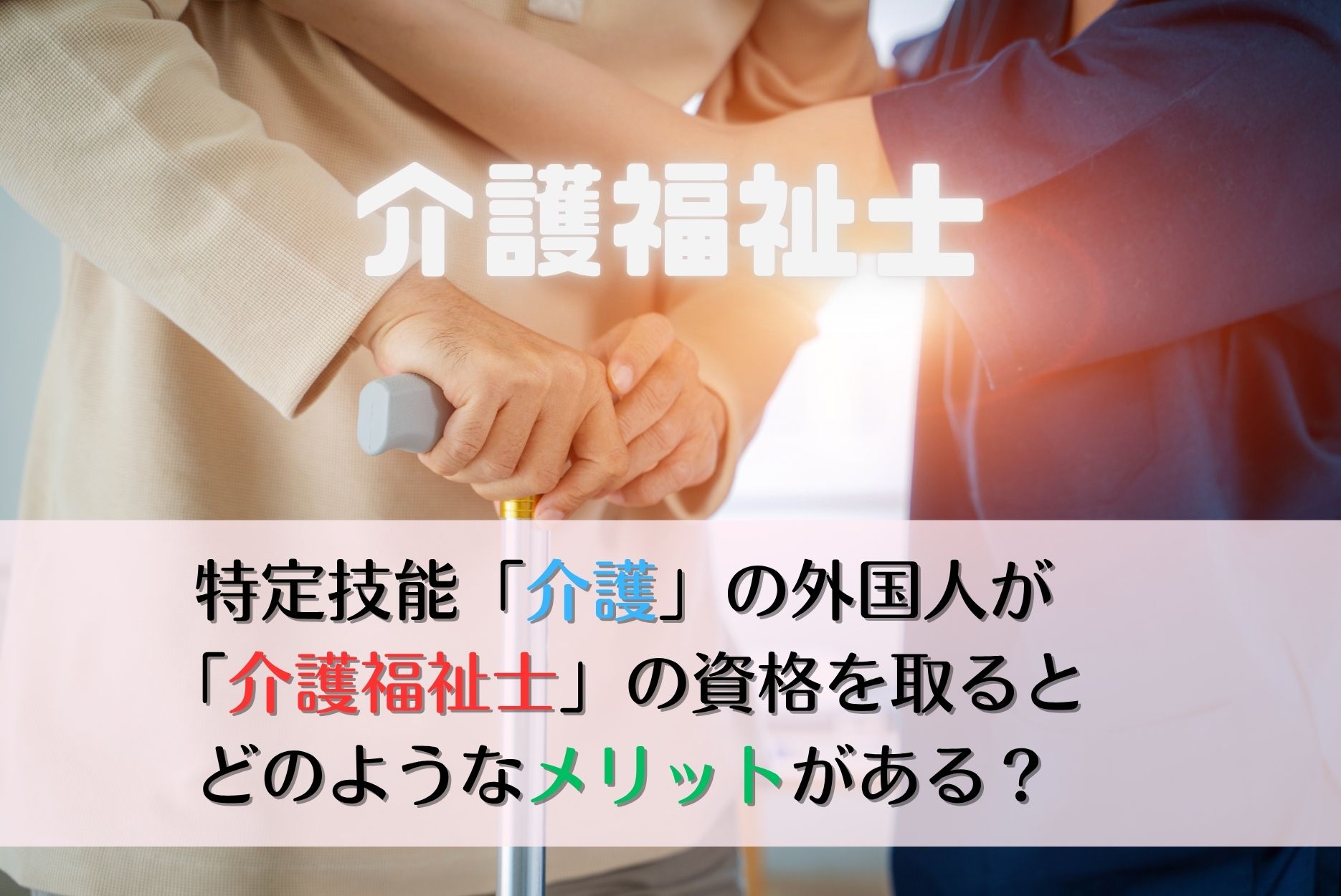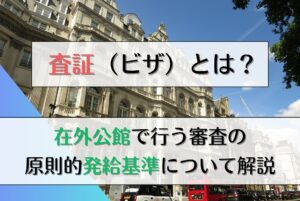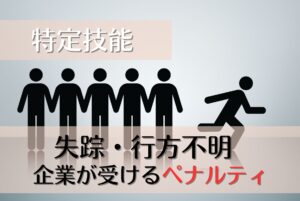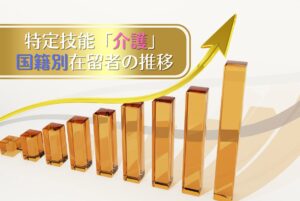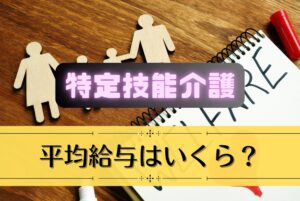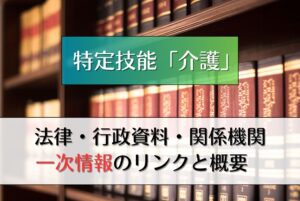監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹
介護業界の人手不足が深刻化する中、外国人材の受け入れに加え、その育成を視野に入れる企業が増加しています。特定技能で働く外国人が「介護福祉士」の資格を取得すると、どのような変化があるのか、また企業と本人の双方にどのような利点があるのかを考えることは重要です。
本記事では、特定技能外国人のキャリア形成の流れや、各在留資格の違いについて具体的に解説します。将来的に日本国内で不足が懸念される介護福祉士の人材確保につながる一助となれば幸いです。
特定技能「介護」と在留資格「介護」とは

特定技能「介護」と在留資格「介護」という二つの在留資格には、それぞれ異なる特徴があります。
ここでは、両者の基本的な仕組みや位置づけについて確認していきます。
一定水準の技能を持つ特定技能「介護」とは
特定技能「介護」は、介護業界の深刻な人材不足に対応するため、2019年に導入された新しい在留資格です。
この在留資格を取得するためには、「介護技能評価試験」「日本語能力試験N4相当以上」「介護日本語評価試験」の3つに合格する必要があります。
在留期間の上限は通算で5年と定められており、この在留資格で働く外国人は、入浴や食事、排せつといった身体介護を中心に仕事をします。ただし、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など日本人職員が通常行う業務にも付随的に従事可能です。
特定技能「介護」は一定水準の専門性と日本語能力を備え、即戦力として人手不足を補うために創設された在留資格であり、多様な現場で活躍の場が広がっています。

介護福祉士の在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、外国人が日本で介護福祉士として働く際に取得できる専門的な在留資格です。
この資格を得るためには、国家資格である「介護福祉士」の取得が必須条件となっています。
そのため、介護分野における知識や技術、日本語能力が高い人材が対象となります。認められる業務の範囲は広く、身体介護をはじめとする介護業務全般だけでなく、介護職員への指導や現場でのマネジメントも含まれます。
なお、在留期間に上限は設けられておらず、定められた審査基準に適合し続ける限り更新が可能です。
特定技能「介護」と在留資格「介護」の主な違い

特定技能「介護」と在留資格「介護」には、いくつかの重要な相違点があります。
在留期間の上限に関して、特定技能「介護」は通算で5年までの滞在が可能ですが、在留資格「介護」は基準を満たす限り何度でも更新でき、期間の制限なく日本で働き続けることが認められています。
また、訪問介護に従事する場合、特定技能「介護」では一定の実務経験や同行訪問など追加の条件が課されますが、在留資格「介護」はそのような要件を満たすことなく訪問サービスに従事できます。
加えて、永住許可申請に関しても、特定技能「介護」の在留期間は、就労年数のカウント対象外となりますが、在留資格「介護」の期間は5年の就労要件に含まれるため、永住申請の年数要件を満たすことが可能です。
| 特定技能「介護」と在留資格「介護」の違い | ||
| 在留資格 | 特定技能「介護」 | 在留資格「介護」 ※介護福祉士 |
| 在留年数 | 通算5年まで | 上限なし(更新は必要) |
| 訪問介護 | 原則1年以上の実務経験が必要 | 追加要件なし |
| 永住許可の年数要件 | カウントされない | カウントされる |
| 国家資格の有無 | なし | 介護福祉士 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)N4相当以上 | 要件なしのため人による |
介護福祉士の資格取得による外国人側のメリット

介護福祉士の資格を取得することで、外国人本人にはさまざまな利点が生まれます。この資格を得ることで、どのような新しい選択肢や可能性が広がるのか、順に見ていきましょう。
日本で5年以上働くことができる
特定技能「介護」では在留期間の通算上限が5年と定められているため、長期的に日本で働き続けたい方にとっては制約となります。
しかし、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」に移行すれば、在留期間の上限なく日本で就労を継続できるようになります。
特定技能外国人は介護福祉士の資格を取得することにより、働く場所やキャリアの幅が大きく広がるうえに、介護福祉士の資格は一度取得すれば失効することはありません。
そのため、たとえ母国に長期帰国をしたとしても再び日本に戻って働きたいと思ったときに、選択肢が残ることとなります。
将来永住許可を取得できる可能性がある
永住許可を目指す場合、日本に連続して10年以上在留していること、かつ、そのうち5年以上は就労系在留資格で滞在していることが必要となります。
特定技能や技能実習での在留期間は、10年以上の継続在留には含まれますが、5年以上の就労資格には該当しません。
このため、特定技能のままでは永住申請に必要な条件を満たすことができない点に注意が必要です。したがって、将来的に日本での永住を希望する場合は、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」に切り替えることが現実的な方法となります。
家族を日本に呼ぶことができる
特定技能「介護」の在留資格では、原則として家族の帯同が認められていません。このため、日本で働く間は単身での生活を余儀なくされることになります。
一方、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」に変更すると、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を取得できるようになります。
この仕組みにより、母国から家族を呼び寄せて一緒に生活したり、日本で新たに家族を持つことも現実的な選択肢となります。
長期的に日本で働きたい方にとって、家族との安定した生活を実現できる点は大きなメリットです。
給料が上がる可能性がある
多くの介護施設では、介護福祉士の資格取得者に対して資格手当を設けているため、介護福祉士を取得することで収入が上がるケースが多く見られます。
加えて、国はキャリアを積んだ介護福祉士の職場定着を推進しており、各種補助金を活用した給与改善の制度も導入されています。
こうした政策のもと、資格取得によって月給や賞与が増額されるチャンスが広がっています。
また、専門資格を持つことで職場内での役割や評価が高まり、将来的なキャリアアップにもつながる点が魅力です。
介護福祉士の資格取得による施設側のメリット

介護福祉士の資格を取得した外国人スタッフが増えることで、施設側にも多くの利点が生まれます。そこで、具体的にどのような場面で効果が現れるのか、以下で詳しく紹介します。
介護報酬の加算の算定に活用できる
介護福祉士を多く配置している施設では、サービス提供体制強化加算や介護職員等処遇改善加算などの各種加算の算定が可能となり、事業所の収益向上につながります。
特に、サービス提供体制強化加算は介護福祉士の割合や勤続年数を評価基準としているため、一定以上の有資格者がいることで加算額が増えやすい特徴があります。
さらに、介護職員等処遇改善加算も、経験豊富な介護福祉士を配置することで要件を満たしやすくなり、スタッフの処遇改善や安定した人材確保にも効果を発揮します。
人材の定着に繋がる
特定技能で入国した外国人労働者は、原則として5年間しか日本で就労できませんが、介護福祉士の資格を取得すれば在留期間に上限なく働き続けることが可能となります。
したがって、事業所が外国人スタッフの資格取得を積極的に支援することで、優秀な人材を長期的に確保できるという利点があります。
また、介護福祉士取得後は、永住許可の申請に必要な就労年数要件を満たせるようになるため、スタッフが永住を目指して勤務を継続しやすくなる点も見逃せません。
こうした流れの中で、職場として資格取得や永住サポートまで手厚く支援する姿勢は、働きやすい環境づくりと定着率の向上に寄与します。
訪問介護に従事するための厳しい要件がなくなる
特定技能「介護」の在留資格で訪問介護の現場に入る場合、原則として介護事業所で1年以上の実務経験や高い日本語能力(N2相当)など厳しい条件が課されます。
こうした要件は、訪問系サービスのみを提供する事業所にとっては、外国人介護人材の確保を難しくする大きな壁となっています。
しかし、介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ切り替えることで、日本人と同じ条件で訪問介護に従事できるようになります。
資格取得を通じて人材の幅広い活用が可能となり、施設側・本人双方にとって大きなメリットが生まれます。
まとめ
本記事では、特定技能「介護」と在留資格「介護」の主な違いや、介護福祉士資格の取得によるメリットを詳しく解説しました。特定技能では5年の在留上限や訪問介護への制約がありますが、介護福祉士を取得して在留資格を切り替えれば、永続的な就労や家族の帯同、給与アップ、加算算定による施設の経営安定といった多くの利点が得られることを紹介しました。
今後、外国人介護人材の受け入れや定着を考えている施設運営者や、長く日本で働きたいと希望する外国人本人にとって、介護福祉士資格の取得は重要な選択肢となります。要件や支援体制をしっかり確認した上で、早めにキャリア設計や受験準備に取り組むことをおすすめします。
監修者コメント
行政書士として、日々入管業務をする中でも介護業界での人手不足の声を聞く機会はとても多いです。
特に、経験豊富な介護人材の確保は、施設内での長期的な育成が前提となるため、簡単には解決できない課題です。
介護福祉士の資格と在留資格「介護」の制度は、日本で長く働きたい外国人の方と、人材の長期定着を求める受入れ側の双方にとって有益な仕組みです。資格取得には相応の努力が必要ですが、その先には大きな成長と活躍の場が待っています。今後も多くの方が介護の現場で力を発揮されることを願っています。