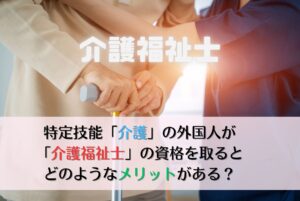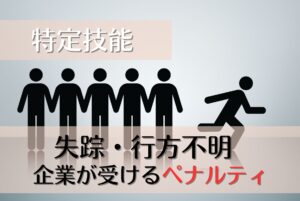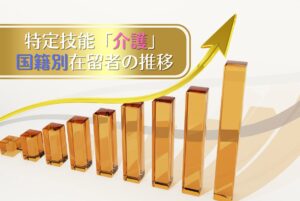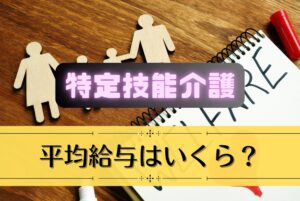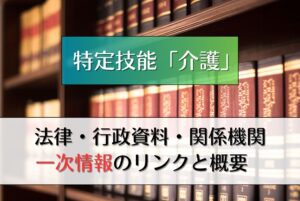監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹
介護・福祉分野では人手不足が深刻化しており、外国人材の受け入れは年々増加しています。しかし、すべての介護・福祉施設が外国人を受け入れられるわけではありません。この分野は複数の法律にまたがる制度で構成されており、どの施設が受け入れ対象となるのかを判断するには、各法律について横断的な理解が求められます。
この記事では、特定技能「介護」の外国人が勤務できる施設の種類や具体的な分類、受け入れに際しての注意点をわかりやすく解説します。各施設ごとの受け入れ可否や関連制度のポイントを整理し、現場の担当者が的確に判断できるよう、実務に役立つ情報をまとめました。
特定技能とは

特定技能とは、日本で深刻な人材不足が続く産業分野において、即戦力となる外国人材の雇用を認めるために設けられた在留資格です。
この制度は、相当程度の技能を持つ1号と、より高い熟練技能を求められる2号に分類されていますが、介護分野に関しては1号のみが認められています。
その理由として、介護分野には「介護福祉士」という国家資格を取得することで得られる在留資格「介護」が存在し、熟練技能に該当する働き方はこの資格によって担保されている点が挙げられます。したがって、介護分野での特定技能2号は制度上設けられていません。

特定技能「介護」の業務内容
特定技能「介護」の業務内容は、利用者の心身状態に応じた入浴や食事、排せつなど、日常生活に必要な動作を支援する身体介護が中心となります。
加えて、レクリエーションの実施やリハビリテーションの補助といった支援業務も求められ、現場では多岐にわたる役割を担うことになります。
関連業務としては、掲示物の管理や物品の補充といった、日本人の介護職員が通常行う補助的な業務にも付随的に従事することが認められています。ただし、これらの関連業務のみに専任的に従事することは認められておらず、主たる業務はあくまで身体介護などの直接的なケアが基本となります。
特定技能「介護」の対象施設の6つの分類

特定技能「介護」で受け入れが認められる施設には、明確な分類があります。
ここからは、それぞれの分類と特徴について詳しく解説していきますので、ご自身の状況に合わせて確認してください。
児童福祉法関係の施設・事業
児童福祉法は、すべての児童が健全な環境のもとで成長できるよう、保護や支援体制を整えることを目的としています。
この法律のもと、特定技能「介護」において受け入れが認められる施設は以下の通りです。
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
これらは子どもたちの多様なニーズに応じて、成長を支援するさまざまな取り組みを行う施設であり、特定技能の制度を活用して外国人介護人材を受け入れることが可能です。
障害者総合支援法関係の施設・事業
障害者総合支援法は、障害のある方が尊厳をもって自立した暮らしを送ることができるよう、生活や社会参加を支えるための総合的な支援体制を整えることを目的としています。
そのなかで特定技能「介護」の受け入れが認められる主な施設は以下の通りです。
・居宅介護
・重度訪問介護
・障害者支援施設
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助(グループホーム)
など
これらの施設やサービスでは、利用者一人ひとりの生活状況や希望に寄り添いながら、障害のある方々の生活の質向上に向けて、きめ細やかな支援が実施されています。
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
老人福祉法は、高齢者の健康や安定した生活を守るために、社会全体で必要な施策を講じることを目的としています。また、介護保険法は、介護を必要とする方々に対して保険給付を通じたサービス提供の仕組みを定めています。
対象となる主な施設や事業は以下の通りです。
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・指定通所リハビリテーション
・指定短期入所療養介護
・指定訪問介護
など
これらの施設は、多様な高齢者のニーズに応じた支援を提供し、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献しており、特定技能外国人の受け入れも活発に行われています。
生活保護法関係の施設
生活保護法は、生活が困難な方々に対し国が必要な援助を行い、最低限の生活水準を守るとともに自立の促進を目指す法律です。
そして、この法律に基づく主な対象施設には、日常生活の支援や社会復帰を目的とした救護施設と更生施設が含まれています。
これらの施設は、利用者が安心して暮らし、次のステップへ進むための環境を整えています。
その他の社会福祉施設等
その他の社会福祉施設等においても、特定技能「介護」の受け入れが可能な施設が複数存在します。
たとえば、地域福祉センターや隣保館デイサービス事業のほか、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、ハンセン病療養所といった専門性の高い施設が含まれています。
また、原子爆弾被爆者養護ホームや原子爆弾被爆者デイサービス事業、原子爆弾被爆者ショートステイ事業など、特定の支援を必要とする方を対象とした施設も特定技能外国人の受け入れが認められています。
このほか、労災特別介護施設なども対象です。
病院又は診療所
病院や診療所でも特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人を雇用することが可能です。
この場合、外国人材は、特定技能「介護」の在留資格を取得して「看護助手」や「看護補助者」として勤務することが一般的です。
担当する業務は、医療従事者の指導のもとで、患者の療養生活を支援する内容が中心となり、食事や清潔の保持、排泄、入浴、移動などの日常生活のサポートを担います。近年は、医療現場においても、特定技能外国人が活躍する機会が増加しています。
特定技能「介護」で在留許可を取るための要件

特定技能「介護」の在留資格取得には、複数の条件を満たすことが求められます。
ここでは必要となる技能や日本語能力、受け入れ可能人数など、審査基準に関するポイントを順に解説します。
外国人は3つの試験に合格しなければならない
外国人が特定技能「介護」で在留資格を取得するためには、3つの試験に合格することが求められます。具体的には、介護現場で必要とされる技能を問う「介護技能評価試験」、基礎的な日本語力を測る「日本語能力試験(N4相当以上)」、そして介護現場特有の用語理解を確認する「介護日本語評価試験」の合格が必要です。
・介護技能評価試験
・日本語能力試験(N4相当以上)
・介護日本語評価試験
訪問系介護サービスに従事する場合の追加要件
特定技能外国人が訪問系介護サービスに従事する場合、以下の追加要件が設けられています。
・実務経験1年以上または日本語能力試験N2相当以上
・利用者やその家族からの書面による同意を得ること
・巡回訪問等実施機関に必要な協力を行うこと
・介護職員初任者研修課程等の修了していること
・訪問介護に関して適切な講習を行うこと
・一定期間の同行訪問など適切なOJTを行うこと
・キャリアアップ計画を作成し巡回訪問等実施機関に提出すること
・ハラスメント対策のマニュアルや窓口を設置すること
・緊急事態に対処するためのマニュアル、連絡体制、情報共有、ICT活用などの整備
なお、「実務経験1年以上」の要件については、特定技能受入れ対象施設における介護業務の経験が必要となります。期間内において介護業務に従事した日数や労働時間については示されていないため、フルタイムでの就労経験が求められるわけではないと思われます。
受け入れ人数の制限
介護分野における特定技能外国人の受け入れ人数には、事業所単位で制限が設けられており、日本人等の常勤介護職員の総数を超えて特定技能外国人を受け入れることはできません。
ここでいう日本人「等」には、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」を持つ者、そして永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格者が含まれます。
一方で、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は人数算定の対象外とされており、また事務職員や介護以外の職種に従事する者はこの枠に含まれません。
まとめ
本記事では、特定技能「介護」制度の概要から対象となる施設の種類、業務内容、受け入れ人数の基準や必要な手続きまでを詳しく解説しました。各施設ごとに定められたルールや、訪問系サービスに従事する際の追加要件、在留許可取得に必要な試験や要件についても整理しています。
介護分野で外国人材の採用を検討している方は、まず自施設が対象施設に該当するか、受け入れ人数の上限や必要書類の整備状況を確認することが重要です。制度の内容を正確に把握し、適切な準備を進めることで、外国人スタッフが安心して活躍できる環境づくりにつながります。
監修者コメント
特定技能「介護」は業務区分が介護業務1種類のみとされており、従事できる内容は比較的シンプルです。
一方で、介護・福祉分野の法律が複数存在していることや、2025年4月に解禁された訪問介護の追加要件など、在留許可を得るためルールが複雑で、私自身も制度の把握に苦労することがよくあります。
制度に関して不明点がある場合は、行政書士や人材紹介会社などの専門機関に早めに相談することをおすすめします。