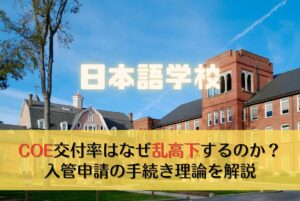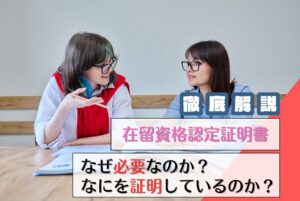技人国ビザで外国人を雇用する企業や、日本での就職を希望する外国人にとって、「審査で学歴と業務内容の関連性がどの程度求められるのか」は重要なポイントです。
実際、この関連性が不足していると不許可の原因となることがあり、不安を抱くのも当然といえます。
本記事では、技人国ビザの業務の内容や、必要とされる学歴・実務経験について整理します。
さらに、専攻分野と業務内容の関連性がどのように判断されるのかを解説し、大卒・専門卒・実務経験者といった立場ごとに分けて詳しく説明します。
技人国ビザの業務内容

技人国(ギジンコク)とは「技術・人文知識・国際業務」をまとめた呼称であり、これら3つの分類が一体となってひとつの在留資格を構成しています。
ここからは、各分類の具体的な業務内容について解説していきます。
技術
「技術」に分類される業務は、理学や工学などの理系分野で学んだ技術、知識を必要とする業務です。
この分類では、システム設計や製造工程の管理など、自然科学に基づく学問的な理論を実務に応用することが求められます。
代表的な職種としては以下のようなものが挙げられます。
- ITエンジニア
- ソフトウェア開発者
- プログラマー
- 機械工学系エンジニア
- 化学系エンジニア
- 技術系コンサルタント
- 建設系技術者
- 技術系カスタマーサービス など
人文知識
「人文知識」に分類される業務は、経済学や法学などの文系分野で培った専門知識を必要とする業務です。
この分類では、企業経営や組織運営を支える人文科学や社会科学などに関する幅広い知識が必要とされています。
代表的な職種としては以下が挙げられます。
- 営業職
- 総務、人事、経理など事務職
- 広報、マーケティング担当者
- 金融、財務、経営コンサルタント
- 顧客管理、カスタマーサービス など
国際業務
「国際業務」に該当するのは、外国文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務です。
この分類では、語学力や異文化対応力を活かして国際的な交流や取引を円滑に進める役割が期待されています。
主な職種には以下のようなものがあります。
- 翻訳
- 通訳
- 語学の指導
- 海外広報、宣伝
- 海外取引業務
- 服飾デザイン、商品開発
- 室内装飾デザイン、商品開発 など

技人国ビザ取得に必要な学歴・実務経験

技人国ビザを取得するためには、学歴や実務経験に関する基準が設けられています。
ここからは「技術・人文知識」と「国際業務」に分けて、それぞれで求められる学歴要件や実務経験の内容について解説します。
技術・人文知識に必要な学歴・実務経験
「技術・人文知識」に分類される業務を行うには、一定の学歴または実務経験が求められています。
許可を受けるためには、以下いずれかの要件を満たす必要があります。
- 業務内容に関連する科目を専攻して大学(短大含む)を卒業していること
- 業務内容に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了していること
- 10年以上の実務経験があること
なお、日本の専門学校を修了してこの在留資格を取得するには、専修学校専門課程を修了し「専門士」の称号を授与されている必要があります。
国際業務に必要な学歴・実務経験
「国際業務」に該当する仕事で許可を得るためには、学歴と実務経験について以下いずれかの要件に適合することが必要です。
具体的な要件は以下のとおりです。
- 大卒者(短大含む)が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は実務経験不要
- 大卒者(短大含む)が翻訳、通訳、語学指導以外の国際業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験があること
- 大卒者(短大含む)以外の者が国際業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験があること
なお、業務内容が「技術・人文知識」と「国際業務」の双方に該当する場合は「技術・人文知識」の基準が優先されます。
そのため、例えば大卒者が海外取引業務を担当する場合であっても、内容が「技術・人文知識」にも当てはまるのであれば、実務経験を問われることなく許可を得られる可能性があります。
IT系資格を持っている場合は学歴・実務経験が不要
「技術・人文知識」の分野に該当する業務であっても、法務大臣が告示で指定したIT関連資格を所持している場合は、通常必要とされる学歴や職務経験が免除されます。
この制度は、日本国内で取得した資格に限らず海外の資格も有効とされているため、海外から直接優秀なIT人材を採用する際にも活用できます。
特例が認められる主な国内資格は以下のとおりです。
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- エンベデッドシステムスペシャリスト試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 基本情報技術者試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
このように、特定の資格を保有していれば学歴や実務経験に関わらず在留資格を取得できるため、企業にとっても人材採用の幅を広げる手段となります。
日本国外のIT資格も有効なものが多数あります。
詳しくは以下をご確認ください。
参照:出入国在留管理庁|IT告示
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html)
技人国は学歴と業務内容の関連性が重要

技人国ビザを得るためには複数の基準がありますが、最も重要なのは「学歴と従事する業務との関連性」です。
ここからは、学歴の種類ごとにどの程度の関連性が求められるのか、その判断基準について整理して解説します。
大卒・短大卒は関連性が柔軟に判断される
大卒者や短大卒者については、入管庁は学歴と従事する業務との関連性を柔軟に判断する方針を示しています。
その理由は、大学教育が「幅広い知識を授け、知的、道徳的、応用的能力を養い、その成果を社会へ提供することで発展に寄与する」という教育機関としての目的があるためです。
このため、履修科目と就職先の業務が必ずしも一致していなくても許可される場合があります。
例えば、経済学部卒業者がITエンジニアとして働くケースや、工学部卒業者が営業職に従事するケースでも、技人国ビザを取得できる可能性があります。
専門学校卒(専門士)は相当程度の関連性が必要
専門学校(専修学校の専門課程)を修了した場合は、専攻分野と従事予定の業務が相当程度一致していることが求められます。
これは、専修学校が職業に必要な実務能力や生活に役立つ技能の習得を目的とする教育機関である点を踏まえた判断基準です。
そのため、専攻内容と職務内容の関連性が不十分とみなされる場合は、許可が得られない可能性があります。
実際の不許可事例としては、声優学科を修了した人がホテルのロビースタッフとして通訳・翻訳業務を申請したケースや、国際ビジネス学科を卒業した人が不動産販売の営業職を申請したケースなどが公表されています。
実務経験は科目履修や関連業務も含まれる
「技術・人文知識」に必要とされる10年の実務経験には、大学などで関連する科目を履修した期間も含まれるとされています。
加えて、必ずしも「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を10年行っている必要はなく、関連分野での従事歴も実務経験に算入されます。
「国際業務」に必要とされる3年の実務経験は、従事予定の業務と全く同一である必要はありませんが、内容的に関連性のある業務でなければなりません。
また、大学を卒業している場合には、翻訳や通訳、語学指導といった業務に従事する場合に限り、実務経験は求められません。
まとめ
この記事では、技人国ビザの業務の分類と、学歴や職務経験との関連性の判断基準について整理しました。
大卒や短大卒は柔軟に評価される一方、専門学校卒業者には高い関連性が求められる点、またIT資格や実務経験の扱いなどについても解説しました。
外国人材を採用しようとする企業や日本での就職を目指す外国人本人にとっては、自身の学歴や経験がどの程度業務と結びつくかを事前に理解することが不可欠です。
疑問点がある場合は、早めに専門家へ相談し、確実に申請を進められるよう準備を整えていくことをおすすめします。
監修者コメント
技人国ビザを申請する際には、業務内容と学歴との関連性を具体的に示すことが重要です。
これは許可を得やすくするだけでなく、3年や5年といった長期の在留期間が認められる可能性を高める効果もあります。
申請書の「活動内容詳細」欄はわずか2行しかないため、業務と学歴のつながりを十分に説明できる補足資料を作成し、添付して提出することが望ましいでしょう。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/)
出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf)
出入国在留管理庁|許可・不許可事例
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf)
出入国在留管理庁|IT告示
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html)