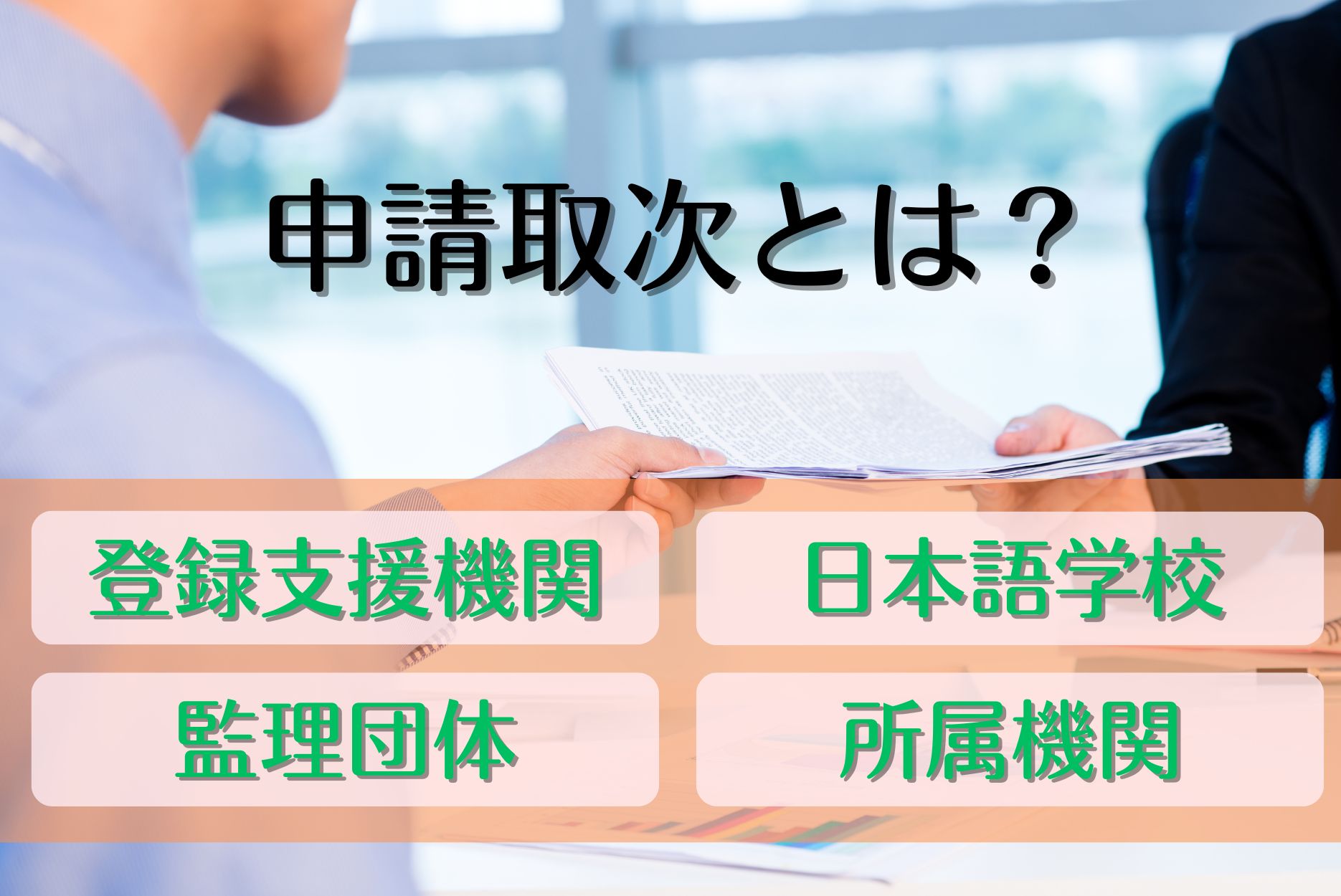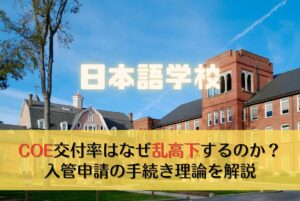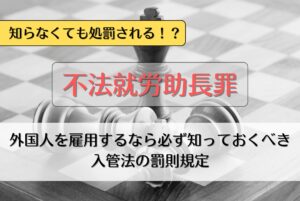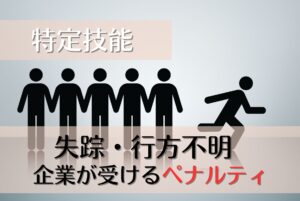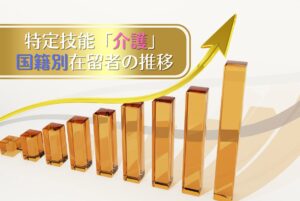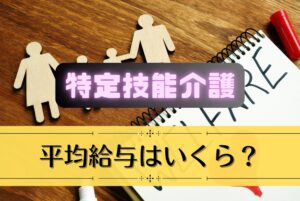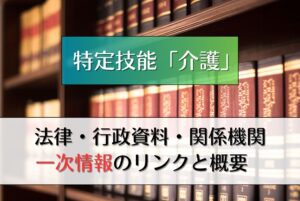外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格の取得が必要です。
入管法令には、外国人本人以外で在留資格申請書類の提出等を行うことができるのは、代理人と申請取次者であると定められています。
しかし、登録支援機関や日本語学校、監理団体に所属し、実際に申請取次業務に関わっていても、制度に対する理解が曖昧なまま業務を行っている方も少なくありません。
この記事では、申請取次の権限の範囲や申請取次を有償で行うために知っておくべき制度の詳細について、令和8年1月1日に施行される改正行政書士法の内容を踏まえて解説します。
申請取次とは
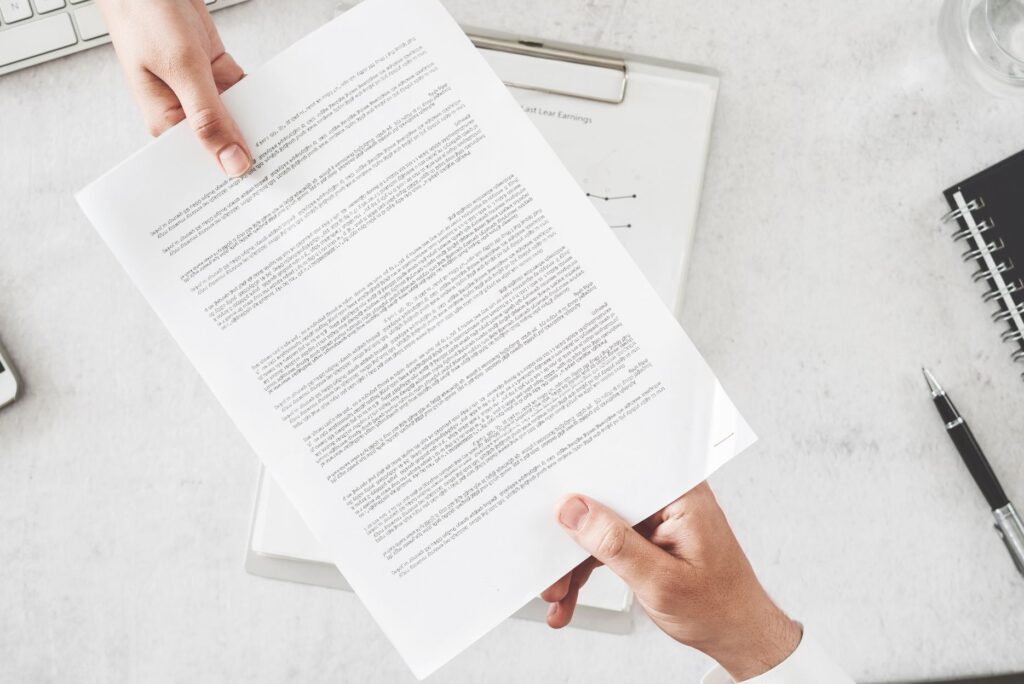
「申請取次」とは、「在留資格申請などの際に、申請人(外国人本人)に代わって申請書や資料などを提出する行為」のことで、入管法施行規則に規定されています。
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、この制度が創設された背景には、「申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和」や「申請人・届出人の負担軽減」などの目的があると説明しています。
本来、日本に滞在する外国人が行う在留資格関連の申請や届出の多くは、「本人出頭の原則」というルールがあり、原則的には、外国人本人が自ら出入国在留管理官署に出向いて手続きを行わなければなりません。
しかし、上述の理由や、やむを得ない事情などで本人による手続きができない場合などを考慮し、入管法上の代理人の規定や申請取次制度が存在しています。
本人出頭の原則
本人出頭の原則とは、在留資格関連の申請や届出の際に、原則として、外国人本人が自ら出入国在留管理官署に出頭して手続きを行わなければならないことを規定した入管法令上のルールのことです。
申請取次制度は、この出頭の義務を免除するための例外規定として存在しています。
申請取次により外国人の出頭義務が免除される手続きは以下の通りです。
なお、申請取次の範囲は、取次権限を取得した者の属性により異なるため、詳細は個別の「申請取次者の取次範囲」をご確認ください。
| 申請取次により外国人の出頭義務が免除される手続き | |
|---|---|
| 本人の出頭義務の根拠が入管法にある手続き | 住居地以外の記載事項の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、汚損等による在留カードの再交付申請、交換希望・再交付命令による在留カードの再交付申請、在留カード記載事項変更・更新・再交付で新たな在留カードを受領する行為、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の許可時に在留カードの交付を受ける行為 |
| 本人の出頭義務の根拠が法務省令(入管法施行規則)にある手続き | 在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更の申出、再入国許可申請 |
申請取次を行うことができる者
外国人に代わって申請取次を行うことができる者は、在留資格や行おうとする手続きの種類によりさまざまです。
弁護士または行政書士以外で申請取次を行うことを希望する場合、事前に地方出入国在留管理局長の承認を受け、「申請等取次者証明書」を取得する必要があります。
弁護士・行政書士の場合は、事前に地方出入国在留管理局長に対して届出を行い、「届出済み証明書」を取得する必要があります。
公益法人の職員、弁護士、行政書士は、在留資格の種別を問わず、入管法令上認められているすべての取次行為を行うことができます。
また、外国旅行業務を取り扱う旅行業者の職員は、自社で雇用する外国人の申請取次の場合を除き、在留資格の種別を問わず、旅行手続を依頼した外国人の「再入国許可申請」の取次のみを行うことができます。
主な在留資格の手続きの際に、申請取次を行うことができる者は以下の通りです。
| 在留資格 | 申請取次者 |
| 「経営・管理」「高度専門職一号(ハ)」など | 外国人が経営する機関の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
| 「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職一号(イ・ロ)」「企業内転勤」「介護」「技能」「特定技能二号」など | 外国人を雇用する機関の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
| 「研修」「留学」など | 外国人が研修または教育を受ける機関の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
| 「技能実習」 | 技能実習生の監理を行う団体の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
| 「特定技能一号」 | 外国人を雇用する機関の職員、支援委託を受けた登録支援機関の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
| 「家族滞在」など | 配偶者・子を扶養する外国人の受入れ機関の職員または公益法人の職員、弁護士、行政書士、旅行業者の職員 |
申請取次者としての承認手続
外国人を雇用する企業の職員が、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けるためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがない等信用できる者であること。また、承認を受けようとする者が所属する機関も同様に信用できる機関であること。
- 出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その経歴に照らし、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること。
①の要件は、申請取次を行おうとする者と所属する機関の両方に、過去に入管法違反や入国・在留管理上の問題がないことを求めるものです。
この規定には、「過去何年以内に~」などの年数の区切りがないため、一度でも入管法違反や入管手続き上の不正行為を行うと、以降一切の申請取次が認められなくなる可能性がありますので注意してください。
②の要件は、申請取次を行おうとする者が外国人の入国・在留手続の知識を有していることを求めるものですが、「出入国管理行政に関する研修会」を受講し修了証明書を提出することで要件を満たすものとされます。
研修会の内容は、実施する研修機関によりさまざまですが、概ね半日程度の研修を受講すれば、修了証明書の交付を受けることができます。
なお、新たに申請取次者の申し出をする際に、既に別の申請取次者が在籍している企業で、かつ、これまで適正に申請取次を行っている実績があり、既存の申請取次者が「必要な説明や指導を実施し、適正な申請手続きを行える者であることを保証する旨の説明書」を作成し、これを提出する場合、新たな申出者は「出入国管理行政に関する研修会」を受けることなく②の要件を満たすことが可能です。
参考:出入国在留管理庁|受入れ機関等の職員の方
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00256.html)
申請取次の承認手続きの提出書類一覧
外国人を受け入れる機関、技能実習生の監理団体、特定技能一号外国人の登録支援機関の職員が申請取次の承認手続きを行う際に、地方出入国在留管理局に提出する書類は以下の通りです。
- 申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表
- 申請等取次申出書
- 承認を受けようとする者の写真(3.0㎝×2.4㎝)2葉
- 承認を受けようとする者の経歴書及び在職証明書
- 在留カードの写し(取次者が外国人の場合)
- 出入国管理行政に関する研修会等の修了証明書などの疎明資料(原則発行から3年以内)
- 登記事項証明書または住民票の写し
- 本人確認資料の写し(郵送で申出する場合のみ)
- 簡易書留返信用封筒(郵送で審査結果の通知書等の交付を受ける場合のみ)
申請取次の承認手続きの書類提出先
申請取次の承認手続きの書類提出先は、申請取次の承認の申し出をする者が所属する企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(本局、支局、出張所)です。
なお、申請取次の承認審査は、本局または支局で実施されるため、郵送で手続きを行う場合は、直接本局や支局宛に書類を送付する方がスムーズです。
申請等取次者証明書の有効期間
申請等取次者証明書の有効期間は「3年」です。
ただし、申請等取次者証明書を取得する者が外国人である場合、有効期間は「3年」または「保有する在留資格の期間満了日」までのいずれか早い方になります。
申請等取次者証明書の更新手続きは、有効期間満了の2カ月前から申し出をすることが可能です。
申請取次者の取次範囲

申請取次の取次可能範囲は、取次資格を取得する者の属性により異なります。
以下に、主な企業・団体等に所属する職員が取次可能な手続きの範囲を解説します。
外国人を雇用する企業の職員
外国人を雇用する企業の職員は、入管法令上、申請取次が認められる手続きのうち、「在留資格認定証明書交付申請」を除くすべての手続きを取次ぐことが可能です。
なお、外国人を雇用する企業の職員は、在留資格認定証明書交付申請では、代理人として手続きを行います。
外国人を雇用する企業の職員が取次可能な在留資格の種類には特段の制限はありませんが、その企業に所属していない外国人の申請等を取次ぐことはできません。
在留資格の種類:制限なし
取次対象:その企業等で雇用する外国人
取次可能範囲:資格外活動許可申請、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請、在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出、在留カードの受領
特定技能1号登録支援機関
特定技能1号登録支援機関の職員は、外国人支援計画の実施の委託を受けている特定技能1号外国人の手続きに関して、入管法令上、申請取次が認められるすべての手続きを取次ぐことが可能です。
なお、特定技能1号登録支援機関が直接雇用する外国人従業員の手続きに関する取次範囲は、「外国人を雇用する企業の職員」の取次範囲と同様です。
在留資格の種類:「特定技能1号」
取次対象の外国人:外国人支援計画の実施の委託を受けている特定技能1号外国人
取次可能範囲:在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請、在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出、在留カードの受領
教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)
教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)の職員は、その教育機関で受け入れする外国人の「留学」の在留資格に関する手続きのうち、在留資格認定証明書交付申請を除き、入管法令上、申請取次が認められるすべての手続きを取次ぐことが可能です。
なお、教育機関の職員は、在留資格認定証明書交付申請では、代理人として手続きを行います。
教育機関が直接雇用する外国人従業員の手続きに関する取次範囲は、「外国人を雇用する企業の職員」の取次範囲と同様です。
在留資格の種類:「留学」
取次対象:その教育機関に在籍する留学生(卒業時の更新許可申請は取次不可)
取次可能範囲:資格外活動許可申請、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請、在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出、在留カードの受領
技能実習の監理団体
技能実習の監理団体の職員は、技能実習生として監理する外国人の「技能実習」の在留資格に関する手続きのうち、在留資格認定証明書交付申請と資格外活動許可申請を除き、入管法令上、申請取次が認められるすべての手続きを取次ぐことが可能です。
なお、技能実習の監理団体の職員は、在留資格認定証明書交付申請では、代理人として手続きを行います。
技能実習の監理団体が直接雇用する外国人従業員の手続きに関する取次範囲は、「外国人を雇用する企業の職員」の取次範囲と同様です。
在留資格の種類:「技能実習」
取次対象:その監理団体が監理する技能実習生
取次可能範囲:在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請、在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出、在留カードの受領
旅行業者の職員
旅行業者の職員は、入管法令上、申請取次が認められる手続きのうち、在留資格の種類を問わず、旅行手続きを依頼した外国人の「再入国許可申請」の取次ぎのみを行うことが可能です。
なお、旅行業者が直接雇用する外国人従業員の手続きに関する取次範囲は、「外国人を雇用する企業の職員」の取次範囲と同様です。
在留資格の種類:制限なし
取次対象:旅行手続きを依頼した外国人
取次可能範囲:再入国許可申請
公益法人の職員・弁護士・行政書士
公益法人の職員・弁護士・行政書士は、入管法令上、申請取次が認められるすべての手続きを取次ぐことが可能です。
また、在留資格の種類についても制限はありません。
在留資格の種類:制限なし
取次対象:制限なし
取次可能範囲:在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請、在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出、在留カードの受領
申請取次と代理申請の違い
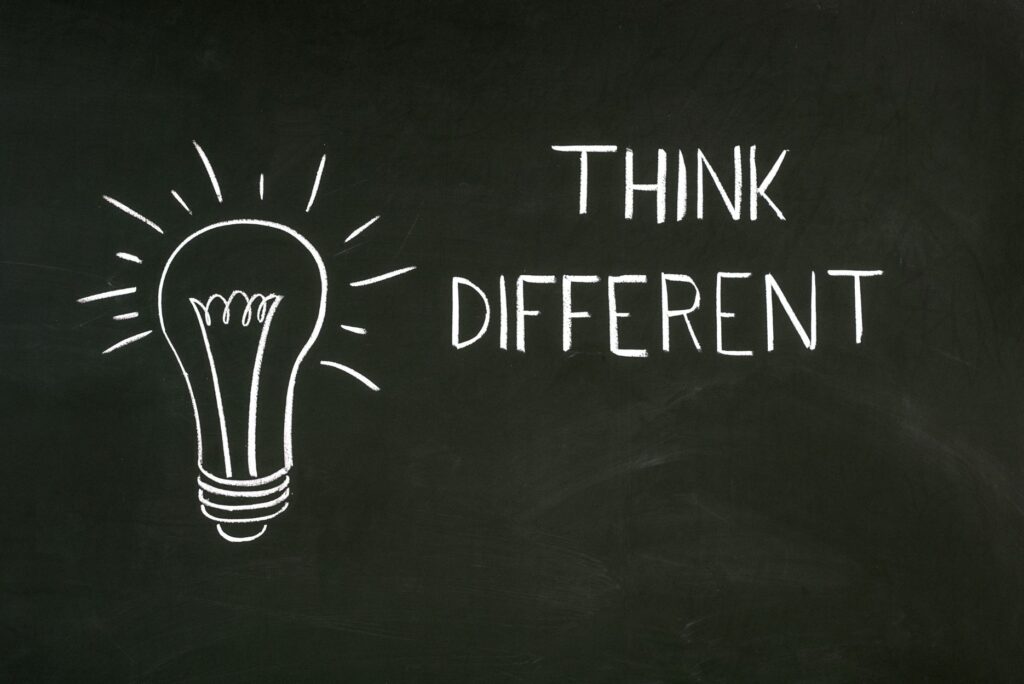
申請取次とは、「外国人本人または代理人から依頼を受けて申請書類の提出を行う行為」のことです。
外国人本人や代理人は、取次資格を持つ者の中から任意に取次者を選定して「書類の提出」を依頼することができますが、原則として申請取次者は「申請内容を変更する」「書類の作成者になる」といった申請に対する意思表示を伴う行為はできません。
申請取次者が取次を行う場合であっても、申請の主体は常に外国人本人または代理人です。
入管庁は「申請取次者は、申請書や資料の提出等の事実行為のみを行うことが認められている」と説明しています。
一方、代理申請とは、代理人が本人に代わって申請内容を決定したり、書類の作成・訂正または申請の取り下げなど、代理人が自ら意思表示を行い、その効果が本人に帰属する行為のことをいいます。
入管法には、任意に代理人を選定することが認められない手続きが多く存在します。
任意代理が制限されている手続きでは、入管法上、認められた代理人のみが代理行為を行うことができるほか、外国人本人または代理人から依頼を受けた申請取次者が代理行為に該当しない範囲で手続きをサポートすることができます。
事実行為とは
申請取次者は、外国人本人または代理人から依頼を受けて、申請書や資料の提出等の「事実行為」のみを行うことが認められています。
「事実行為」とは、「意思表示を伴わずに法律上の効果を発生させる行為」のことです。
例えば、申請取次者は、「外国人本人または代理人が作成した書類」を入管の窓口に「提出」することができます。
依頼を受けて書類を提出するだけでは、申請内容に「取次者の意思表示」は含まれませんが、申請の受理などの「法律上の効果」は発生します。このような行為を「事実行為」と言います。
入管申請における「事実行為」の例としては、「申請・届出書類の提出」「パスポートや在留カードの提示」「在留カードの受領」などが存在します。
これらの行為は、本来「本人出頭の原則」が適用されるため、他人が代わりに行うことはできませんが、外国人本人または代理人から依頼を受けた申請取次者は、例外的にこれらの事実行為を行うことができます。
取次範囲外の行為を行う権限

入管法施行規則には、申請取次者が外国人に代わって行うことができる行為として、「申請・届出書類の提出」「パスポートや在留カードの提示」「在留カードの受領」が挙げられています。
申請取次の権限のみでは、原則としてこれら3つの行為以外を行うことは認められませんが、申請取次者が所属機関の職員である場合など、所属機関の職員としての行為も同時に行うことができます。
以下に、申請取次者が取次範囲外の行為を行う場合について、「できること」「できないこと」を解説します。
外国人を雇用する企業の職員
外国人を雇用する企業の職員が申請取次者として、外国人に代わって在留資格申請を行う場合、申請取次者と所属機関の職員それぞれの立場で「できること」と「できないこと」は以下の通りです。
なお、外国人を雇用する企業の職員は、在留資格認定証明書交付申請において、代理人として書類作成や内容の訂正、申請の取り下げなど、意思表示を伴う行為を行うことが可能です。
| 権限の有無 | 行為の内容 |
|---|---|
| 申請取次者としてできること | ・申請書類を提出する ・窓口でパスポートや在留カードを提示する ・入管から在留カードを受領する |
| 所属機関の職員としてできること | ・所属機関作成用申請書類の作成者になる ・所属機関作成用申請書類に加除訂正する ・所属機関が発行する証明書類等を作成する |
| どちらの立場でもできないこと | ・申請人作成用申請書類の作成者になる ・申請人作成用申請書類に加除訂正する ・申請の取り下げの意思表示をする ・申請内容の変更の申し出をする ※在留資格認定証明書交付申請の場合は代理人として全て行うことができます |
| 立場に関係なくできること | ・申請書類の作成を補助する ・申請資料の収集を補助する ・申請資料を点検する ・申請資料を翻訳する ・申請内容の相談に応じる |
特定技能1号登録支援機関
特定技能1号外国人の支援委託を受けた登録支援機関の職員が申請取次者として、特定技能1号外国人に代わって在留資格申請を行う場合、申請取次者と登録支援機関の職員それぞれの立場で「できること」と「できないこと」は以下の通りです。
なお、登録支援機関は自ら特定技能1号外国人を雇用する場合を除き、代理人として特定技能1号の申請に携わることはできません。
| 権限の有無 | 行為の内容 |
|---|---|
| 申請取次者としてできること | ・申請書類を提出する ・窓口でパスポートや在留カードを提示する ・入管から在留カードを受領する |
| 登録支援機関の職員としてできること | 申請に関しては特になし |
| どちらの立場でもできないこと | ・申請人作成用申請書類の作成者になる ・申請人作成用申請書類に加除訂正する ・所属機関作成用申請書類の作成者になる ・所属機関作成用申請書類に加除訂正する ・所属機関が発行する証明書類等を作成する ・申請の取り下げの意思表示をする ・申請内容の変更の申し出をする |
| 立場に関係なくできること | ・申請書類の作成を補助する ・申請資料の収集を補助する ・申請資料を点検する ・申請資料を翻訳する ・申請内容の相談に応じる |
教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)
留学生を受け入れる教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)の職員が申請取次者として、留学生に代わって在留資格「留学」に関する申請を行う場合、申請取次者と教育機関の職員それぞれの立場で「できること」と「できないこと」は以下の通りです。
なお、留学生を受け入れる教育機関の職員は、在留資格認定証明書交付申請において、代理人として書類作成や内容の訂正、申請の取り下げなど、意思表示を伴う行為を行うことが可能です。
| 権限の有無 | 行為の内容 |
|---|---|
| 申請取次者としてできること | ・申請書類を提出する ・窓口でパスポートや在留カードを提示する ・入管から在留カードを受領する |
| 教育機関の職員としてできること | ・所属機関作成用申請書類の作成者になる ・所属機関作成用申請書類に加除訂正する ・教育機関が発行する証明書類等を作成する |
| どちらの立場でもできないこと | ・申請人作成用申請書類の作成者になる ・申請人作成用申請書類に加除訂正する ・申請の取り下げの意思表示をする ・申請内容の変更の申し出をする ※在留資格認定証明書交付申請の場合は代理人として全て行うことができます |
| 立場に関係なくできること | ・申請書類の作成を補助する ・申請資料の収集を補助する ・申請資料を点検する ・申請資料を翻訳する ・申請内容の相談に応じる |
技能実習の監理団体
技能実習の監理団体の職員が申請取次者として、技能実習生に代わって在留資格「技能実習」に関する申請を行う場合、申請取次者と監理団体の職員それぞれの立場で「できること」「できないこと」は以下の通りです。
なお、技能実習の監理団体の職員は、団体監理型技能実習の在留資格認定証明書交付申請において、代理人として書類作成や内容の訂正、申請の取り下げなど、意思表示を伴う行為を行うことが可能です。
| 権限の有無 | 行為の内容 |
|---|---|
| 申請取次者としてできること | ・申請書類を提出する ・窓口でパスポートや在留カードを提示する ・入管から在留カードを受領する |
| 監理団体の職員としてできること | ・所属機関作成用申請書類の作成者になる ・所属機関作成用申請書類に加除訂正する ・監理団体が発行する証明書類等を作成する ・技能実習計画作成・変更等の指導 |
| どちらの立場でもできないこと | ・申請人作成用申請書類の作成者になる ・申請人作成用申請書類に加除訂正する ・申請の取り下げの意思表示をする ・申請内容の変更の申し出をする ※在留資格認定証明書交付申請の場合は代理人として全て行うことができます |
| 立場に関係なくできること | ・申請書類の作成を補助する ・申請資料の収集を補助する ・申請資料を点検する ・申請資料を翻訳する ・申請内容の相談に応じる |
申請取次を有償で実施する方法

「申請取次」とは、「在留資格申請などの際に、申請人(外国人本人)に代わって申請書や資料などを提出する行為」のことです。
この行為は事実行為であるため、入管法上の代理行為には該当せず、また行政書士法など入管法以外の法律で規制される行為でもないため、有償で業として取次を行っても問題ありません。
ただし、在留資格申請全体を形成する行為の中には、有償で業として行うと行政書士法違反となる「官公署に提出する書類の作成」という行為が含まれるため、申請取次を有償で行う場合は、取次権限の範囲を超えないように注意して手続きを行う必要があります。
以下に申請取次を有償で実施している公益法人の事例を紹介します。
公益法人が有償で行う申請取次
入管協会は、出入国在留管理業務に関する研修会の実施や書籍の発刊などを行っている公益財団法人です。
入管協会は、在留資格や申請の種類を問わず、入管法令上認められているすべての申請取次を行う権限を有しており、申請書類の点検および取次業務を有償で行っています。
ただし、公益法人の職員は、有償で申請書類の作成や訂正等を行うことができないため、入管協会に依頼できる業務の範囲は「申請書類の点検」と「申請取次」のみです。
また、同じく公益財団法人である国際人材協力機構(JITCO)は、技能実習や特定技能の申請取次業務を有償で行っています。
JITCOが行う業務のサービス範囲も「申請書類の点検」と「申請取次」のみで、書類作成やその他の意思表示を伴う行為は一切行っていません。
これらの公益法人が有償で行う入管申請に関連する業務の範囲は、登録支援機関や教育機関、監理団体など多くの外国人の在留資格申請に関わる企業・団体にとって非常に参考になる情報です。
「申請書類の点検」と「申請取次」だけを行う場合は、たとえ有償で依頼を受けたとしても行政書士法に違反しないと公益法人が判断していることを示しています。
法令遵守の意識が強い公益法人の判断を参考にするのであれば、例えば登録支援機関の職員が、申請取次者として支援委託を受けた特定技能1号外国人の在留資格申請に関わる場合、登録支援機関として有償で特定技能1号の支援業務を行うことに加えて、申請取次者として有償で「申請書類の点検」と「申請取次」を行っても行政書士法には違反しないと解釈することができます。
ただし、書類作成も行う場合は、「作成」と「点検・取次」を明確に分離することができ、かつ、書類作成は無償で行っていることを客観的に説明できない場合、行政書士法違反となる可能性があるため注意が必要です。
参考:公益財団法人 入管協会|事前点検(申請取次)
(URL:https://www.nyukan-kyokai.or.jp/pages/30/)
参考:公益財団法人 国際人材協力機構|JITCOの支援サービス
(URL:https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html)
行政書士法改正により「書類作成」と「点検・取次」の分離が難しくなる
令和8年1月1日より改正行政書士法が施行され、入管申請においても大きな影響があると言われています。
入管分野に影響する主な改正点は、「行政書士または行政書士法人でない者が行ってはならない行為」の明確化です。
以下は、行政書士法第19条の新旧比較表です。
| 改正前 | 改正後 |
| (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 | (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。 |
表内の「第一条の二に規定する業務」「第一条の三に規定する業務」とは「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)を作成すること」です。
例えば、技能実習の監理団体が「会費」「監理費」などを得て、あるいは特定技能1号の登録支援機関が「支援委託費」を得て、入管申請書類の作成部分を無償サービスとして提供する行為は、実質的に「行政書士法に違反して有償で書類作成を行った」と判断される可能性があります。
また、オンライン申請についても、入管庁は「弁護士または行政書士以外の方が有償で在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反または行政書士法違反となる可能性がある」という注意喚起を出しているため、法律違反にならないよう注意が必要です。
この法改正以降は、以下いずれかの方法で入管申請の手続きを進める必要性がより高まると考えられます。
- 外国人本人または受入れ企業が自ら書類を作成し申請する
- 外国人本人または受入れ企業が書類を作成し、申請取次者が点検・取次する
- 弁護士または行政書士が書類を作成し、申請取次する
- 弁護士または行政書士が書類を作成し、申請取次者が取次する
これらのうち、申請取次者が申請取次をするのは②と④ですが、どちらも有償で行っても問題ありません。
また、外国人本人または受入れ企業が書類を作成する場合に、申請取次者が書類作成の助言を行うこと自体は問題ありません。
日本行政書士会連合会|「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について
(URL:https://www.gyosei.or.jp/news/20250606)
総務省|行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)
(URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/001014708.pdf)
参考:出入国在留管理庁|在留申請オンラインシステムの利用申出を行う皆様へ
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001351567.pdf)
申請取次の有償化は行政書士との協業が有効
技能実習の監理団体や特定技能1号の登録支援機関が入管申請の負担を軽減するには、行政書士との協業が有効です。
行政書士は、申請全体の代行だけでなく「書類作成」の部分のみを切り離して請け負うことも可能です。
書類作成を行政書士が担当し、申請取次や資料の収集などの事実行為を取次者が行うことで、いずれも法令を遵守しながら、負担の大きい申請業務を有償化できます。
きさらぎ行政書士事務所では、Web面談やオンライン申請に対応しているため、全国どこからでもご依頼いただけます。
コンプライアンスの強化に取り組む際には、行政書士の活用も一つの選択肢です。
複数案件の同時ご依頼や継続的なお取引についても、個別にお見積もりいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
この記事では、申請取次の権限の範囲や有償で取次を行う方法などを解説しました。
本来、申請取次とは、資料の提出などの事実行為のみを行うものであるため、大きな労力が必要な作業ではありません。
しかし、実情としては、申請取次者が申請全体の指揮を執るなど負担のかかる役割を担っていることも多くあり、業として有償で取次を行いたいと感じるのは自然なことです。
入管申請は法律事務であるため、有償で行う場合は弁護士法や行政書士法などを考慮する必要があります。
申請取次者として行う業務が事実行為のみであり、書類作成を伴わなければ、どちらの法的リスクも回避できるため、部分的に専門家を活用するなどして無理のない範囲で取次業務を行うことをおすすめします。