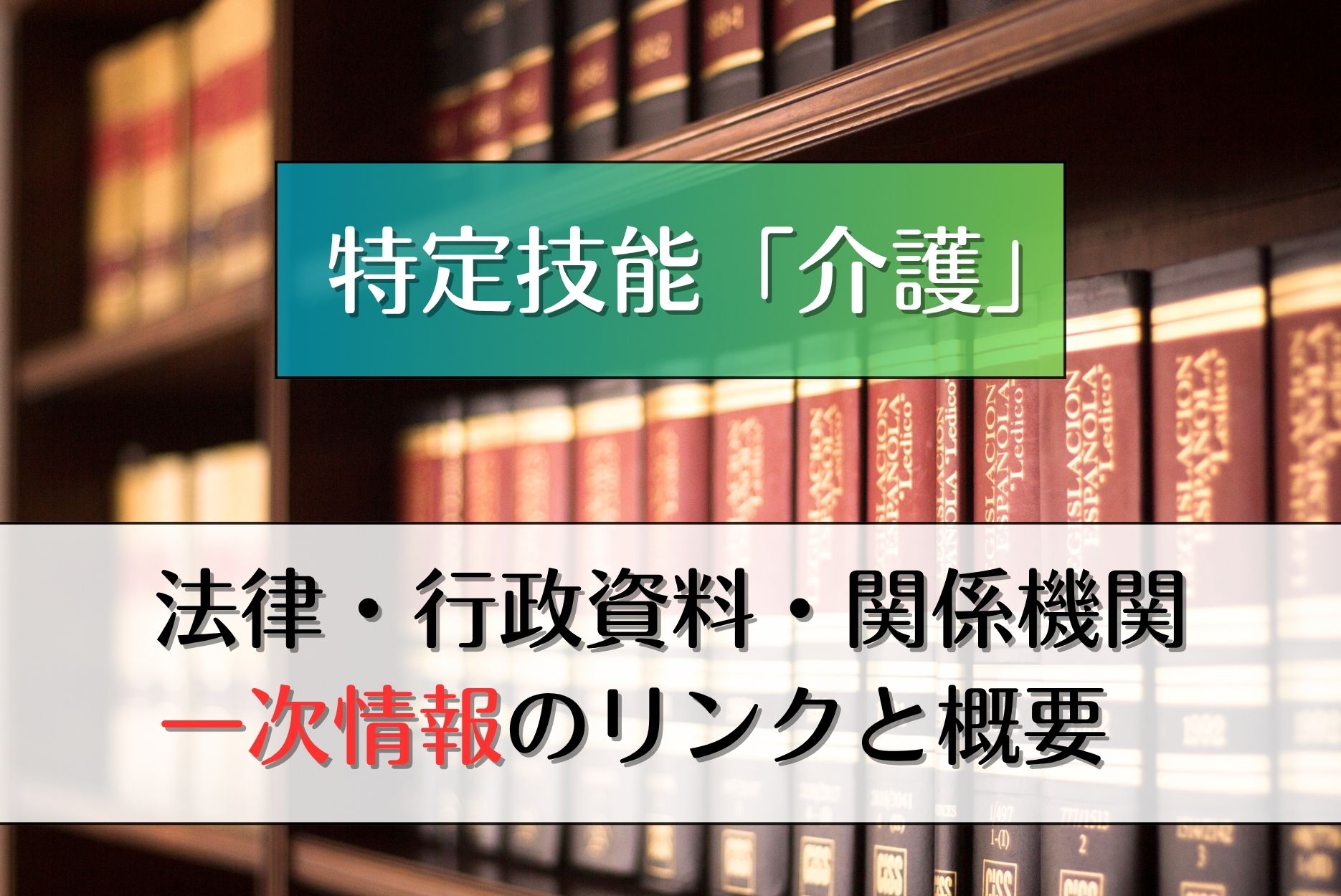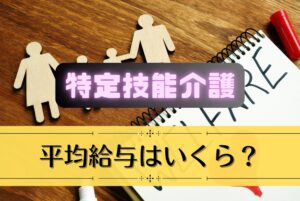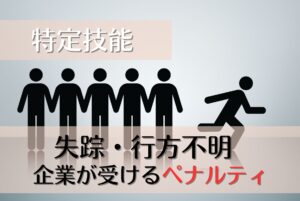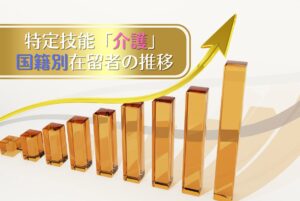監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹
入管制度は、法律・政省令・告示・ガイドライン・他国との協定文書など、異なる階層の公的資料によって成り立っています。
そのため、全体像をつかむには幅広い資料に目を通す必要があり、「どこに正しい情報があるのか分からない」とお困りの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、複数の行政機関や関連団体にまたがる特定技能「介護」に関する一次情報のURLと、各資料のポイントをわかりやすくまとめています。
介護分野で外国人の採用を検討している施設担当者の方をはじめ、在留手続きに悩む外国人ご本人、また外国人材の支援に携わる登録支援機関や教育機関の担当者の方にとって、有用な情報源となるはずです。
特定技能「介護」の制度に関する一次資料

ここでは、介護分野における特定技能制度の概要に関する一次資料の内容とURLを紹介します。
特定技能外国人の受け入れに関して、介護分野で紹介事業や登録支援機関を運営するうえで、知っておくべき重要な情報が多く含まれています。

分野別運用方針
関係閣僚会議で閣議決定された基本方針に基づき、所管省庁の大臣が連名で分野別運用方針を定めます。
介護分野の運用方針では、「介護分野の人手不足の状況」「特定技能外国人の受け入れ見込み数」「求められる技能および日本語能力の水準」「特定技能『介護』における業務内容」などが示されています。
分野別運用方針は、資料の分量自体は多くありませんが、各分野における人手不足の状況などが簡潔にまとめられており、一度は目を通しておきたい重要な資料です。
出入国在留管理庁|閣議決定等
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html)
分野別運用要領
分野別運用要領は、入管法令や特定技能基準省令、分野別方針などを踏まえ、各分野における特定技能制度をどのように運用していくかを定めた重要な資料です。
介護分野の運用要領には、特定技能「介護」に関連する各種法令について、関係省庁による具体的な解釈が示されています。
分野別運用要領は、特定技能の各分野における固有のルールを把握するための、最も重要な資料のひとつです。
介護分野の特定技能制度を深く理解したい方にとっては、まず最初に読むべき資料と言えるでしょう。
出入国在留管理庁|特定技能運用要領
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html)
訪問介護の固有要件
特定技能の在留資格で訪問系介護サービスに従事するためには、多くの追加要件を満たす必要があります。
原則として1年以上の就労経験(※ただし、JLPT N2相当の場合は例外あり)に加え、キャリアアップ計画の策定、同行訪問の実施、ハラスメント防止対策の整備など、さまざまな追加ルールが定められています。
令和7年4月に、特定技能外国人による訪問介護業務への従事が解禁されましたが、要件が比較的厳しく設定されているため、令和7年7月時点では受け入れがあまり進んでいないのが現状です。
ただし、今後は制度の緩和が検討される可能性も十分にあるため、最新の動向に注意を払う必要があります。
厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html)
特定技能「介護」の在留許可申請に関する一次資料

特定技能の在留資格申請における基本的な審査基準は、すべての産業分野で共通ですが、分野ごとに固有の要件があるため、提出書類の一部が異なる場合があります。
ここからは、在留許可を得るために必要となる各種手続きについて、詳しく解説していきます。
入管申請
出入国在留管理局で行う在留許可申請には、「在留資格認定証明書交付申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」などがあります。
これらの申請に必要な提出書類の根拠規定は、入管法や入管法施行規則、さらには運用要領など複数の法令・規則等にまたがっていますが、出入国在留管理庁のウェブサイトには、提出すべき資料の一覧が整理されています。
特定技能の申請に必要な書類は多岐にわたりますが、制度改正が頻繁に行われているため、申請手続きを行う際には、必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新の提出書類を確認するようにしましょう。
入管申請では、たとえ誤った書類を提出しても形式的な要件を満たしていれば審査が開始されてしまうため、正確な情報を理解せずに申請を行うことで、思わぬ不利益を被る可能性があります。
また、提出した申請書類は原則として返却されないため、書類作成時には必ず控えを手元に残しておくことが重要です。
出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)
協議会加入申請
特定技能外国人を受け入れる事業者は、受け入れに先立ち、必ず協議会へ加入する必要があります。
介護分野における協議会は、厚生労働省から委任を受けた「公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)」が運営を担っています。
なお、介護分野においては、登録支援機関に協議会への加入義務は課されていません。
特定技能外国人を雇用する事業者は、入管で在留資格の申請を行う前に、協議会への入会を済ませておく必要があります。
手続きにはおおよそ2週間程度かかるため、余裕を持って加入申請を行いましょう。
なお、入管申請時に提出が求められる「協議会入会証明書」には有効期間があり、初回は1年間、有効期間の更新後は4年間と定められています。
厚生労働省|介護分野における特定技能協議会
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html#link3)
定期届出・随時届出
特定技能外国人を雇用する企業は、年に一度、入管庁に対して定期届出をしなければなりません。
また、雇用契約の変更や受け入れの停止など、さまざまな場面で随時届出を行う義務を負うこととなります。
届出義務違反には罰則が科される可能性がありますが、届出書類の作成は制度上、登録支援機関に委任することはできません。
また、登録支援機関には届出業務を支援する義務もないため、外国人を受け入れる雇用主自身が、制度の内容を正しく理解しておく必要があります。
出入国在留管理庁|特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html)
介護の日本語試験に関係する一次資料

特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、所定の日本語能力基準を満たす必要があります。
具体的には、「介護日本語評価試験」に合格し、かつ「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかに合格していることが求められます。
ここでは、それぞれの試験の概要と公式サイトのリンクを紹介します。
介護日本語評価試験
介護日本語評価試験は、介護分野の特定技能に従事するうえで必要とされる日本語能力を満たしているかどうかを確認するための試験です。
試験はCBT方式で実施されており、受験料は受験する国によって異なります。
この試験に不合格となった場合、45日間は再受験できないため注意が必要です。
なお、技能実習「介護職種・作業」の2号良好修了者が特定技能へ移行する場合は、介護日本語評価試験の受験が免除されます。
プロメトリック|介護技能評価試験、介護日本語評価試験
(URL:https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/2)
日本語能力試験(JLPT)N4
日本語能力試験(JLPT)N4は、「基本的な日本語を理解できるかどうか」を判定するための試験です。
試験は毎年7月と12月の年2回実施され、国内外の多くの都市で開催されています。
日本国内では、全47都道府県で受験することが可能です。
技能実習2号を良好に修了した外国人については、修了した職種・作業の種別にかかわらず、JLPT(N4)またはJFT-Basicの試験の合格が免除されます。
JLPT|日本語能力試験JLPT
(URL:https://www.jlpt.jp/)
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、就労を目的として日本に入国する外国人の日本語能力を測定する試験です。
「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」が備わっているかどうかを判定することを目的としています。
試験はCBT方式で実施され、結果は試験終了と同時に通知されます。
この試験は、JLPT(日本語能力試験)と比較すると実施される都市は限られていますが、試験の実施頻度は多く設定されています。
また、一定期間内で任意の日程を選んで受験できるCBT方式の試験であるため、スケジュールを柔軟に調整しやすいというメリットもあります。
JFT-Basic|JFT-Basicとは
(URL:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/about/index.html)
介護の技能試験に関係する一次資料

特定技能「介護」の在留許可を取得するためには、介護技能評価試験に合格することが必要です。
ここでは、介護分野における技能試験の概要と、関連する一次情報のリンクを紹介します。
介護技能評価試験
介護技能評価試験は、特定技能「介護」の在留資格を取得するために必要な技能水準を確認する試験です。
介護業務に関する知識や技術を問う内容で、全45問が出題されます。
試験はCBT方式で実施され、国内外の会場で受験することができます。
技能実習「介護職種・作業」の2号良好修了者が特定技能へ移行する場合は、介護技能評価試験の受験が免除されます。
プロメトリック|介護技能評価試験、介護日本語評価試験
(URL:https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/2)
特定技能のすべての分野で共通の一次資料

特定技能制度は、複数の法令に基づいて運用されています。
ここでは、制度全体に関係する主要な法令を紹介します。
登録支援機関や教育機関の担当者をはじめ、入管法についてより深く学びたい方は、ぜひ参考にしてください。
入管法令
入管法令は、特定技能をはじめとする外国人受け入れ制度の根幹を規定する、非常に重要なルールです。
申請手続や在留管理において問題が生じた際には、そのリスクの大きさや適切な対処法を判断するためにも、制度の根拠となる法律の理解が欠かせません。
この章では、各法令の規定内容や、それぞれの重要度について解説します。
出入国管理及び難民認定法(入管法)
入管法は、外国人の入国・在留資格・各種申請手続き・退去強制・罰則などについて定めた、日本の外国人受け入れ制度の根幹となる法律です。
特定技能の在留資格や登録支援機関に関する制度など、制度の基本的な枠組みは、この入管法に基づいて規定されています。
入管法は、外国人受け入れ制度の全体像を把握するうえで、最も重要な法律です。
ただし、条文だけを読んでも理解が難しい場合が多いため、制度を学びたい方は解説書などの補助資料を活用するとよいでしょう。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
入管法施行令
入管法施行令では、各種申請手続にかかる手数料の額や、入管職員の階級、行政機関への権限委任などが定められています。
ただし、外国人の受け入れ手続きにおいて、施行令を直接確認する機会はあまり多くありません。
入管法施行令は、申請実務において使用することはほとんどありません。
申請手数料が値上げされるときは、この政令が改正されます。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法施行令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000178)
入管法施行規則
入管法施行規則は、入管法の細目を定めた法務省令のことで、申請手続の具体的な内容や提出書類、在留期間、代理人、申請取次制度などが規定されています。
入管法施行規則は、在留資格ごとに提出書類や申請取次のルールなどが定められているため、入管法のルールを理解するためには避けて通れない重要な省令です。
入管申請に携わる方であれば、必ず押さえておくべき内容が多く含まれています。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法施行規則
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054)
上陸基準省令
上陸基準省令は、外国人が日本に上陸する際に満たすべき、在留資格ごとの追加的な基準を定めた省令です。
特定技能に関しては、年齢や健康状態、技能水準、日本語能力水準、費用の徴収に関するルールなどがこの省令に規定されています。
上陸基準省令は、本来、外国人が新規に日本へ入国する際に適合すべき基準を定めたものです。
ただし、実務上は、日本国内に在留している外国人が在留資格の変更や在留期間の更新を行う際にも適用されるため、非常に重要な省令といえます。
上陸基準省令を理解することで、入管申請において何が審査の対象となるのかを具体的に把握できるようになります。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/)
特定技能制度(全分野対象)
ここからは、特定技能のすべての分野に共通するルールについて解説します。
特定技能制度の全体像を把握したい方や、外国人材の紹介事業・登録支援機関を運営している方にとって、非常に重要な内容です。
特定技能基準省令
特定技能基準省令は、特定技能に関する具体的なルールを定めた法務省令であり、雇用契約の基準、受け入れ企業等の基準、支援計画の内容に関する基準などが規定されています。
義務的支援の内容や、受け入れ企業に対する欠格期間の取扱いについても、この省令で定められています。
この省令の内容を理解することで、「特定技能雇用契約」や「特定技能支援計画」といった、制度の根幹をなす要素がどのようなものかを把握できるようになります。登録支援機関や特定技能外国人材の紹介事業を行う際は、必ず理解しておくべき内容が含まれています。
e-GOV法令検索|特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010005/)
特定産業分野を定める告示
特定技能の受け入れ対象となる産業分野は、この告示により定められています。
分野が追加される場合はこの告示が改正され、施行日から制度運用が開始されます。
受け入れ対象の分野を定める重要な告示ですが、情報量が少ないため特に読む必要はありません。
出入国在留管理庁|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001425330.pdf)
特定技能に関する閣議決定(関係閣僚会議)
特定技能制度における基本方針は、閣議決定によって定められます。
各分野の関係省庁は、この基本方針を踏まえたうえで、それぞれの分野別運用方針を策定します。
分野別の人手不足の状況の概要や受け入れ見込みの人数はこの分野別運用方針により示されています。
分野別方針は、各分野の人手不足の状況などがまとめられている便利な資料です。ボリュームの少ない資料であるため、繰り返し読む必要はありません。
出入国在留管理庁|閣議決定等
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html)
二国間協力覚書(二国間協定)
二国間協力覚書とは、特定技能制度に関して、日本政府と送出し国政府との間で取り交わされる協定文書です。
外国人の受け入れは、日本および送出し国の双方の法制度に適合する必要があるため、国ごとの制度や運用の違いを調整する目的で、この覚書が締結されています。
たとえば、送出し機関の利用が義務付けられているかどうかなどは、各国との二国間協力覚書によって定められています。
送出し機関との契約や、実際に受け入れ手続きを進める段階では、必ず確認しておくべき資料です。必要な国の覚書を必要なタイミングで読みましょう。
出入国在留管理庁|特定技能に関する二国間の協力覚書
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html)
特定技能運用要領・外国人支援要領
特定技能運用要領は、各種の法令にまたがる特定技能の複雑な制度をまとめた資料で、入管庁や分野別の関係省庁の法解釈などの指針示されています。
外国人支援要領は、特定技能外国人に対する法律上の支援のルールに関する入管庁の解釈が示されています。
特定技能制度の全体像を把握したい方は、まず「特定技能運用要領」に目を通すことをおすすめします。運用要領は、特定技能制度において最も重要な資料のひとつであり、制度の理解に欠かせません。
制度についてより深く学びたい方は、繰り返し読み返すことで理解が一層深まるでしょう。
出入国在留管理庁|特定技能運用要領
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html)
監修者コメント
入管分野の制度は、法改正が頻繁に行われることや、法律そのものの理解が難しいことから、正確性の高い二次情報を見つけるのが非常に困難です。
法律の条文や出入国在留管理庁などが発信する一次情報は難解なことも多いため、やさしく表現された二次情報に頼りたくなることもあります。
しかし、申請手続は外国人の人生に大きな影響を与える重要な判断であるため、最終的な決定を下す際には、必ず一次情報に目を通すか、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。