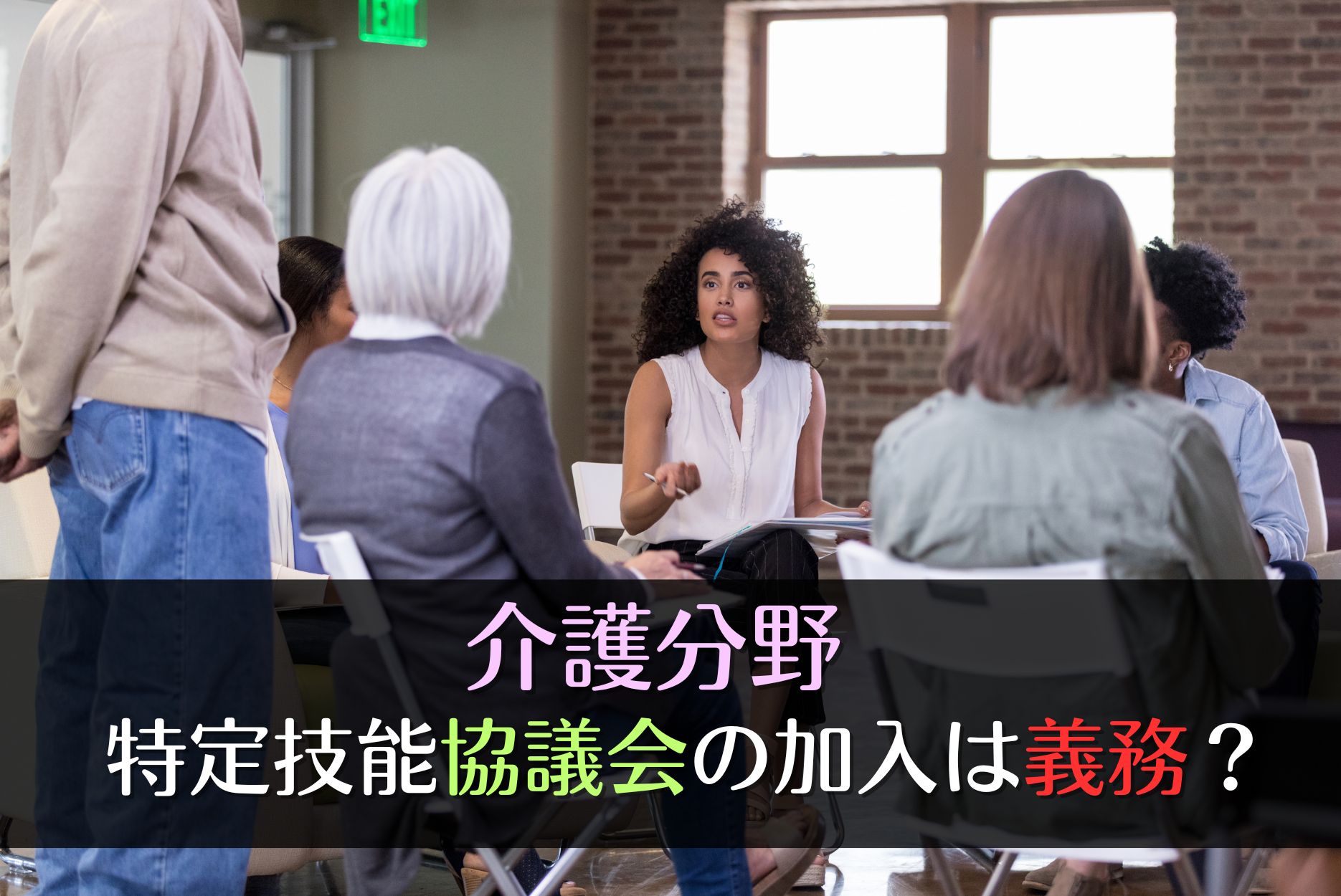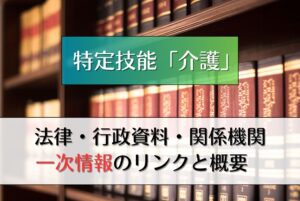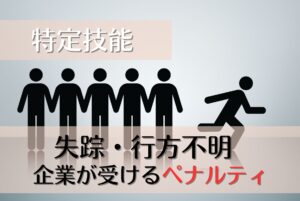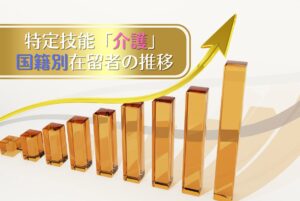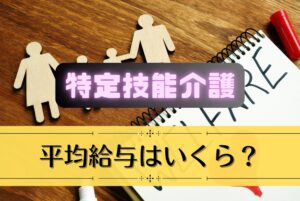監修者:申請取次行政書士 安藤祐樹
介護分野で外国人材の活用を進める企業や登録支援機関が増えていますが、「特定技能協議会」とは何か、加入が本当に必要なのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に制度の変更や運用ルールの細かな違いは、現場の担当者にとって分かりにくい点が多く、正しい理解が求められます。
この記事では、介護分野の特定技能協議会の概要や、その役割、加入や協力の義務があるかどうかについて詳しく解説します。初めて外国人介護人材の受け入れを検討している企業担当者や介護分野に進出予定の登録支援機関の方に向けて分かりやすく説明します。
介護分野特定技能協議会とは

介護分野において在留資格「特定技能」で外国人を雇用する場合、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。
運営主体は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)であり、厚生労働省からの委託を受けて協議会事務局を運営しています。

国際厚生事業団とは
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、厚生労働省から外国人介護人材の受入れや定着支援などの業務を委託されている機関です。
同団体は介護分野における特定技能協議会の事務局として、受入機関の申請内容の確認や、特定技能外国人への巡回訪問など実務的な支援を担っています。
加えて、EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れ事業においても重要な役割を果たしており、介護分野における外国人材受け入れの制度運営上の中心的な存在です。
協議会の役割
協議会の主な役割は、特定技能外国人の受け入れ制度に関する情報や優良な事例を広めることや、関連する法令の遵守を呼びかける活動にあります。
あわせて、介護分野における就業構造の変化や経済状況などの最新情報を収集・分析し、現場のニーズに対応しています。
地域ごとに異なる人手不足の実態や受け入れ状況を把握し、これらの情報を基に大都市への人材集中を防ぐための対策や調整も重要な業務です。
円滑かつ適切な特定技能外国人の受け入れ実現に向けて、現場で生じる課題や必要な情報を共有し合いながら運営を進めるための組織です。
協議会加入義務と協力義務

特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、在留資格申請を行う前に特定技能協議会に加入しなければなりません。
協議会への入会後、入会証明書を取得してから出入国在留管理局へ許可申請を行うことになります。
加えて、協議会に加入した介護事業所は、協議会が実施する情報共有や調査などの活動に対して必要な協力を行う義務があります。
こうした義務は、制度の適正な運用と外国人材受け入れの円滑な実施を支えるために設けられています。
登録支援機関には加入義務はない
特定技能外国人を雇用する際、介護事業者は外国人労働者の日常生活や職場での適応を支援する法的な義務があります。
この支援業務は、入管庁に登録された登録支援機関へ委託することができます。
この際、介護分野においては登録支援機関自体は特定技能協議会の加入対象ではなく、協議会に入会するのは実際に外国人を受け入れる介護事業者などに限られています。
ただし、支援業務を委託した場合は、登録支援機関も協議会の調査や情報共有などに必要な協力を行う義務があります。
協議会への入会手続き
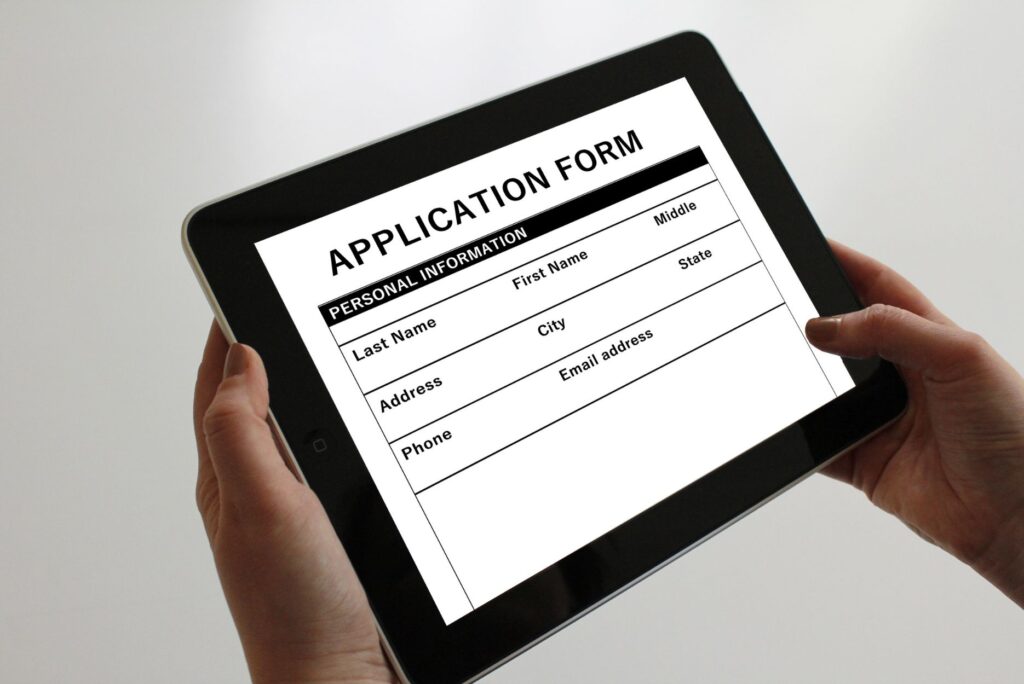
協議会への入会手続きは、オンライン申請システムを利用して行い、郵送や窓口での手続きは受け付けていません。
申請が完了すると、通常はおよそ2週間ほどで協議会入会証明書が発行されます。
入会証明書の交付を受けた後に、出入国在留管理局で在留資格の申請を行う流れとなります。
なお、協議会に加入する際には入会金や年会費などの費用負担は発生しません。
参考:厚生労働省|介護分野における特定技能外国人の受入れについて
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)
協議会入会後に行うこと

協議会への入会が完了した後は、事業者として適切に対応すべき手続きや情報管理が求められます。
ここからは、入会後に必要となる具体的な作業や注意点について順を追って解説します。
受け入れた外国人の情報を登録する
特定技能外国人を新たに受け入れた場合は、地方出入国在留管理局で在留資格の手続きを終えた後、4か月以内に外国人本人の情報を協議会へ登録する必要があります。
登録にあたっては、「雇用条件書」「支援計画書」「在留カードの写し」の3点をオンラインシステムから提出します。
雇用条件書および支援計画書については、在留申請時に提出した書類と同じものをそのまま流用します。
未登録の事業所・施設種別で外国人を受け入れる場合
協議会に登録されていない事業所や施設で新たに特定技能外国人を採用する場合は、まず該当する事業所情報を協議会へ申請し、入会証明書の再発行を受ける必要があります。
この証明書には新たに登録した事業所や施設種別が明記されます。
協議会に受入れ事業所が登録されていない状態では外国人の在留許可は取得できません。
登録済みの情報に変更があった場合
登録済みの受入機関情報や事業所情報、あるいは特定技能外国人の情報に変更が生じた場合は、協議会申請システム上で速やかに情報を最新の内容に更新することが求められます。
情報が正確に反映されていない場合、必要な証明書の発行や各種手続きに支障が生じるおそれがあります。
入会証明書の有効期限が近い場合
入会証明書には発行日からの有効期間が設定されており、初回発行時は1年間、更新後は4年間となります。
有効期限が近づいた場合、協議会申請システムを通じて有効期間満了の4か月前から更新手続きを行うことが可能です。
こうした更新作業を怠ると証明書が無効となり、外国人の受け入れに支障が生じるため、早めの対応が重要です。
まとめ
本記事では、介護分野における特定技能協議会の概要や入会手続き、入会後に必要な対応について詳しく解説しました。制度の目的や協議会の役割、介護事業者が順守すべき義務、そして実際の登録手順まで、受け入れを円滑に進めるための重要なポイントをまとめています。
外国人介護人材の受け入れを検討している方にとって、適切な手続きや協議会への協力は必須となります。不明点がある場合は、必ず公式情報や専門家のアドバイスを参考にし、余裕を持った準備を心がけることで、安心して人材の受け入れを進めることができるでしょう。
監修者コメント
協議会と聞くと、「大きな組織に加入しなければならないのでは」「入会後は頻繁に会合への参加が必要なのでは」といった不安を抱く方も少なくありません。
たしかに特定技能の協議会には加入義務がありますが、受け入れ事業者が行うべきことは、主に事業所情報や外国人従業員の情報など、協議会のシステムに登録されている情報を常に最新の状態に保つことです。
介護分野では巡回訪問への対応など、必要に応じて協議会の活動に協力する場面もありますが、過度に構える必要はありません。