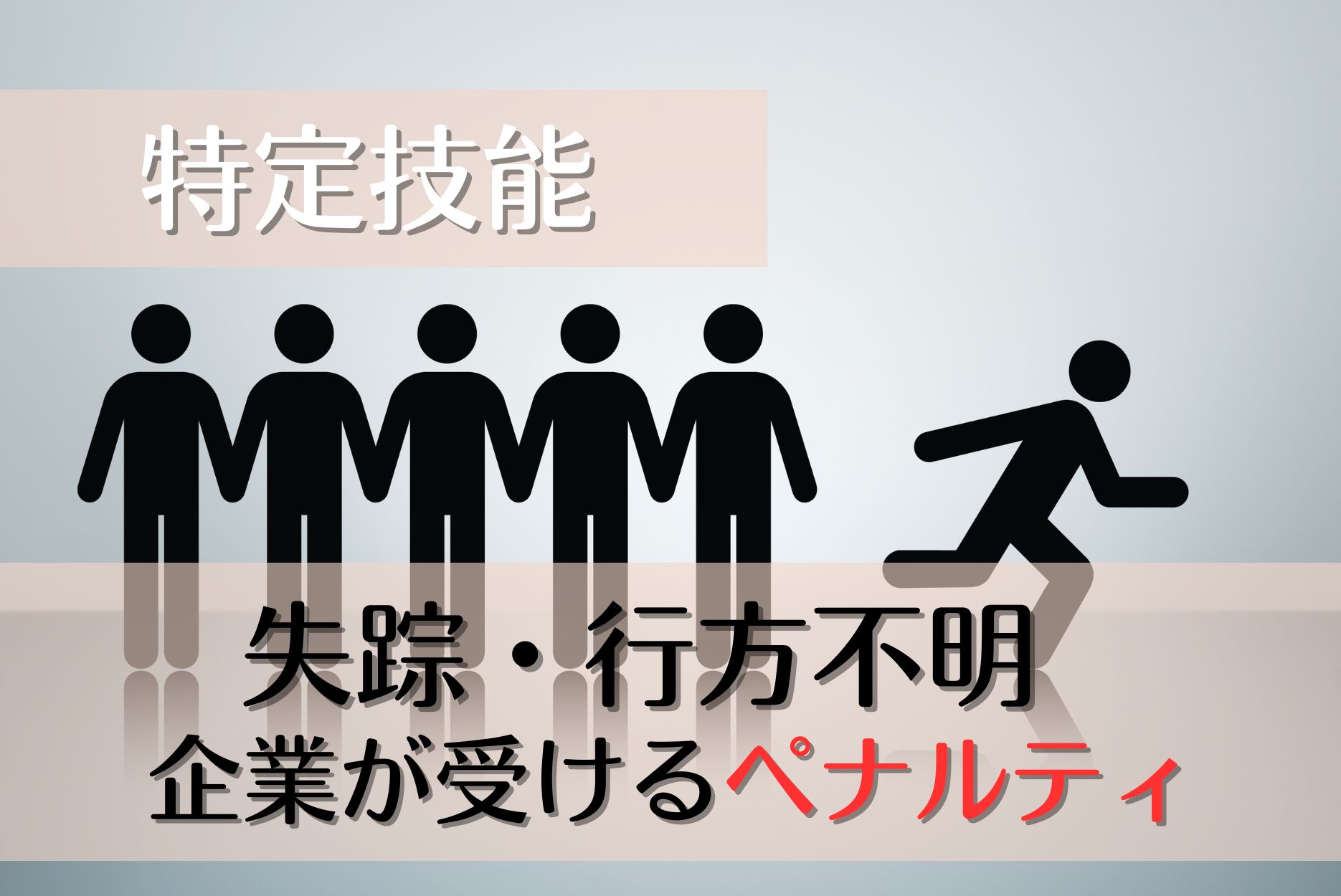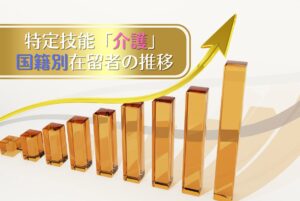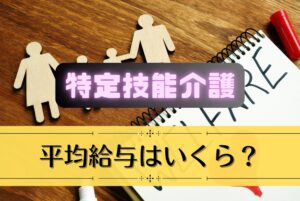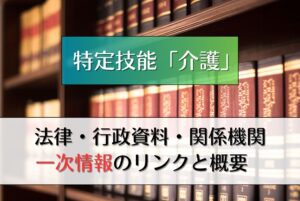特定技能外国人を雇用している企業にとって、失踪は深刻なリスクです。
突然の人員不足による業務停滞だけでなく、場合によっては法的なペナルティや今後の受け入れ制限につながる可能性があります。
特に原因が企業側にあると判断されれば、事業運営や採用計画に大きな影響を及ぼしかねません。
この記事では、特定技能外国人が失踪した場合に企業が負う責任や発生し得る不利益、適用されるペナルティの内容を整理します。
さらに、失踪の主な背景や防止策、発生時の適切な対応方法についても解説し、安定した外国人雇用のために押さえておくべきポイントをわかりやすくお伝えします。
失踪とはどのような状態を意味するのか

失踪とは、雇用している外国人労働者の所在や連絡先が不明となり、勤務先に出勤しない状態を指します。
永住者や定住者などの在留資格を持つ場合、就労は在留の条件ではないため、出勤しなくても入管法上の問題は直ちには生じません。
一方、特定技能の在留資格は雇用契約を前提に付与されており、在留許可は受入企業との雇用関係と結びついています。
このため、特定技能外国人がその職場で働いていない状態が続くと、入管法上は「失踪」とみなされることになります。
なお、失踪が発覚しても外国人本人と企業の双方が即座に違法状態となるわけではありませんが、認められた活動を行わずに失踪して他の就労活動を行ったり、許可された活動を3カ月以上継続して実施しない場合は、外国人側は入管法違反として扱われる可能性があります。
特定技能外国人が失踪したら届出義務が発生する

特定技能外国人が行方不明となった場合、受入企業は地方出入国在留管理局へ「受入れ困難に係る届出」を提出する義務があります。
提出期限は、失踪が判明した日から14日以内とされており、これは企業側に原因や責任がない場合でも義務が発生します。
届出義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があり、場合によっては今後の特定技能人材の受入れ資格にも影響を及ぼすことがあります。
そのため、行方不明者が発生した場合には速やかに事実確認と届出手続きを進めることが不可欠です。
届出事項と届出方法
届出の際は地方出入国在留管理局に「受入れ困難に係る届出書」「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書」「行方不明が判明した際の状況説明書」などを提出します。
届出には、対象となる特定技能外国人の氏名、生年月日、在留カード番号といった本人情報や、受入れが困難となった理由、失踪の経緯、企業側の実施した措置、その他失踪者の所在に関して判明している情報などを記載します。
提出方法は、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用する方法のほか、地方出入国在留管理局の窓口に直接持参するか、郵送で提出することが可能です。いずれの場合も、期限内に届出義務を履行することが不可欠です。
雇用契約終了届との違い
特定技能制度では、外国人との雇用契約が終了した場合、事由発生日から14日以内に「雇用契約終了届」を提出する義務があります。
この届出手続きは自己都合退職や契約満了、在留期間満了など、通常の離職時にも実施しなければなりません。
一方、特定技能外国人が行方不明となった場合は「雇用契約終了届」に加えて「受入れ困難に係る届出」が必要です。
「受入れ困難に係る届出」は所在が不明になった日から14日以内に提出する必要があり、その後に契約解除を行った際には、改めて「雇用契約終了届」を契約解除の日から14日以内に提出します。
両方の届出が必要となるケースでは、原則として「受入れ困難に係る届出」を先に提出するのが一般的ですが、提出可能な期間が重なることもあるため、同時に行っても差し支えありません。
失踪により企業に科せられるペナルティ

特定技能外国人が勤務先から失踪してしまった場合、その原因や企業側の関与によっては行政処分や法的制裁を受ける可能性があります。
ここでは、状況別に想定される影響や受入れ制限について説明します。
失踪原因が企業側にある場合
企業の労務・在留管理上の問題やその他の法令違反などに起因して特定技能外国人が失踪した場合、行方不明者の発生から1年間は新たに特定技能外国人の受入れは認められません。
この制限は、同一企業で雇用している他の特定技能外国人にも及び、雇用中の外国人の在留期間の更新などができなくなる可能性があります。その場合、企業全体の人材確保や事業運営に大きな支障が生じる可能性があるため、企業側に責任のある事由による失踪事案の発生は避けなければなりません。
企業が重大な違反行為を行った場合
企業が労働基準法や最低賃金法に違反して罰金刑を受けた場合、または暴行や脅迫といった刑法違反、人権侵害にあたる不正行為などを行った場合は、5年間特定技能外国人を受け入れることができなくなる可能性があります。
この中には、旅券や在留カードの不正な取り上げ、不当な違約金の徴収、財産の管理などの行為も含まれ、重大な違反行為として厳しく扱われます。
失踪がこうした行為に起因する場合、届出時にその経緯を詳細に報告する義務があります。
また、受入れ困難に係る届出の際に虚偽の申告を行った場合も同様に5年間の受入れ停止事由となり、企業の信用や採用計画に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
企業側に原因や違法性がない場合
企業側に過失や法令違反がない場合は、行方不明となった日から14日以内に「受入れ困難に係る届出」を期限通りに提出すれば、基本的にペナルティは科されません。
ただし、届出書に記載する経緯説明が不正確であったり、事実と異なる内容を記載した場合には、結果として事業者側に責任があると判断されるおそれがあります。
そのため、失踪の事実関係や受入れ停止などのペナルティが適用される条件を十分に把握したうえで届出書類を作成することが重要です。
特定技能外国人を採用する企業は、失踪が発生しても企業側に責任がないことを裏付けられるよう日常的な記録や証拠の保管体制を整えておくことが望まれます。
失踪の主な原因

特定技能外国人が職場を離れ行方不明となる背景には、複数の要因が考えられます。
ここでは、制度運用上特に多く見られる典型的な事例について整理し、その特徴や影響を詳しく解説します。
過酷な労働環境
雇用前に説明された勤務条件と、実際の職場環境が大きく異なる場合、労働者が強い不満や不安を抱くことがあります。
特に、高所での作業や重機・鋭利な工具を扱う業務などは、危険性や身体的負担が高いため、事前に十分な理解と同意を得ていないと短期間での離職に繋がりやすくなります。
加えて、安全管理や労働時間の配慮が欠けている環境では、精神的・肉体的負担が積み重なり、最終的に職場から離脱する選択を取る可能性が高まります。
こうした状況を防ぐためには、採用段階での正確な情報提供と、安全確保を徹底した労務管理が不可欠です。
多額の借金を抱えている
渡航前に海外の送り出し機関や仲介業者から高額な借入をしている場合、返済負担が生活や就労継続を圧迫することがあります。
こうした事情を抱えた外国人労働者は、より高収入を求めて在留資格外の就労や違法労働に関与し、失踪に至る危険性が高まります。
また、企業が不当な契約や高額な手数料徴収を行う仲介業者を経由して採用した場合、たとえ企業自身が直接関与していなくても、法令上は重大な不正行為に該当する可能性があります。
この場合、特定技能の受入れが5年間停止されるなどの厳しい処分を受けるおそれも生じます。
そのため、採用前には仲介業者の合法性や契約条件を慎重に確認し、適法かつ適正な送り出し機関とのみ取引を行う体制を整えることが重要です。
事前説明と異なる待遇
採用時に提示した条件と実際の待遇が異なると、労働者の不信感や不満が募り、離職や失踪のきっかけとなります。
特に、約束していた給与や勤務時間が守られない場合は深刻な問題へと発展しやすくなります。
加えて、サービス残業の強要や有給休暇の取得拒否などは、労働基準法等の法令違反に該当する可能性が高く、行政指導や刑事罰の対象となる場合があります。
こうした違反が明るみに出れば、企業は社会的信用を失うだけでなく、特定技能の受入れ制限といった不利益を被るおそれもあります。
このため、契約段階で提示した条件を誠実に履行し、労働環境の透明性を確保することが、失踪防止と法令遵守の両面で極めて重要です。
職場内での孤立
特定技能外国人の多くは家族と離れて単身で来日しており、職場での人間関係や地域社会とのつながりが希薄になると、孤独感から失踪に至ることがあります。
特に、日本語能力の不足により日常会話や業務上の意思疎通が難しくなると、孤独感に加えて精神的負担が大きくなります。
こうした孤立状態が続くと、精神的ストレスが蓄積し、職場や生活環境から離れる選択をしてしまう場合があります。
失踪後にそのまま帰国するケースでは企業の責任が問われない可能性もありますが、法律上義務付けられた生活支援や相談体制の提供など、支援義務を果たしていないと判断されれば、一定期間特定技能外国人の受入れが制限される可能性があります。
そのため、企業には孤立を防ぐための施策や、安心して働けるサポート体制の整備が求められます。
失踪時の対応や事前対策としてやるべきこと

特定技能外国人が所在不明となった場合や、その兆候が見られる際には、企業として迅速かつ適切な対応が求められます。
ここでは、特定技能外国人が失踪した際に企業が行うべき行動の手順と未然防止のための具体策について説明します。
失踪が発生してしまった場合
特定技能外国人が行方不明になった場合は、まず状況を把握するために本人への電話やメール連絡を試み、友人や同僚、登録支援機関など関係者からの聞き取りを行います。
事件や事故の可能性がある場合や、不法就労のおそれがある場合には、義務ではないものの警察への通報も検討しましょう。
入管庁への報告は、所在不明となった日から14日以内に「受入れ困難に係る届出」を提出することが法律で定められています。
これは、失踪の原因が判明している場合も、理由が不明な場合も同様に義務が発生し、自己都合退職でない限りは必ず手続きを行う必要があります。
最終的に企業側の責任による失踪と判断された場合は、その後1年間または最長5年間にわたり特定技能外国人の受入れが制限される可能性があります。
その際には、在籍している他の外国人労働者が不利益を被らないよう、転職支援や必要な生活支援など適切な措置を講じることが求められます。
企業がペナルティを回避するためにやるべきこと
外国人労働者が失踪する背景には、劣悪な労働環境や待遇の不備、体調不良、人間関係の摩擦など、多様な要因が存在します。
企業側の責任が認められた場合には、1年または5年間の特定技能受入れ停止に加え、過料や罰則が科される可能性があります。
このような事態を防ぐためには、雇用契約を適法かつ労使双方の合意に基づき締結し、提示した条件どおりの待遇で雇用することが基本です。
さらに、法令で定められた支援義務を確実に履行し、悪質な仲介業者を介さないこと、職場内のハラスメントや差別を未然に防ぐ取り組みも欠かせません。
加えて、失踪発生時には迅速かつ適切に対応できるよう、入管庁への届出方法や必要書類の様式を事前に確認し、社内で共有しておくことが重要です。
これにより、不測の事態においても法令遵守と企業の信用維持を両立できます。
まとめ
本記事では、特定技能外国人が失踪した場合の企業側の届出義務や、原因別に異なるペナルティの内容、発生しやすい背景要因、そして発生時・予防のための具体的な対策について解説しました。
制度の特性上、雇用条件や支援体制の不備が原因であれば、企業は長期的な受入れ制限や罰則を受ける可能性があります。
外国人雇用を検討している企業担当者は、日頃から契約条件の遵守、職場環境の改善、適正な仲介業者の選定、そして支援義務の徹底を行うことが不可欠です。加えて、失踪発生時の報告手順や必要書類を事前に確認し、速やかに対応できる体制を整えておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
監修者コメント
近年、技能実習生の行方不明件数がメディアで大きく報じられるなど、失踪問題は社会的な関心事となっています。
私も行政書士として企業担当者の方とお話しする際、「外国人を雇用して、もし失踪したらどうなるのか」というご相談を受けることがあります。
こうした不安を解消するためには、失踪を未然に防ぐための予防的な取り組みと、企業が負う法的義務や責任について正しく理解しておくことが不可欠です。
外国人雇用は、日本人雇用と比べて入管法に関するリスク管理が求められるため、人材受入れの際には入管法に精通した専門家を活用するなど、適切な体制を整えたうえで採用活動を進めるとスムーズです。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
出入国在留管理庁|特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html)
出入国在留管理庁|特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html)
出入国在留管理庁|特定技能制度における運用改善について
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html)
出入国在留管理庁|特定技能運用要領
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html)