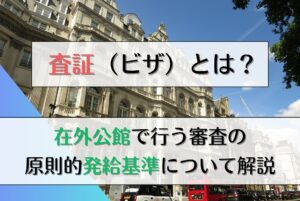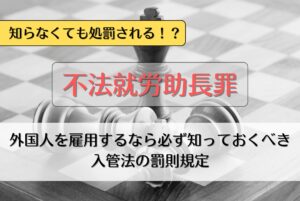外国人が日本に滞在するためには、その目的に合わせた許可を取得しなければなりません。
これを「在留資格」といい、一般的にはビザと呼ばれることもあります。
本記事では、日本における在留資格29種類を整理して紹介します。就労ビザ19種類、非就労ビザ5種類、特定活動ビザ、そして就労制限のない居住ビザ4種類について、それぞれの活動内容や対象者をわかりやすく解説します。
ビザ(在留資格)は全29種類

日本で暮らす外国人は、入管法に定められているいずれかの在留資格を取得する必要があります。
2025年10月現在、在留資格は全部で29種類に区分され、それぞれ活動範囲や在留期間が異なります。
また、在留資格は目的に応じて「就労ビザ」「非就労ビザ」「特定活動ビザ」「居住ビザ」の4種類に分類されることもあります。
| 在留資格一覧 |
|---|
| ■就労ビザ 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」 ■非就労ビザ 「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」 ■特定活動ビザ 「特定活動」 ■居住ビザ 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 |
なお、ビザと在留資格は本来は異なる概念ですが、一般的には「永住ビザ」「就労ビザ」「留学ビザ」など在留資格を指してビザという言葉が用いられています。本記事でも同じ意味でビザという言葉を用いて解説します。
就労ビザは19種類

就労ビザは、外国人が日本で報酬を伴う仕事に従事するための在留資格で、全部で19種類に区分されています。
それぞれの在留資格には活動できる範囲が細かく定められており、職種や業務内容によって取得すべき就労ビザの種類や審査基準が異なります。
外交
「外交」の在留資格は、外国政府の大使や公使、総領事、代表団の構成員などの外交官とその家族に与えられるものです。
在留期間は「外交活動を行う期間」とされており、通常の在留資格のように年数で区切られることはありません。
この在留資格を持つ外国人は、滞在が長期に及んでも中長期在留者には含まれないため、在留カードの交付対象外となります。
公用
「公用」の在留資格は、外国政府の在外公館に勤務する職員や国際機関から公務で派遣される者、その家族に与えられます。
外交の在留資格と似ていますが、公用の場合は在留期間が設定されており、最長5年までの範囲で期間が付与され、期限前には更新許可を受ける必要があります。
この在留資格で滞在する外国人は中長期在留者には区分されないため、在留カードの交付対象とはなりません。
教授
「教授」の在留資格は、日本の大学やこれに相当する教育機関、高等専門学校で研究や教育、または研究指導を行う者に与えられます。
在留期間は就労予定期間などを基に決定され、一度に付与される最長期間は5年とされています。
芸術
「芸術」の在留資格は、作曲家や画家、作家などが日本で音楽や美術、文学といった芸術活動を行う場合に与えられます。
この在留資格では収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動が認められています。
在留期間は活動の内容や在留状況の安定性などに応じて決定され、一度の許可で最長5年までとなります。
宗教
「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から派遣された宣教師や僧侶などが日本で布教活動や宗教上の行為を行う場合に与えられます。
この在留資格の取得対象者は宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官などです。
在留期間は活動の内容など踏まえて決定され、一度の許可で最長5年まで認められます。
報道
「報道」の在留資格は、外国の報道機関と契約している記者やカメラマンなどが、日本で取材や報道活動を行う際に認められるものです。
対象職種は新聞や雑誌などの記者、カメラマン、編集者、アナウンサー、レポーターなどです。
在留期間は活動内容や滞在予定期間などを踏まえて決定され、一度の許可で最長5年まで認められます。
高度専門職
「高度専門職」の在留資格は、学歴や職歴、年収などを基準にしたポイント制度により、高度人材と評価された外国人に与えられます。
この在留資格には「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に応じた分類が存在します。
また、それぞれの分類ごとに1号と2号の在留資格があり、1号は最長5年の在留が認められ、2号では無期限の滞在が可能です。
高度専門職は、永住許可の要件が短縮されるほか、親や家事使用人の帯同など複数の優遇措置が受けられる点も大きな特徴です。
経営・管理
「経営・管理」の在留資格は、企業等の経営を行う経営者や、支店長や執行役員などの管理職に与えられます。
この在留資格を取得すると、日本国内において貿易や各種事業の運営、または管理業務に従事することが認められます。
在留期間は事業計画や滞在予定期間など応じて決定され、一度に付与される最長期間は5年です。
法律・会計業務
「法律・会計業務」は、法律や会計に関する資格を必要とする業務に従事する者に与えられる在留資格です。
対象となるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の11種類が該当します。
在留期間は滞在予定期間や業務の安定性に応じて決定され、最大で5年まで許可される可能性があります。
医療
「医療」の在留資格は、医師や歯科医師、看護師など資格を有する外国人医療従事者が日本で働くための在留資格です。
対象職種は医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士です。
在留期間は滞在予定期間や在留の安定性などに応じて決定され、一度に認められる在留期間は最長5年です。
研究
「研究」の在留資格は、政府機関や民間企業などに所属し、日本国内で研究活動に従事する研究者に与えられます。
この在留資格の対象者は、公的機関や企業との契約に基づく研究活動に従事する者です。
大学などで教授として研究活動を行う者は、この在留資格の対象とはなりません。
一度に許可される最長期間の上限は5年で、延長が必要な場合は在留期間更新許可申請を行います。
教育
「教育」の在留資格は、小学校や中学校、高等学校、特別支援学校などで語学教育やその他の授業を行う外国人に付与される在留資格です。
民間企業が運営する語学学校での指導はこの資格に含まれず、「技術・人文知識・国際業務」に区分されます。
在留期間は個別の審査によって決定され、一度に与えられる最長期間は5年です。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、「理系または文系の学問的知識を応用した業務」や「外国語や外国文化に基づく感受性などを活かす業務」に従事する者に与えられる在留資格です。
この在留資格で従事できる業務は、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者など、多岐にわたります。
対象となる職種の幅が広いため、現在は多くの外国人材がこの在留資格を取得して日本で就労しています。
在留期間は企業規模や在留状況、活動実績などによって決まり、一度に付与される最長期間は5年です。

企業内転勤
「企業内転勤」の在留資格は、海外の事業所から日本の本店や支店、事業所などへ一定期間駐在する外国人に付与される在留資格です。
活動内容は「技術・人文知識・国際業務」と同一であり、専門性を必要とする業務のみに従事可能です。
一度に認められる在留期間の上限は5年とされており、定められた駐在期間などに応じて決定されます。
介護
「介護」の在留資格は、日本の介護施設等との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
この在留資格を取得するには、日本の国家資格である介護福祉士の合格が必要です。
したがって、介護ビザは特定技能や技能実習など、他の在留資格から切り替えて申請されることが多く、入国時に直接取得する事例はごくわずかです。
一度に付与される在留期間は最長5年です。
興行
「興行」の在留資格は、舞台芸術や音楽、スポーツ、その他の芸能活動などに従事する際に取得する在留資格です。
対象職種は俳優、歌手、演奏家、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手などです。
在留期間は一度の許可で最長3年まで付与されます。
技能
「技能」の在留資格は、産業上の特殊技能に基づく高度な熟練技術を必要とする分野で働く際に認められます。
具体的な職種の例としては、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機操縦士、貴金属加工職人などが挙げられます。
一度の許可で付与される在留期間は最長5年で、職種ごとに定められた実務経験などが審査の対象となります。
特定技能
「特定技能」の在留資格は、深刻な人材不足に直面する産業分野で即戦力となる技能を持つ外国人を受け入れるために設けられています。
特定技能1号は「相当程度の技能」を有する者が対象で、2025年10月現在において、介護や建設、外食、農業など16の産業分野で人材の受け入れが行われています。
一方、2号は「熟練した技能」が求められ、対象となる産業分野は建設、外食、農業など11分野です。
一度に与えられる在留期間は1号が最長1年で、2号が最長3年となっており、延長を希望する場合は在留期間更新許可申請が必要です。
また、特定技能1号は通算の在留期間の上限が設定されており、5年を超えて1号ビザのまま日本に滞在することはできません。
技能実習
技能実習の在留資格は、開発途上国への技術移転を目的として設けられた制度で、技能実習生が日本で学んだ知識や技能を母国に還元することを目的として制度が運用されています。
技能実習には1号、2号、3号があり、いずれも認定を受けた技能実習計画に基づいて段階的に実習を行います。
在留期間は1号が最長1年、2号と3号はいずれも最大2年と定められています。
なお、技能実習は1号、2号、3号合わせて通算5年を超えて技能実習ビザのまま日本に滞在することはできません。
就労を目的としないビザは5種類

就労を目的としない在留資格には5種類があり、留学や文化活動など活動内容に応じて分類されています。
ここではそれぞれの特徴を順に解説します。
文化活動
「文化活動」の在留資格は、「日本の特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行う」「専門家の指導を受けてこれを修得する」場合にに認められる在留資格です。
対象となる文化・技芸は、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、禅、空手などです。
一度に付与される在留期間は最長で3年と定められており、延長を希望する場合は都度更新が必要です。
文化活動ビザでは就労はできないため、在留審査の際は主に保有資金などの資産状況が重視されます。
短期滞在
「短期滞在」の在留資格は、日本に一時的に入国して短期間の観光や親族訪問、会合参加、業務連絡などを行う場合に付与されます。
対象となる活動は観光や保養のほか、スポーツや講習への参加、視察など、収入を得ることを目的としない活動です。
査証免除国のパスポート保持者であれば、事前に大使館で査証を取得せずに入国し、空港で行う入国審査の際に短期滞在ビザを付与する仕組みが設けられています。
在留可能期間は最長90日であり、原則としてその更新は認められていません。
留学
「留学」の在留資格は、日本の大学、専門学校、日本語学校などで教育を受ける活動を行う外国人に付与されます。
原則として、収入を得る活動は認められていませんが「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイトをすることも可能です。
在留期間は教育機関の種類により異なり、大学入学者は最長4年3か月まで留学ビザで滞在することが認められています。
研修
「研修」の在留資格は、日本の企業や団体に受け入れられて技能や知識を学ぶ活動に対して認められる在留資格です。
原則として報酬を得る活動を行うことは認められておらず、技能実習などとは性質が異なります。
一度に付与される在留期間は最長1年です。
家族滞在
「家族滞在」は、就労ビザなどで日本に滞在する外国人が、配偶者や子どもを呼び寄せて扶養する場合に許可される在留資格です。
この在留資格を持つ者は、原則として働くことはできませんが、「資格外活動許可」を受ければ週28時間まで就労が可能とされています。
一度に付与される在留期間は最長5年ですが、扶養者に与えられる在留期間に合わせて決定されます。

特定活動ビザは1種類でも内容は50種類以上ある

「特定活動」は、法務大臣が個々の事情を考慮して活動内容を指定する在留資格です。
入管法上は1種類の在留資格として分類されますが、2025年10月現在、あらかじめ定められた告示は1号から57号まで設けられています。
そのため、特定活動ビザを取得した外国人が行うことができる活動内容は、就労可と就労不可を含めて50種類以上存在しています。
この在留資格には、告示に基づいて活動内容が示されている「告示特定活動」と、個別の事情に応じて都度指定される「告示外特定活動」があります。
代表的な告示特定活動には、「5号:ワーキングホリデー」「46号:本邦大学等卒業者」「55号:特定自動車運送業準備」などがあります。
一度に付与される在留期間は最長で5年ですが、具体的な活動内容によって在留期間の上限は大きく異なります。
就労制限のない居住ビザは4種類

居住ビザは、外国人の身分や地位に基づいて与えられる在留資格であり、就労ビザのように在留資格ごとの業務内容の制限はありません。
ここから就労制限のない4種類の居住ビザを紹介します。
永住者
「永住者」は、法務大臣から永住許可を受けた外国人に与えられる在留資格であり、就労制限はありません。
永住許可を申請するには、原則として10年以上継続して日本に滞在し、そのうち5年以上は就労ビザ(技能実習と特定技能1号を除く)または居住系ビザで滞在していることが求められます。
また、日本には入国時点で永住許可が付与される制度は存在せず、必ず別の在留資格で入国して年数要件を満たした上で永住許可申請をする必要があります。
永住者の在留期間は無期限で更新義務はありませんが、在留カードは7年ごとに更新する必要があるため注意が必要です。
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した外国人に付与されます。
この在留資格を持つ者には入管法上の就労制限が課されていないため、労働基準法などの法律を遵守すれば職種を問わず働くことが可能です。
付与される在留期間は審査により決定されますが、一度に認められる最長期間は5年と定められています。
永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者や特別永住者の配偶者、または永住者等の子として日本で生まれ継続して在留している外国人に認められます。
日本国外で出生した子や出生後に出国し日本国内で在留を継続していない子は対象外となるため注意が必要です。
この在留資格には入管法上の就労制限が設けられていないため、労働法令など他の法令を遵守する限り職種を問わず働くことができます。
一度に付与される在留期間は最長で5年となっています。
定住者
「定住者」は、法務大臣が個別の事情を考慮して日本国内での居住を認める場合に付与される在留資格です。
この在留資格には、あらかじめ法務省告示で定められた「告示定住」と、告示に基づかず個別判断で認められる「告示外定住」が存在します。
代表的な告示定住の例として、「日系2世・3世」、「定住者の配偶者」、「中国残留邦人」、「第三国定住難民」などが挙げられます。
入管法上の就労制限は設けられていないため、労働関係法令を遵守すれば幅広い職業に従事可能です。
一度に付与される在留期間は最長5年とされています。
まとめ
本記事では、29種類の在留資格それぞれの特徴を整理しました。
外国人が日本に滞在し、安定した生活を築くためには、在留資格制度を正しく理解することが欠かせません。
在留資格ごとに申請方法や審査基準は大きく異なり、誤った認識は不許可や在留継続の不安定さにつながる可能性があります。
不安や疑問を感じた場合は、早めに専門家へ相談し、正確な情報を踏まえて手続きを進めることが重要です。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法施行規則
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054)
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/)
出入国在留管理庁|在留資格一覧表
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)