近年、グローバル化の進展により海外との取引や多言語対応の重要性が高まり、通訳・翻訳・語学指導の人材を採用したいと考える企業が増えています。こうした状況を受けて、企業の人事担当者には職種に応じて適切な在留資格を判断する力が求められています。さらに、外国人本人にとっても、自身の希望する職種に合った在留資格を理解しておくことで、就職活動における企業選びの精度が高まります。
本記事では、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格について、その基本的な仕組みや許可取得の条件を整理し、典型的な許可・不許可の事例を示しながら、申請前に押さえるべき実務上のポイントをわかりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)は、営業職や開発職、事務職などの業務に従事する外国人が取得する在留資格です。
この在留資格は主にオフィスワーカーを対象としており、単純労働や肉体労働を中心とする職種では認められていません。
令和6年末時点では418,706人が技人国の在留資格で日本に滞在しており、永住者や技能実習に次いで3番目に多い在留資格区分となっています。
以下に、技人国で就労することが認められる3つの枠組み「技術」「人文知識」「国際業務」について解説します。
「技術」分野の業務
「技術」分野の業務は、理学や工学などの理系学問を基盤とする職種が該当します。
IT分野では、システムエンジニアや情報セキュリティの専門家などが含まれ、情報技術に関する高度な知識が求められます。
製造や建設の分野では、機械設計や建築設計などが対象となり、それぞれに求められる専門的な技術力を有していることが許可の前提となります。
「人文知識」分野の業務
「人文知識」分野の業務は、法律学や経済学、社会学など文系の学問を基盤とする知識を活かす職種が中心です。
例えば、企業活動における営業や企画が該当し、専門知識を踏まえて商品やサービスを市場に展開する役割を担います。
また、経理や人事、総務、広報といった管理部門の業務も含まれ、経済や社会制度に関する理解を前提とした実務が求められます。
「国際業務」分野の業務
「国際業務」分野は、外国の文化や言語に基づく理解や感受性を必要とする職種が中心となります。
代表的な業務には通訳や翻訳があり、異なる言語間で正確に意味を伝える高度な専門性が求められます。
語学指導の業務では、外国語の文法や話法を体系的に教える力が必要であり、教育現場で重要な役割を担います。
さらに、海外マーケティングや広報活動も国際業務に含まれ、外国市場の特性を踏まえた企画や販売戦略を立案する能力が重視されます。

通訳者・翻訳者・語学指導者として採用する条件

通訳者・翻訳者・語学指導者の職種は基本的には「国際業務」に区分されますが、状況により「技術・人文知識」の業務と重なる場合もあり、許可取得のための基準は一律ではありません。
ここからは、外国人がこれらの職種で働くために求められる学歴や実務経験などの条件について整理して解説します。
専属の通訳者・翻訳者・語学指導者として働く場合
専属の通訳者・翻訳者・語学指導者として働く場合は、原則として「国際業務」の許可基準である3年間の実務経験を満たす必要がありますが、大学(短期大学を含む)を卒業している場合はこの基準が緩和されます。
大学または短期大学の卒業者であれば、国際業務のうち通訳・翻訳・語学指導に限って、実務経験がなくても基準に適合すると判断されます。
一方で、高等学校の卒業者や専門学校で専門士の称号を取得した者には緩和措置は認められず、原則通り3年以上の実務経験を有することが条件となります。
技術・人文知識の業務と兼務する場合
営業職や開発職などの「技術・人文知識」に該当する業務と、通訳・翻訳や語学指導といった「国際業務」を兼ねる場合は、まず技術・人文知識の基準を満たしていることが前提となります。
その条件としては、大学卒業または国内の専門学校を修了して専門士の称号を得ていることに加え、専攻科目と従事する業務との関連性が求められます。
ただし、学歴要件を満たさない場合でも、10年以上の実務経験を証明することができれば許可を取得することが可能です。
専攻科目と業務の関連性については、大学卒業者には比較的柔軟に判断が行われますが、専門学校卒業者についてはより厳格に関連性が求められます。
通訳者・翻訳者・語学指導者採用の許可事例
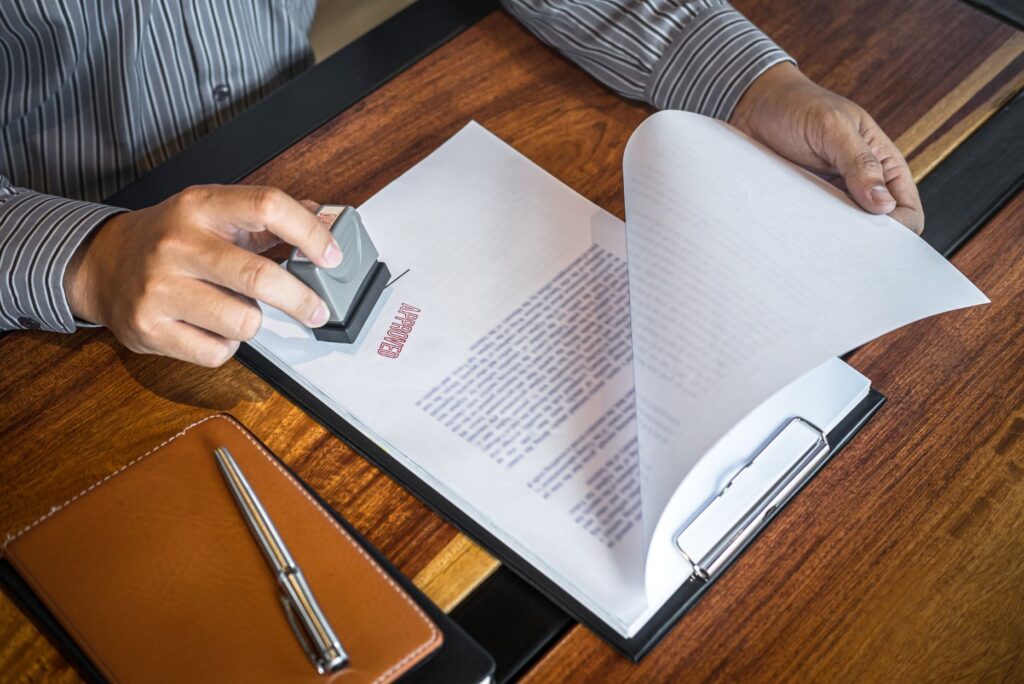
通訳者・翻訳者・語学指導者としての採用が認められた具体的なケースを、入管庁が示す許可事例をもとに紹介します。
海外の大学を卒業している場合
海外の大学を卒業した者の許可事例としては、以下のようなケースが示されています。
大卒者の場合は原則として実務経験を要しませんが、審査においては日本語能力の有無やその必要性が考慮される点に注意が必要です。
- 海外で経営学を専攻し大学を卒業した後、日本の食料品・雑貨等の輸入販売会社に入社し、月額約30万円の報酬を得て、本国との取引に伴う通訳・翻訳業務に従事する
- 海外の大学を卒業し、日本の語学学校で月額25万円の報酬を受けて語学教師として勤務する
日本の大学を卒業している場合
日本の大学を卒業した者の許可事例としては、以下のようなケースがあります。
- 日本の大学の経営学部を修了した者が、IT関連サービスを業務とする企業と契約し、翻訳・通訳の業務に従事する
- 日本の大学の経営学部を修了した者が、日本の航空会社と契約を結び、月額約25万円の報酬を受けて国際線の客室乗務員として勤務し、緊急時対応や保安業務に加えて、母国語・英語・日本語を用いた通訳や案内、さらに社員研修における語学指導を担当するもの
日本の専門学校を卒業して専門士を付与されている場合
日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者が通訳・翻訳業務に従事する場合の許可事例として、以下のケースが公表されています。これは専属通訳としてではなく、文系学問に基づく「人文知識」業務の一部として通訳や翻訳が位置付けられているものと考えられます。
- 日本の専門学校の観光・レジャーサービス学科で観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論などを履修した者が、大型リゾートホテルの総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務などをシフトにより担当するとして申請があった。
業務内容の確認を行ったところ、一部にレストランでの接客や客室備品オーダー対応といった「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務も含まれていたが、申請人は総合職として雇用されており、主な業務はフロントでの通訳・翻訳、予約管理、ロビーでのコンシェルジュ対応、顧客満足度分析などであり、日本人の総合職従業員と同様の職務内容であることが確認されたもの
不許可事例

技人国で通訳・翻訳・語学指導に従事するには、許可基準を満たすことが不可欠ですが、あらかじめ典型的な不許可事例を理解しておくことが安心につながります。
日本人と比較して報酬が低い
技人国の許可を得るためには、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。
以下は、報酬が不当に低いと判断され、不許可となった事例です。
- 日中通訳翻訳学科を卒業した者が、輸出入業を営む企業と雇用契約を結び、月額17万円で翻訳や商談時の通訳に従事するとして申請があった。しかし、同時期に採用された新卒日本人の報酬が月額20万円であることが判明し、日本人と同等額以上の待遇を受けているとは認められず不許可となった
入社後の研修計画が不透明
技人国の在留資格申請では、合理的な理由があれば研修期間中に「技人国の本来の業務に該当しない業務」を行い、その後に技人国の業務へ移行することも認められる場合があります。
しかし、以下の事例は採用後の計画が不透明であるとして不許可となりました。
- ビルメンテナンス会社に入社した者から、会社が将来受け入れる予定の複数の外国人従業員への対応として、通訳や技術指導に従事するとして申請があった。
しかし、将来の受入れ計画自体が具体化しておらず、開始までの間は研修を兼ねて清掃業務に従事するとされていた。
この研修期間の業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも該当しなかったため不許可となった。
専門科目と業務内容の関連性がない
専門学校卒業者の場合、大卒者と異なり実務経験なしで許可を得るには、「技術・人文知識」に該当する形で専攻科目と業務内容の関連性が必要となります。
以下は、その関連性が認められず不許可となった事例です。
- 専門学校の声優学科を修了した者が、外国人客の多いホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして通訳や翻訳業務に従事するとして申請しました。しかし、専攻分野とのつながりが確認できなかったため、結果として不許可と判断されました。
まとめ
この記事では、技人国における通訳・翻訳・語学指導の採用条件や許可・不許可の事例を取り上げ、企業と外国人双方が円滑に採用活動・就職活動を進めるために必要な知識を解説しました。
外国人材の雇用を検討する企業や就労を希望する本人にとっては、採用条件や職務内容を制度上の基準に適合させることが重要です。
判断に迷う点がある場合は、早い段階で専門家に相談し、計画段階から制度に沿った準備を整えることで、安心して申請に臨むことができるでしょう。
監修者コメント
技人国の在留資格申請では、業務の具体的な内容やスケジュールを正確に申告することで申請の信頼性が高まり、長期の在留期間を取得しやすくなります。
また、申請者自身が許可要件を理解したうえで精度の高い申請資料を整えることは、入管行政の負担軽減や不正防止の観点からも有効です。
技人国の申請に臨む際は、最良の結果を得るために、可能な限り丁寧かつ正確に手続きを行うことが望まれます。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
e-GOV法令検索|出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016/20230801_505M60000010028)
出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf)









