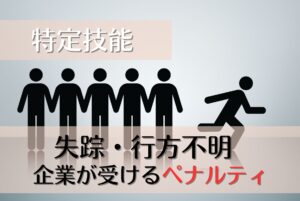外国人を採用したい企業や、日本での就労を目指す方にとって、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」と「特定技能」の違いを理解しておくことは重要です。
いずれも就労を目的とした在留資格ですが、認められる業務内容や求められる技能には明確な違いがあり、判断を誤ると採用計画やキャリア形成に大きな影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、技人国と特定技能の業務範囲を整理し、2つの在留資格の制度の違いや共通する部分を具体的に解説します。
さらに、業務範囲を逸脱した場合に生じるリスクについても取り上げ、雇用側・就労側双方にとって役立つポイントをわかりやすく紹介します。
技人国と特定技能の業務範囲

技人国は、学歴や実務経験を基盤とする専門的な知識やスキルを活かして就労するための在留資格です。
一方で、特定技能は人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能水準を満たした外国人が即戦力として働くことを前提に設計されています。
このように両制度は根本的な仕組みが異なるため、許可される業務範囲も異なります。
ただし、実務の中では境界が分かりにくい業務も存在するため、具体的な内容を整理して解説していきます。
技人国の業務
技人国の在留資格で認められる業務は、大きく「理系・文系の学問的素養を必要とする業務」と「外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務」に区分されます。
具体的には、企業での営業や事務、システム開発のほか、通訳や翻訳、外国語教育などが該当します。
技人国の対象となる業務は幅広く、専門性を活かして多様な分野で活用できる在留資格といえます。
一方で、この資格は高度な専門性を前提としているため、単純作業や肉体労働を中心とする業務は認められていません。
そのため、未経験者が短期間の訓練で習得できる作業には従事できず、専門的な知識や技能を必要とする業務に限定されている点が大きな特徴です。

特定技能1号の業務
2025年9月時点において、特定技能1号の業務は人手不足が深刻な16の産業分野に限定されており、一定水準以上の技能や知識を必要とする業務が対象となります。
具体的には、介護、外食業、建設業など分野ごとに細かく業務内容が定められており、外国人は試験などで証明した能力を活かして、即戦力として働くことが求められます。
主な業務は各分野における現場作業ですが、関連業務として他の従業員を指導するなど管理的な役割を担うことも可能です。
ただし、関連業務のみに従事することは認められていないため、現場作業を中心に業務を行う必要があります。
特定技能2号の業務
特定技能2号の在留資格は、建設や造船などを含む11分野に設けられており、熟練した技能を必要とする業務が対象となります。
この在留資格を得るためには、原則として一定期間以上の実務経験が求められ、現場作業に従事するだけでなく、従業員の指導や作業工程の管理といった責任ある役割を担うことも必要です。
そのため、特定技能1号と比べてより高度な技能や経験が要求され、長期的な就労も認められます。
業務範囲に重なる部分はあるのか?

技人国と特定技能の許可範囲が重なるかどうかについて、入管庁が明確な基準を示しているわけではありません。
一方で、実際の現場では両制度の業務内容が近接するケースがあり、境界が分かりにくい状況が生じることがあります。
ここからは、代表的な事例を取り上げつつ、どのような場面で業務内容が重なる可能性があるのかを解説していきます。
1.ホテルのフロント業務など顧客管理
ホテルのフロントで行う顧客情報の管理や予約対応といった業務は、技人国と特定技能のいずれの在留資格にも該当する可能性があります。
特に、外国語能力を活かした顧客対応は技人国の業務として認められる場合があり、同時に宿泊分野の特定技能に含まれる業務でもあります。
ただし、技人国ではベッドメイキングやレストランでの接客といったフロント以外の宿泊者向けの業務を行うことは認められていません。
また、特定技能「宿泊」の分野では、宿泊施設における多様な業務に従事することが要件とされているため、1号と2号どちらも在留期間全体を通じてフロント業務だけに従事する働き方は認められません。
2.従業員のキャリア指導などの業務
従業員へのキャリア指導は、技人国と特定技能の双方にまたがる可能性のある業務の一つと考えられます。
例えば、飲食業において従業員のキャリア形成を目的に教育や助言を行う場合、高度な専門性を要する技人国の業務範囲に含まれることがあり、同時に特定技能「外食」の管理業務にも該当する可能性があります。
ただし、技人国で認められるのは人材育成やマネジメントに関わる業務であり、調理や接客といった店舗運営上の作業に従事することはできません。
一方、特定技能では飲食店など実際にサービスを提供する現場での就労が求められるため、調理や接客を伴わない本部スタッフのような役割は1号・2号いずれでも認められていません。
業務範囲を逸脱すると不法就労になる?

在留資格で認められた範囲を超えて働くと不法就労となり、雇用主と本人の双方に重大な影響を及ぼします。
ここでは、不法就労の類型のうち「非専従資格外活動」と「専従資格外活動」について整理し、その違いを解説します。
部分的に逸脱すると非専従資格外活動
在留資格で認められた活動から少しだけ外れた場合も不法就労に該当しますが、その場合は「非専従資格外活動」と判断される可能性が高いです。
例えば、技人国で就労する外国人が、本来の専門業務に従事しつつ、毎日1時間程度清掃業務を担当する場合などは、非専従資格外活動とみなされる可能性があります。
同様に、特定技能「外食業」の許可を受けた外国人が、一定期間本部スタッフとして飲食店の管理業務に従事する場合も、許可を受けた範囲内で就労していないとみなされ、非専従資格外活動に該当するおそれがあります。
非専従資格外活動は、直ちに強制送還の対象となるわけではないものの、更新時の審査で不許可になるリスクが高く、継続的な在留に悪影響を及ぼす可能性があるため十分な注意が必要です。
専任的に従事すると強制送還の可能性もある
許可範囲外の就労活動を明らかに専任的に行っている場合は、「専従資格外活動」とみなされ退去強制処分(強制送還)となる可能性があります。
例えば、技人国の資格で在留している外国人が、本来の許可された業務を行わず、一日を通して現場作業などに従事している場合は、この専従資格外活動罪に該当する可能性が高いです。
同様に、特定技能の在留資格を持つ外国人も、許可を受けた分野と関係のない業務などを長期的に行っている場合などは、専従資格外活動とみなされ退去強制の対象になる可能性があります。
まとめ
この記事では、技人国と特定技能の業務範囲の違いを整理し、両者の制度設計や重なり得る場面を具体例とともに解説しました。
さらに、業務範囲を逸脱した場合のリスクとして非専従資格外活動や退去強制の可能性についても言及し、押さえておくべき注意点を説明しました。
外国人を採用する経営者や日本での就職を希望する外国人にとって、制度の理解不足は大きなリスクにつながります。
どの在留資格でどの業務が認められるかを正しく整理し、不安がある場合は入管庁の情報を確認したうえで、専門家に相談してから採用やキャリア選択を進めることをおすすめします。
監修者コメント
技人国と特定技能で認められる業務範囲は、一部に重なる可能性があるものの、感覚的に判断するのは非常に難しいといえます。
実際に境界線を見極める必要がある場合には、在留資格変更や更新の申請時に提出する理由書などで業務内容を正確かつ具体的に記載し、その内容で許可を得たうえで従事するのが最も安全な方法です。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
e-GOV法令検索:出入国管理及び難民認定法
(URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html)
出入国在留管理庁|特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html)
出入国在留管理庁|特定技能運用要領
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html)