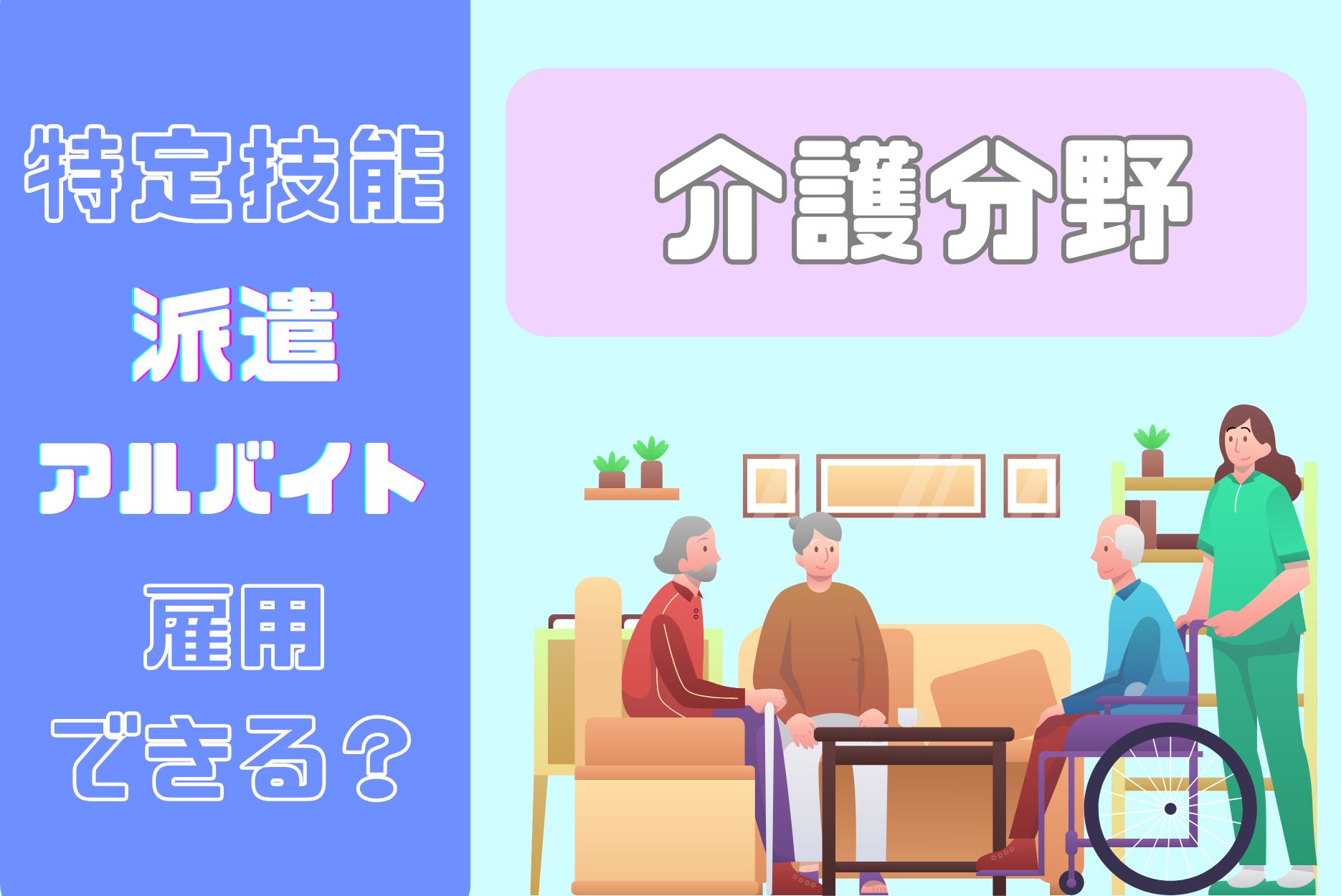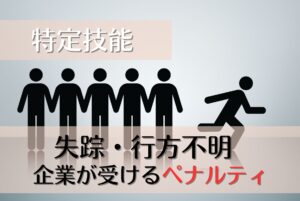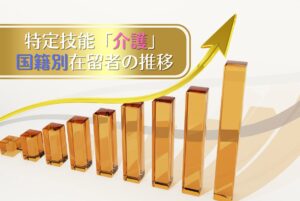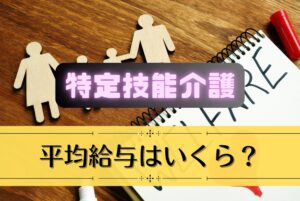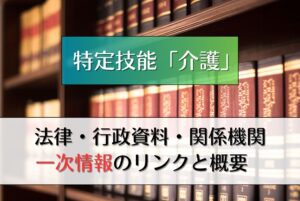介護現場では慢性的な人手不足が続いており、外国人材の採用を検討する企業も増加しています。
中でも「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用するにあたり、手続きの簡便さを重視してアルバイトや派遣といった雇用形態での受け入れが可能かどうか、疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能「介護」分野において外国人を雇用する際に選べる雇用形態や、法律上の制限についてわかりやすく解説します。
特定技能で派遣やアルバイトが認められるかどうか、また他の在留資格との違いについても具体的に説明しますので、外国人材の受け入れを検討中の方はぜひ参考にしてください。
特定技能「介護」はフルタイム雇用が原則

特定技能「介護」の在留資格で外国人を雇用する場合、制度上はフルタイムかつ直接雇用であることが必須とされています。具体的には、週あたり30時間以上の勤務に加え、年間217日以上かつ週5日以上の就労が必要です。
これらの条件を満たさないパートタイムや短時間労働での契約では、特定技能の在留資格は認められません。そのため、雇用形態の選択には一定の制約があります。
特定技能制度は、慢性的な人手不足に対応するための制度であり、短期的・補助的な働き方を目的とした雇用は制度の対象外となっています。

正社員じゃなくても雇用可能
「正社員」という言葉は、一般的に雇用期間の定めがない無期契約の従業員を指します。
これに対して、特定技能1号の在留資格には通算5年という在留期間の上限が設けられており、期間を限定した雇用契約(有期雇用)が基本となります。そのため、たとえ有期契約であっても、フルタイムの勤務条件を満たしていれば、在留資格の取得は可能です。
特定技能の在留資格申請においては、雇用契約が無期か有期かは審査の対象とはなっていません。
報酬は日本人と同等額以上
特定技能で働く外国人には、日本人と同等以上の給与や福利厚生を提供することが制度上求められています。
この基準は、国籍による不合理な待遇差を防ぐために定められています。
勤続年数や保有する資格の違いによって、賃金や手当の差が生じること自体は認められていますが、外国人であることだけを理由に、賃金や福利厚生の面で不利な取り扱いをすることはできません。
特定技能「介護」では派遣形態は認められない

介護分野の特定技能では、外国人労働者を派遣という形態で受け入れることは認められておらず、直接雇用が制度上の必須要件とされています。
一方、農業や漁業のように季節によって業務量が大きく変動する分野では、繁忙期の人手不足に対応するため、特定技能外国人の派遣雇用が例外的に許可されています。
なお、介護分野に限らず、多くの特定技能分野においては直接雇用が基本とされており、派遣による受け入れは原則として認められません。
もし派遣を受け入れるとどうなる?
介護分野で特定技能外国人を派遣という形で受け入れた場合、雇用主や派遣元、外国人本人それぞれに法的リスクが生じます。
外国人本人にとっては、在留許可の範囲を超えて就労していることになり、不法就労や届出義務違反とみなされる可能性があります。
受け入れ側や派遣元となる企業も、不法就労助長罪や営利目的在留資格不正取得助長罪といった違反に問われるリスクが高まります。
介護分野で外国人を派遣形態で受け入れる方法
介護分野で派遣従業員として外国人を雇いたい場合、特定技能外国人の受け入れは制度上認められていませんが、他の在留資格であれば派遣での就労が可能です。
たとえば、永住者や定住者、日本人の配偶者等といった「身分に基づく在留資格」を持つ外国人であれば、日本人と同じ条件で就労できるため、派遣形態で介護業務に従事させることができます。
また、介護福祉士の資格を取得し「介護」の在留資格を得た外国人も、派遣従業員として介護の現場で働くことが認められています。
そのほか、留学生や家族滞在の在留資格を有する外国人で、資格外活動許可を受けている場合は、週28時間以内という制限付きで介護のアルバイトができ、派遣形態での就労も可能です。
特定技能「介護」の外国人はアルバイト可能か?

アルバイトという言葉は、日常的には短時間勤務や副業を指して使われますが、法律上の明確な定義はありません。
ここでは特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人が、いわゆるアルバイト的な働き方を選べるのかについて解説します。
短時間労働では許可要件を満たさない
一般的にアルバイトとされる短時間勤務、たとえば週30時間未満の労働契約では、特定技能「介護」の在留資格を取得することはできません。
特定技能制度は、深刻な人手不足に直面する業界において、即戦力となる外国人材を一定の基準で受け入れることを目的としており、短時間労働を前提とした就労は想定されていません。
ただし、契約上はアルバイトとされていても、週5日以上かつ年間217日以上の勤務、さらに週30時間以上の労働条件を満たしていれば、特定技能の在留資格を取得することは可能です。
特定技能「介護」で資格外活動許可は取れるか?
資格外活動許可とは、在留資格で認められていない業務、すなわち本業以外の仕事を行う際に必要となる許可です。
たとえば、特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人が、本業とは別にアルバイトなどの副業を希望する場合には、事前に資格外活動許可を申請しなければなりません。ただし、特定技能制度はフルタイム勤務を前提としており、「本来の在留資格の活動の遂行を妨げないこと」という許可要件を満たすのが難しいため、特定技能外国人に対して資格外活動が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
個別審査によって判断されるため、絶対に不可能とは言い切れませんが、現実的には副業目的での資格外活動許可の取得は困難です。
介護分野で外国人アルバイトを受け入れる方法
介護分野で外国人を短時間のアルバイトとして採用したい場合、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用することはできません。
一方で、永住者や定住者、日本人の配偶者等といった在留資格を持つ外国人であれば、日本人と同様に就労時間や雇用形態の制限がなく、週数回や短時間のみの勤務も可能です。
また、留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人でも、資格外活動許可を取得していれば、週28時間以内の範囲で介護職のアルバイトに従事することができます。
まとめ
この記事では、特定技能「介護」の外国人雇用に関する雇用形態のルールや、派遣・アルバイトでの受け入れ可否、そしてそれぞれに関する制度上の注意点を解説しました。
介護現場で外国人の雇用を検討している経営者や担当者の方は、在留資格ごとに認められる雇用形態をしっかり把握し、法令や制度を遵守した採用を進めていくことが重要です。不明点や判断に迷う点がある場合は、専門家や行政の窓口に相談しながら、最適な雇用方法を選択しましょう。
監修者コメント
特定技能制度は、日本国外から人材を受け入れるための整備された仕組みであり、「年間1人」や「5年で10人」といった中長期的な採用計画には適しています。ただし、この制度は厳格な在留管理のもとで運用されているため、急な欠員補充など、スポット的な人材確保には不向きです。
一方、永住者や留学生など「就労系以外」の在留資格を持つ人材は、比較的柔軟な雇用条件で働くことが可能です。各在留資格の特徴を把握したうえで、目的に応じた雇用形態を選ぶことが、人手不足解消に向けた効果的なアプローチとなります。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
出入国在留管理庁|特定技能分野別運用要領(介護)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001437816.pdf)
出入国在留管理庁|分野別運用方針(介護)
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001434811.pdf)
出入国在留管理庁|資格外活動許可について
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html)