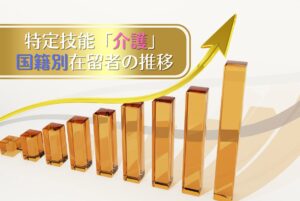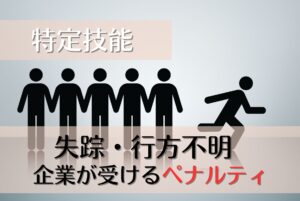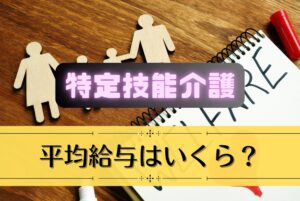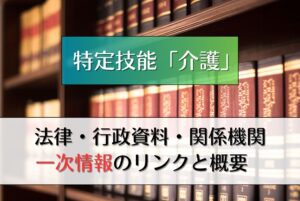人手不足の解消や人材の定着を図るには、外国人職員の将来的なキャリア設計や安定した生活基盤を支援する視点が欠かせません。
とはいえ、特定技能「介護」から永住許可を取得するには、複雑な要件や長期間にわたる準備が求められるため、「どのような道筋をたどればよいのか」「何を準備すべきか」といった不安を抱える方も少なくありません。
本記事では、特定技能「介護」から永住許可を取得するための道筋や準備の進め方を、状況に応じてわかりやすく解説します。特定技能人材の長期定着を目指す事業者や永住を希望する外国人の方にとって、今後の選択肢を整理するための指針としてご活用ください。

永住許可取得の主な要件

永住許可を取得するためには、以下3つの基本的な要件を満たす必要があります。
・素行が善良であること
・独立して生計を営む能力があること
・日本の国益に合致していること
このうち「国益に合致していること」という要件には、在留年数に関する基準も含まれており、特に特定技能「介護」から永住を目指す場合には重要です。
・3年以上の在留期間をもって在留していること
・継続的に10年以上日本に在留していること
まずは、これら5つの要件について詳しく解説していきます。
素行が善良であること
素行善良要件は、日々の生活の中で法律を守り、社会的にも非難されることのない行動を続けているかどうかが審査の基準となります。
たとえば、刑罰を受けるような重大な犯罪はもちろん、罰則がない違反行為であっても、繰り返し行われていれば評価が下がる可能性があります。
一見すると些細なルール違反であっても、申請時に過去の生活状況が総合的に見られるため、常に注意が必要です。
独立して生計を営む能力あること
独立して生計を営む能力が審査される理由は、申請者が公共の支援に頼ることなく安定した生活を維持できるかを判断するためです。
この審査では、資産や年収、職業の安定性など、複数の側面を総合的に確認されます。
また、世帯全体の収入や生活状況も重要な判断材料となり、扶養家族が多い場合には基準も厳しく見られる傾向があります。
日本の国益に合致していること
日本の国益に合致しているかどうかは、外国人の永住申請において最も重視される審査基準です。
この要件では、日本で安定的に生活しているかどうかを確認するために、長期の在留実績や犯罪歴の有無、納税状況、社会保険料の納付実績などが総合的に評価されます。
さらに、公衆衛生上の問題がないかといった健康面の確認も含めて、広い視点から判断される仕組みとなっています。
3年以上の在留期間をもって在留していること
永住許可を申請するためには、申請時点で持っている在留資格に紐づく在留期間が3年以上であることが求められます。
許可されている在留期間が1年や6ヶ月の場合などは、この条件を満たしていないと判断され、たとえ他の基準をクリアしていても、永住許可を取得することができません。
そのため、永住申請を目指す場合は、事前に長期間の在留許可を取得できるように計画的に準備しておく必要があります。
継続的に10年以上日本に在留していること
永住許可を得るには、原則として継続して10年以上日本に在留していることが求められます。
この10年のうち、少なくとも5年間は就労系または居住系の在留資格で滞在している必要がありますが、特定技能1号や技能実習はこの「就労系」の年数として認められない点に注意が必要です。
たとえば、特定技能「介護」で5年勤務し、その前後を留学や家族滞在など非就労系資格で過ごしていた場合、在留年数は合計10年でも、就労系資格での5年以上という条件を満たせないため、永住申請の要件を満たさないことになります。
そのため、特定技能1号から永住を目指すには、早い段階で在留資格の変更も視野に入れ、計画的に進めていくことが重要です。
特定技能「介護」から永住許可を取るためには

ここからは、特定技能「介護」から永住許可を取得するための具体的な方法について、状況ごとに道筋を整理して解説していきます。
どのケースでも要件や注意点が異なるため、それぞれの流れを把握しておくことが重要です。
介護福祉士の国家資格を取得する
特定技能「介護」で日本に在留できる期間は最長5年間と定められていますが、この間に介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格を「特定技能」から「介護ビザ」へと切り替えることが可能です。
介護ビザに変更後は、永住許可の要件である就労年数のカウントに含めることができるため、たとえば特定技能「介護」で5年、介護ビザで5年の合計10年間日本に継続して滞在すれば、年数要件を満たすことができます。
ただし、介護福祉士国家試験の受験資格を得るには、実務経験3年以上(従事日数540日以上)と指定の研修修了が必要となっており、実際に試験を受けられるのは4年目と5年目の2回に限られます。
そのため、実務経験を積みながら日本語能力を向上させることが合格のカギとなり、早い段階から計画的に学習を進めることが重要です。
他の就労系在留資格に移行する
他の就労系在留資格に変更することで、永住許可に必要な年数要件を満たす選択肢もあります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、事務職や営業職、通訳など多様な業務に対応できる在留資格であり、業務内容と学歴との関連性が認められれば、異業種への転職なども含め、この在留資格へ変更できる可能性があります。
介護施設内では、事務や管理部門の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するため、適切な配置転換が行われれば、同じ事業所で在留資格を変更しつつ就労年数を積み重ねることも可能です。
このように、特定技能「介護」で5年、「技術・人文知識・国際業務」で5年の合計10年継続して在留すれば、永住申請に必要な在留年数要件を満たすことができます。
居住系在留資格に変更する
居住系在留資格には、日本人や永住者と結婚した場合に取得可能な「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などがあります。
この在留資格を取得した場合、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本国内に在留していれば、永住許可の年数要件を満たすこととなります。
たとえば、特定技能「介護」で4年間日本に滞在した後、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更した場合、合計7年の時点で永住許可申請の年数要件をクリアすることができます。
ただし、年数要件以外にも国益に合致するかどうかなどの審査が並行して行われるため、全体的な要件適合性の確認も大切です。
介護福祉士の資格取得は入念な準備が大切
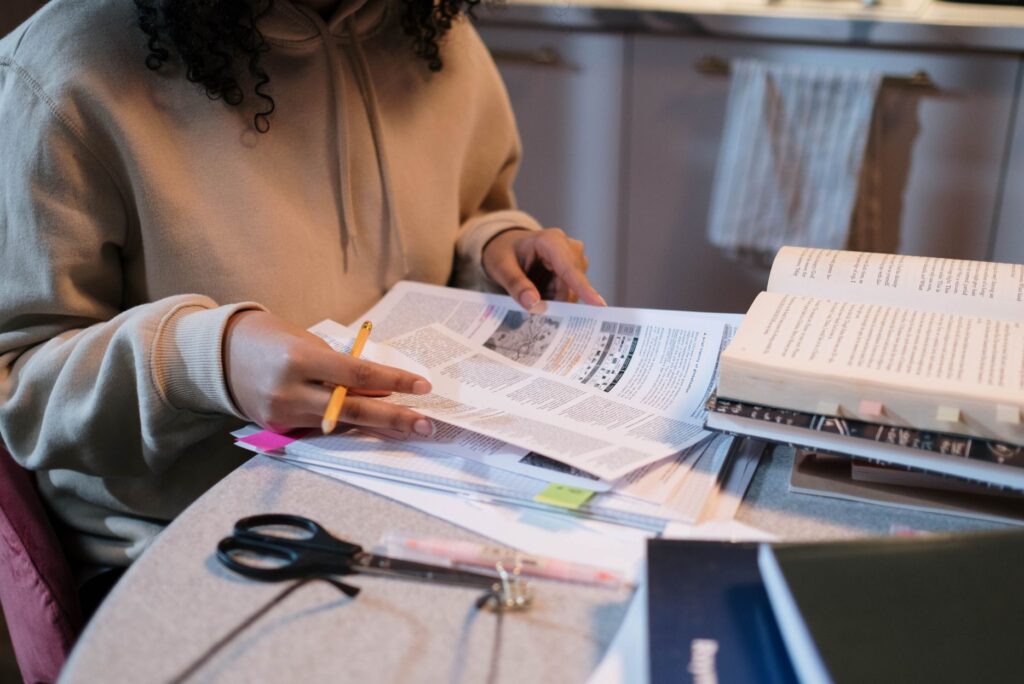
特定技能「介護」の外国人が永住許可を目指す際、もっとも確実な方法は介護福祉士の国家資格を取得し、介護ビザを経由してから永住許可を取得するルートです。
介護福祉士の国家試験を受験するには、3年以上の実務経験と実務者研修の修了が必要であり、特定技能「介護」で入国した場合、受験できるのは4年目と5年目に限られています。
また、無資格の状態から実務者研修を受講する場合は450時間の研修が必要になるため、3年目はこの研修に多くの時間を割くことが想定されます。
そのため、早い段階で日本語能力の強化に取り組み、できれば2年目までにN2レベルを目指すことが望ましいでしょう。
ただし、介護福祉士試験は日本語能力試験の合格が要件となっているわけではないため、介護福祉士の合格を見据えた効率の良い日本語学習計画を立てることが重要です。
まとめ
この記事では、特定技能「介護」から永住許可を取得するために必要な主な要件や具体的な道筋、介護福祉士国家資格取得のポイントなどについて詳しく解説しました。永住許可取得には継続的な日本での在留や就労資格の要件を満たすことが重要であり、介護福祉士の資格取得が最も現実的なルートです。
今後、特定技能「介護」から永住許可の取得を目指す方は、自身のキャリアプランや語学力の向上、受験資格の確認などを早い段階から計画的に進めていくことが大切です。疑問点や不安がある場合は、専門家への相談や最新の情報収集を行いながら、一歩ずつ着実に準備を進めていきましょう。
監修者コメント
特定技能から永住許可を取得するためには、長期間にわたる継続的な準備と計画が求められます。そのため、まずは永住許可の要件を正しく把握し、日本語の習得や介護福祉士試験に向けた学習計画を早期に立てることが重要です。
雇用者にとっても、外国人職員が永住を目指すことを支援する取り組みは、10年以上にわたる人材の安定的な定着につながる可能性があります。採用の段階から将来を見据えた支援体制を整えていくことが、双方にとって有益な結果をもたらすでしょう。
記事作成で参照した一次情報
この記事を作成する際に、参照した一次情報は以下の通りです。
出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html)
出入国在留管理庁|永住許可申請
(URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター|介護福祉士国家試験
(URL:https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html)